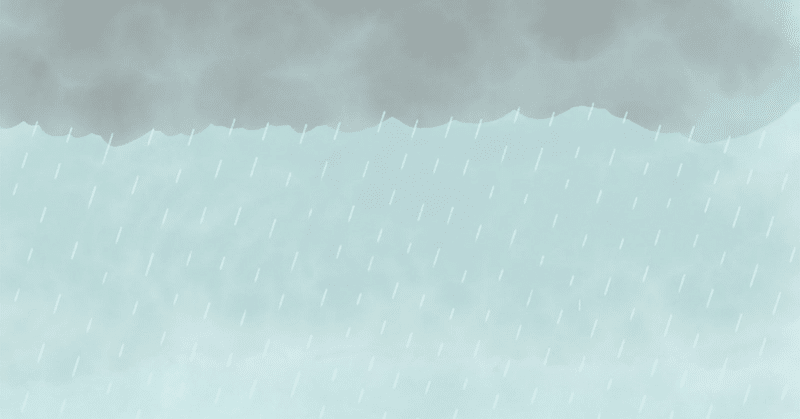
【短編小説】『簪(かんざし)』
こんな空の色にも、立派な名前がついていることを菜津子は知っていた。
三日三晩降りつづいた秋雨がやんだ。やんだはいいが、黄昏の空には象のお腹みたいに硬くて分厚い雲がいっぱいに残っていた。
思い出すのもこんな空模様の夕方のこと。
学校から大急ぎで帰った、当時八歳の菜津子を玄関で迎えてくれたのは祖母だった。
「なっちゃん、おかえり。まあ、傘もささんと!」
「ただいま、おばあちゃん! 雨な、なつが学校でたときに、ぴったりやんだん!」
「まあ。なっちゃんは晴れ女やなあ」
祖母はそう言うと、土間におりて外を覗いた。
菜津子は玄関の庇の下から曇り空を見上げて言った。
「なつはハレオンナ! なつはハレオンナ!」
……ぼんやりとしか意味はわからないけれど、きっと嬉しいことを言ってもらえたのだろうと、祖母の言葉をまねした。
「なつ、雨やんどるあいだにな、帰ろうと思うて、いそいで帰ったんで!」
「ご苦労さま、なっちゃん。やけど、道路は気をつけないかんで。きょうはおばあちゃんとお留守番しような。お空はまだ〝にびいろ〟やけん、また降りだしそうや」
「ニビーロ?」
「に、び、い、ろ。こんな色や」
祖母は空を指さした。
空には灰色よりもっと濃い色の、まるで学校のベランダに干されたままだれにも使わなくなったボロ雑巾のような雲が、べったりと張りついていた。
「きったない雲の色!」
そう言って菜津子は自慢の地蔵眉の眉がしらを目いっぱい上げて笑った。祖母も笑っていた。地蔵眉という言葉を教えてくれたのも祖母だった。
「こんなきたない雲の色が、にび色っていうんや。学校では習わんかもしれんなあ」
祖母がいつもそう言って教えてくれる言葉は、地蔵眉もそう、菜津子の生活にあたらしい色を添える、小さな花のようなかわいらしい言葉ばかりだった。
「なっちゃん、きょうもお勉強、しっかりがんばった?」
菜津子には、祖母のその質問の意図がすぐにわかった。菜津子は張りきって「うん!」とこたえた。
「じゃあなっちゃん、手ぇ洗ったら、おばあちゃんの部屋、おいで」
祖母はそう言うと、菜津子が脱ぎ捨てた運動靴を並べなおしてくれた。「ありがとう、おばあちゃん!」、菜津子は洗面所に駆けだした。
せっかく置いてあるテレビもほとんどつけず、いつも本ばかり読んでいる祖母との暮らしには、菜津子にはもう慣れっこの深い静けさが染みついていた。菜津子の父は東京に単身赴任をしていて、母はいつも日が暮れるまで働いた。一人っ子の菜津子はそれでもへっちゃらだった。家の中にはどこよりも落ち着く匂いがした。祖母のつくってくれる料理は美味しかった。その日は母の帰りがいつもより遅くなるときいていたが、菜津子は祖母との留守番の時間を特別にたのしみにしていた。
祖母から、ある「いいもの」をもらう約束をしていたからだ。
部屋で祖母はにこにこしながら菜津子を待っていた。鏡台の上に置いてあった木製の化粧箱を持ってきて、菜津子の前に置いた。
化粧箱の中に入っていたのは金属製の箸のようなものだった。太くなっている方の先端がつながっていて、そこには鮮やかなピンク色の花が付いている。
「なっちゃんは、にび色、いう言葉知って、また大人になったなあ」
祖母はそう言うと、その箸のようなものを自分の右の掌に乗せて、菜津子の目をまっすぐに見た。
「やけどまだまだ、なっちゃんは、大人になるまでにいろんな言葉をおぼえないかん」
「いろんなことば?」
菜津子は祖母の掌にある「いいもの」の説明をはやくききたくてうずうずしていたが、祖母のやさしくて力づよいまなざしに見つめられて、すこしだけ緊張した。
「そう。それは色の名前やったり、自分の気持ちをあらわす言葉やったり、いろいろや。いろんな言葉を知っとると、いろんなものが見えるようになるんよ」
「いろんなものが見えるようになるん?」
「そう。さっきなっちゃんは、にび色いう言葉を知って、空がちょっと違うふうに見えたんちゃうかなあ」
菜津子がさっき、玄関の庇の下から見上げた空、いまにも泣きだしそうな空はいつもと同じ曇り空だった。けれどそれは同時に、たしかに菜津子がはじめて見る、「鈍色(にびいろ)」をした空だった。
「見えた、ほんまや、なつ、見えた!」
「よかった。そんなふうにな、言葉をたくさん知っとると、見えるものもたくさんになってくるんよ」
——こんなによく喋る祖母を、菜津子はこのときをのぞいて、どれほど見ただろう。いきいきとした祖母の姿にも、そして祖母が教えてくれたことそのものに対しても、菜津子の小さな胸はつよく打たれ、どきどきしていた。
「なっちゃん、これはな、簪、いうものや。二股簪。ほんでこの花の色は、ときいろ、っていう色や」
「ときいろ?」
「そう。鴇色(ときいろ)。——ほら、なっちゃんはまたあたらしい言葉知って、〝ええ女〟に近づいたで」
「え! ハレオンナ!?」
菜津子は地蔵眉を上げて白い歯を見せた。けれど祖母の目はいつになく真剣に菜津子を見つめていた。
「晴れ女よりも、ええで。にび色の空の日でも、簪がよう似合う。そんな、おばあちゃんみたいな女や!」
そう言うと祖母は菜津子よりもいくらもしわくちゃな顔をいっそうしわくちゃにして笑った。
「なっちゃんがな、将来いっぱい言葉おぼえて、ええ旦那さん見つけて、お嫁さんにいくときには、この簪挿したらええ。ええ女のなっちゃんには、きっとよう似合うで」
「じゃあ、これ、なつにくれるん!」
菜津子はとびあがって喜んだ。
「うん、あげるよ。けど約束な。なっちゃん、よう勉強して、いろんな言葉、おぼえるんで」
「うん! 約束、約束! ありがとう、おばあちゃん!」
菜津子は鴇色の簪の花が、祖母のしわだらけの掌で美しくきらめくのを、夢を見るような気持ちで長いあいだ見つめていた。——
*
あの鈍色の日の祖母との約束をちゃんと守って、きょうまで生きてこられただろうか。菜津子は自問する。まだ「ええ旦那さん」には巡り会えずにいる。
祖母は五年前にこの世を去った。
菜津子は大学進学のために東京へ越してくるときも、祖母にもらった簪を手放さなかった。それは菜津子にとっての御守のようなものだった。いまも簪は下宿先のクローゼットの奥に大切にしまってある。
菜津子が祖母に簪を譲り受けてから、二十年の歳月が流れていた。
アパートの三階の部屋から武蔵野平野を見渡すと、低いところまでせまった分厚い雲が果てしなく空を覆っていた。雨がやんでいるのもきっとつかのまのこと、すぐに雨脚はやってきて、これからも幾日か鈍色の空はつづく予報だった。
テレビを消した菜津子の部屋には、祖母がいた日の実家のそれとは違う、さびしい静寂が流れていた。
……そのとき、雲間から地上に一条の光が差し込んでゆくのを菜津子は見た。光はすこしずつ束になり、空の一部を明るくした。わずかな範囲ではあるが、夕焼けが空を杏色(あんずいろ)に染めはじめた。
菜津子は空の表情の変化に見惚れながら、自分のなかにたしかに息づく「杏色」という言葉を噛みしめた。おばあちゃんとの約束はまだつづいていた。この雲の向こうには、まだ知らない名前をもつ色の空が広がっているのだろう。
簪を挿す日のことを夢想しながら、菜津子は地蔵眉を指でなぞった。
〈終〉
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
