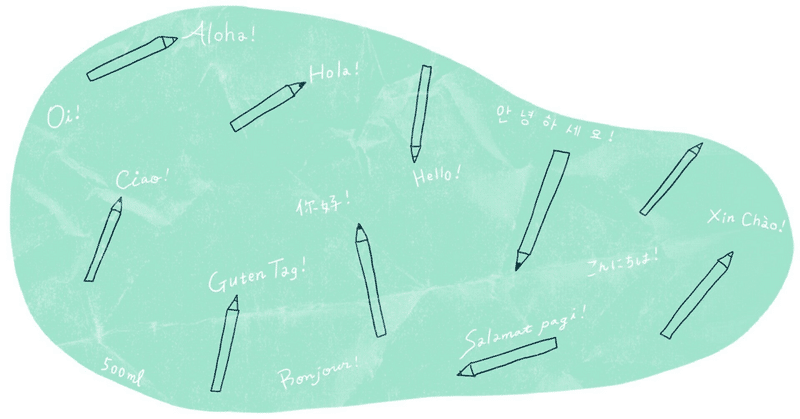
受験生と詩を学ぶ ~詩と「対話」について、国語教師として考えたこと
国語の授業の一環で、生徒さんと詩を作った。
フリースクールでの授業は、科目名こそ「国語」だが、受験対策のようなことはしない。暗記や読解にほとんど時間を割かないのは、生徒さんが受験を「あきらめている」からではなく、むしろ反対に、それ以上のもの、言い換えれば、受験をクリアしたあとの社会生活のなかで真に必要とさえる力をつけることを求めているからだ。そしてこちらもそれを提供したいと考えているからだ。
そもそも詩と受験とは、相性が良くない。詩は、本来、揺るぎない意味やメッセージを伝えるための道具ではない。だから、その「解釈」に「たった一つの正解」は必要ない、というか、一つの意味しか伝えられない詩は、どちらかというと「つまらない詩」と呼ばれてしまう。
教科書に「つまらない詩」が載っているわけはないのだが、教科書に「正解のないもの」が載っているというのもまた困った話だ。とくに受験生にとっては迷惑千万である。ぼくは受験生たちの日々の頑張りも知っているつもりだ。だから、彼らに対しては、詩の解釈も小説の読解でも、いちおう「国語の先生」と呼ばれる立場である以上、「これが正しい〝読み〟ですよ!」と教えてあげたいと思うし、教えてあげるのが自分の仕事であることもわかってはいる。
しかし、ぼくは教科書のなかの詩を前にして、しばしば複雑な気持ちになるのだ。「とりあえずこんな読み方ができますよ」というものであっても、「これが正解ですよ!」と言い切ってあげなければ、生徒は不安になる。テストでは基本的に、「最も正しい」〝解釈〟しか問われないのだから。教材としての詩は、はっきり言って、扱いづらい代物であるし、受験生にとっては、じつにめんどくさい存在である。
しかしどうだろう。意味をもたないもの、簡単にはそれがわからないように出来ているものに、無理やり「意味」を与え、それが「わかる」人と「わからない」人を区別して、彼らをふるいにかけることに、それこそ意味があるだろうか。
「ネガティヴ・ケイパビリティ」とは近頃よく聞く言葉だが、受験生にはやや縁遠い言葉かもしれない。受験生は、目標に向かって、一直線に、最短ルートで向かえることがいいに決まっている。子供たちは「答え」が欲しくて日々頑張っているのだ。それを理解し、納得し、自分の得点アップにつなげるために、受験勉強を頑張っている。詩をじっくり味わう余裕は、多くの受験生にはないだろう。
そんななかで、中学生の生徒さんと詩を作った。谷川俊太郎さんの『自己紹介』という詩をモチーフにして、「自己紹介」に関する詩を作った。タイトルは、『あなたの自己紹介』。生徒さんは講師であるぼくとマンツーマンでお互いのプロフィールを対話によって交換しあい、自分自身のことではなく、「あなた」のことを言葉にする。いわゆる「他己紹介」を詩にした。
詩を作るという行為は、いろいろな解釈を可能にする余白を言葉と言葉とのあいだに作りだすという行為だ。メッセージのためではなく、言葉そのもののために、言葉を選び抜くということだ。
生徒さんは、自由な発想力で、積極的にアイデアを出してくれ、ぼくたちの詩はあっという間に素晴らしい作品に仕上がった。一言一句にこだわり、工夫を凝らして、最良の作品が生まれたことに感激したし、生徒さんもそのプロセスを楽しんでくれたようだった。
優れた詩のなかには、優れた技巧をこらしたものも多いだろう。詩について、多くのことを知っている方が、知らないよりはもちろんいい。しかし、詩を教える・学ぶということは、言葉としっかりと向き合う姿勢を持とうとすることではないだろうか。そこに描くテーマやモチーフと、正面から向き合おうとすることではないだろうか。技巧や知識を憶えるのは、そのあとで充分だと思う。欠かせないのは「対話」である。今回の詩の場合は、そこに描く「あなた」とのコミュニケーションであり、多くの詩は、作者による自己との対話で出来ている。
詩を作るという行為そのものにも、わかりやすい「意味」はない。その試行錯誤のプロセスに「ゴール」は見えないし、そこに誰かが用意してくれた「正解」は存在しない。だから自分で「正解」を作っていくしかない。「意味」は自分で見つけるしかない。それを可能にするのは、「対話」を繰り返すということだ。
詩を読むということは、言葉との対話である。言葉がこちらに向かって何を呼び掛けているのか、耳をすまし、注意深くそれを聴きとるということだ。前のめりになってガツガツせずに、相手の呼びかけを、ときには「待つ」ということも必要である。50分や90分の試験時間のなかでは、むしろ邪魔になってしまうくらいの、その真摯な〝待ち〟の姿勢。そしてそれを可能にする心の余裕。
それでも、「わかる」ことよりも重要なその「姿勢」を持つことは、たぶん、生きていくうえでも何かと役に立つような気がするのである。
2023.10.21
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
