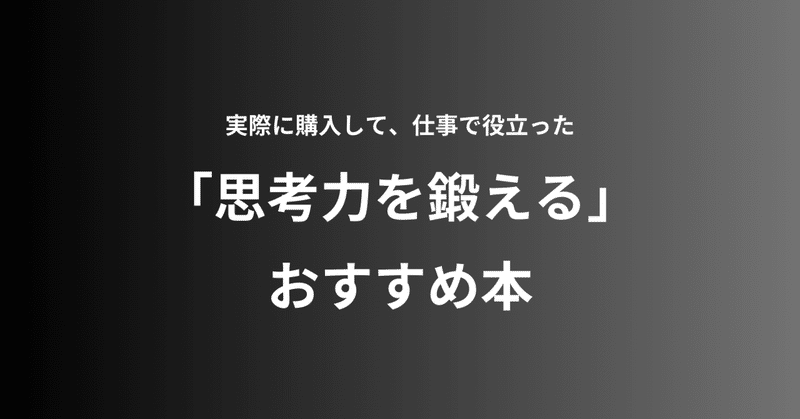
仕事で役立った【思考力を鍛える】ためのおすすめ本 7選
はじめに
本記事を読んでいただき、ありがとうございます。普段は、エグゼクティブビジネスデザイナーとして、企業の新規事業開発やサービス開発を支援をしているKATOです。年間200冊くらいビジネス本を購入して読んでいます。
今回【思考力を鍛える】ために、私が実際に購入して役立った本を厳選してご紹介します。
【思考力を鍛える】ために役立ったおすすめ本
①「イシューからはじめよ」- 安宅 和人(著)
コンサルの人なら読んでいるであろう鉄板本の1冊。バリューのある仕事を「解の質」と「イシュー度」の2軸で整理しているマトリクスは、シンプルですが、とても本質的な整理の仕方で、とても参考になります。「犬の道」でプロジェクトを推進しないよう、気を付けるようにもなりました。手元において、ふとした時に何度も読み返す、個人的に至極の一冊です。
元マッキンゼーで、慶應義塾大学の教授やヤフーのCSOを務める安宅さんによる、ビジネスで求められる「問題解決の本質」を解明する一冊。膨大な情報の中から、真に価値のある問題(イシュー)を見極めることが、成果を最大化する鍵であることを説いている。この本は、時間やリソースを無駄にすることなく、どの問題に注力するべきかを判断する力を身に付けさせてくれる。問題を解決するための具体的なアプローチや思考法が紹介されているので、問題解決力を高めたい、プロジェクトの効率性を上げたい方に必読の一冊。
②「思考・論理・分析」- 波頭 亮(著)
「思考」「論理」「分析」するということについて、いかに自分が理解したつもりになっていたのか…を気づかせてくれる良書です。
「思考」とは、思考対象にして何らかの意味合いをえるために、頭の中で上方と知識を加工すること
「論理」とは、ある根拠に基づいて、何らかの主張/結論が成立していること
「分析」とは、分けて分かるための実践的作業
「正しく考えること・正しく分かること」とは何かを理論と実践から学ぶことができ、自身の思考力のベースを整えてくれた本です。
元マッキンゼーであり経営コンサルタントの波頭さんによって書かれた本。論理的思考という大テーマに真正面から取り組み、「思考」の原論、方法論としての「論理」、「分析」のテクニックという3部構成で、体系的構造的かつ平易で実践的に解説。「考える」ことについて基礎的な土台を作りたい人におすすめしたい必読の一冊。
③「論点思考」 - 内田 和成(著)
問題解決能力が高い=論点設定が上手、であることを教えてくれた本。ビジネスにおいて本当に大事なことは、やらないことを決めること、そのために真に解くべき問題=論点を設定することが大事であることを学べます。
論点の筋の良し悪しを見極めるために、下記の3点を検討する内容は、非常に参考になりました。
「解決できるか、できないか」
「解決できるとして実行可能(容易)か」
「解決したらどれくらいの効果があるか」
元BCGである内田和成さんによって書かれた本。問題解決のプロセスの中での「問題発見」に力点が置かれている。「論点」とは何か、そしてそれをどう活用して問題を解決していくのかを体系的に教えてくれる。論点を明確にすることで、問題の核心をつかみ、効率的に解決策を導き出せることが理解できる。
また、論点を構造化する方法や、それを元にした効果的なコミュニケーションの取り方も解説しており、ビジネスシーンで実際に役立つ内容が満載。
論点を見極めて効果的に行動し、ビジネスで成果を出すための思考法を身につけたい方には、ぜひおすすめしたい一冊。
④「問い続ける力」- 石川善樹(著)
考え方や取り組みについて個人的に大好きで、よく記事や本を読んでいる予防医学者の石川善樹さんの1冊。現代経済学の直観的方法の著者の長沼さん、ライフネット生命創業者でありAPU学長の出口さん、元WIRED日本版編集長の若林さんなど、9人の有識者と対談した内容がどれも興味深く、面白かったです。
個人的には、本の前半に石川さんが書いている「考えるとは何か」「創造とは何か」について分解した内容と、「What(〇〇とは何か?)」→「How(いかにして…)」の順番で考えると思考が進んでいくことが学びでした。
<考えると何か>
(1)いかにして考え始めるのか?
(2)いかにして考えを進めるのか?
(3)いかにして考えをまとめるのか?
<創造とは何か>
「創造=新しさ×価値」→「いかにして新しさ×価値を数式にできるか」
予防医学の研究者である著者が、様々な職業/業界のトップランナー達との対談を通して、彼らの問い、考える力を紐解いていく本。
各対談は、対談者が自身の専門領域や課題認識について話し、著者がそれとなくファシリテートする形式を取る。対談者がなぜそれを考えるに至ったのか、幼少期の原体験を振り返ったり、日々の習慣を深掘ったりしながら、彼らの思考様式に漸近していく。
本書自体が全編を通じて発する「問う力はどこから来るか」という”問い”と、一流の思考人たちの個別具体的な生のエピソードは、世にある類書が教えてくれる「問いの仕方」よりも、よりプリミティブで深遠な知の形式/生成の一端を垣間見せてくれる。読み物としてとても面白く読め、問う力をこういった側面から照射する意義は一定あると思われる。
⑤「考える続ける力」- 石川善樹(著)
先ほど紹介した「問い続ける本」の続編となる石川さんの本。「問い続ける本」とセットでぜひ読んでもらいたい本です。「創造的に考えるとは何か?」をコンセプトにして書かれていて、イノベーションや創造的に物事を考えることに興味がある人には必読の一冊。
安宅和人氏、濱口秀司氏など5人の考える達人との対談内容は、至極の内容です。
IBMで無限の食材の組み合わせを提案する人工知能「シェフ・ワトソン」をつくった若い天才ラヴ・ヴァーシュニーによる創造性の定義「創造性=新奇さ(Novelty)×質(Quality)」や、本のあとがきの中の石川善樹さんのシメの言葉「価値とは、考えることでなく、実行にあり」は、非常に心に突き刺さりました。
『問い続ける力』は、石川善樹さんによる、人生やビジネスにおいて新しいアイデアを創造するための「問い」の重要性について書かれた一冊です。
様々な事例や実践的なアプローチが紹介されているため、読者は日常で実践しやすい形で「問い続ける力」を鍛えることができる一冊。問いを通じて人生を豊かにする方法を学びたい方におすすめです。
⑥「瞬考」- 山川 隆義(著)
元BCG、ドリームインキュベータ代表取締役社長の山川さんによる1冊。今まで紹介した本より、実務よりな内容が多く書かれています。仮説を一瞬ではじき出す思考法=「瞬考」と定義し、新しい時代の職種「ビジネスプロデューサー」について解説してくれている本です。
ビジネスデザイナーとして仕事をしているので、普段の実務でも活かしやすい内容が多く、今後でどのようなキャリアをつくっていくとよいのか、考える上でも非常に役立ちました。
個人的には「自分自身で鋭い仮説を生み出す」瞬考の6つの要諦(下記)が特に学びでした。
①求められる仮説とは「相手が知らなくて、かつ、知るべきこと」をひねり出すこと
②仮説構築するためには、事象が起きたメカニズムを知る必要がある。
③導き出した仮説を「メカニズム」として頭の中に格納し、それらをアナロジーで利用する
④事例などのインプット量が仮説を導き出す速度と精度を決める
⑤「一を聞いて十を知る」人でなく、「一を聞いて十を調べる」人が仮説を出せるようになる
⑥あらゆる局面でエクスペリエンス・カーブ(経験曲線)を意識する
⑦「論点を研ぐ」- 則武 譲二(著)
元BCGで、現在ベイカレント・コンサルティング常務執行役員の則武さんによって書かれた1冊。問題解決の5つのフェーズ「論点設定」→「仮説立案」→「仮説検証」→「打ち手具体化」→「打ち手実行」の中でも、重要で難しいとされる【論点設定】について、丁寧に解説された本。
この本のユニークな特徴が、プロジェクトの初期に設定する論点でなく、プロジェクトを推進する中で、論点を見直し続ける「論点を研ぐ」こと、その技法について解説している点。
消費財メーカーのA社のプロジェクトを通じて、論点を研ぐとはどういうことなのか、則武さんの考えている頭の中を覗ける感じがして、実践的に学べる内容でした(ただ読み込むにはわりとパワーがいる感じでだったので、時間的に余裕があるときに読むのがおすすめです)
【論点を研ぐ5つのステップ】
①同質化する
②前提を自覚する
③前提を問い直す
④核心を突く
⑤再構築する
ご紹介した本のまとめ
①「イシューからはじめよ」- 安宅 和人(著)
②「思考・論理・分析」- 波頭 亮(著)
③「論点思考」 - 内田 和成(著)
④「問い続ける力」- 石川善樹(著)
⑤「考える続ける力」- 石川善樹(著)
⑥「瞬考」- 山川 隆義(著)
⑦「論点を研ぐ」- 則武 譲二(著)
…最後まで読んでくださり、ありがとうございました。記事へのスキや記事のシェアをしてくれると、すごく嬉しく、次の記事を書くモチベーションにもなります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
