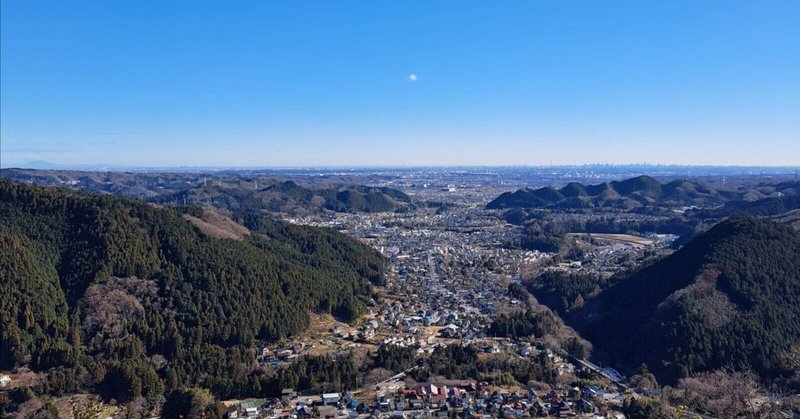
なぜ、まちづくりは上手くいかない!?(行政システムエラー説)
東京山側でゴミ拾いしたり、自然探究学習スクールなどを運営している『みちくさの達人』サクちゃんです。
真っ先に削減される研修予算
行政に長く身を置いていた時、特に不安や不具合を感じていたのが、人件費を軽く見ていることと、職員教育を軽んじていること、ジョブローテーションも軽視されていると感じたことです。
なんでも外部コンサルに依頼して、自分たちでは何も出来ないというのは問題ですが、逆に自前で立案から実行まで担当するにはあまりにも組織外での情報や経験がなさすぎる。時間外労働のための人件費は用意できても、外部で研鑽を積むための研修旅費などが殆どカットされてしまっており、国や県が用意した+実務的な研修しか実施されていなかったように思います。
そして、ころころと人事異動してしまうことで、情熱を持って計画を作っても、その熱量を持った担当ではない人間が実務を担当することになる。
分野横断的課題を解決するのが公務では!?
どんなにスキルや経験を持っていても、異動で部署が変わると、他部署関連の業務に関わることが「悪」と捉えられるような風潮には大きな違和感を持っていました。戦後すぐや高度成長期がどうだったか知りませんが、現代の複雑な社会・地域課題は様々な分野を横断しているので、セクショナリズムに捉われた働き方では対処療法にしかならないなぁと感じていました。
課題を解決ではなく、失敗しないことを重視
課題を解決するために新たなチャレンジをするのではなく、誰かに批判されないために失敗しないことを重視する風潮が一番辛かったです。市民のためではなく、組織のためを第一に考えて行動する(行動しない)体質から、何で先の大戦がなかなか止められなかったのか、分かった気がしました。コロナ禍からの立ち直りの遅さも同様で、事前に決められていた事だから、失敗すると分かっていても、想定される架空の誰かから批判を受けないために行動する/しない。
そして従来からの業務も決して止めない。という時間の経過とともにどんどんタスクが増えていく組織の在り方に将来性や効率性が感じられませんでした。
議会⋙行政でまちづくりが出来るか?
議員さんたちはまちづくりの先進地に視察に行くことがありますが、行政職員は同行しても、議会担当者のみで該当部署の職員が同行することは殆どないと記憶しています。議員さん(市民/都民/国民の代表)⋙行政職員という力関係では真の意味でのまちづくりが出来るとは思えないですね。対等な立場になって初めて建設的な議論が出来るように思います。決して議員さんが偉ぶっていると批判しているわけではありません。そういう環境を作ってしまっている土壌に問題があると思います。
ただし先述した通り、行政職員にそのスキルはないし、議会での質問や態度が、フワッとしたエモーショナルなもの、重箱の隅をつつくような質問や、執行部を落とし入れるような質の低い行動に走りがちだと、行政側のモチベーションは上がりませんし、まちづくり、国づくりが上手くいかず、負のスパイラルに陥ることになるでしょう。
ともに学んで、対等に議論ができる環境が最適です。
民間の在り方は!?
特にまちづくり活動に関わる民間団体が、自分たちの経済活動のステージである地域、商店街等について、将来のまちの在り方まで俯瞰した視座をどこまで共有出来ているか!?
行政の補助金ありきで、内容もメンバーも硬直化し、惰性で続けているイベントの時だけ連携するような枠組みでは良いまちには成らないでしょう。
この地域に魅力を感じて地域でビジネスをしたい若者や移住者を優遇せず、元からこの地域で商売を続けて、そのスタイルを変えたくない事業者さんの意向を優先的に汲む地域が人を惹きつけるのか?
これは批判ではなく、地域が柔らかくなるか?固まったままになるか?の違いを表現しているだけです。
これについても行政のスタンスが重要で、所謂地域の重鎮に忖度するしか出来ないのか?新規参入障壁を取り払うようなコーディネーター的な立ち振舞いが出来るのか?個人的な能力ではなくて、組織=システムとしての在り方が問われていると思います。
地域の本質(ストーリー)を理解しているか?
真偽は別として、とある地域で『成功事例』と話題になると、それを各地で量産化するための補助金が作られ、劣化コピーのようなプロジェクトが各地で立ち上がりますが、事例はあくまでも手段であり、本当に大切にすべきは各地域が持つ独自のストーリーに則した商品やプログラムの開発です。
「地産の食材を使用しています」、「江戸時代に建てられた寺院です」という表面的なものではなく、美味しい、歴史があるというのは当然の上で、なぜその地域に育つのか?育てられてきたのか?どのような経緯でそこに建てられたのか?なぜそのような建築様式で建てられたのか?
当地の自然環境や歴史的な背景などを提供側がしっかりと理解し、ストーリーとして体感できることが重要です。
そのためにもまちづくりに係わる行政、事業者、住民が地域資源である自然環境や歴史文化について、その本質をしっかりと学び、ストーリーとして理解していることが必須となるでしょう。
変化への適応力
成功事例として取り上げられた地域ほど実感していると思いますが、一度成功したからといって、それで未来永劫、どころか数年間まちづくりをサボって良いなんてことは絶対ありません。
絶えず変化する社会情勢、地域に関連する新たな情報、それらを敏感に感じ取る情報感度…挙げればキリがありませんが、生きものである『まち』の経営は、本当にプロフェッショナルな知識と経験が必要な重労働だと思います。
※上記あくまでも行政経験からの視点による説なので、社会課題には様々な要因があります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
