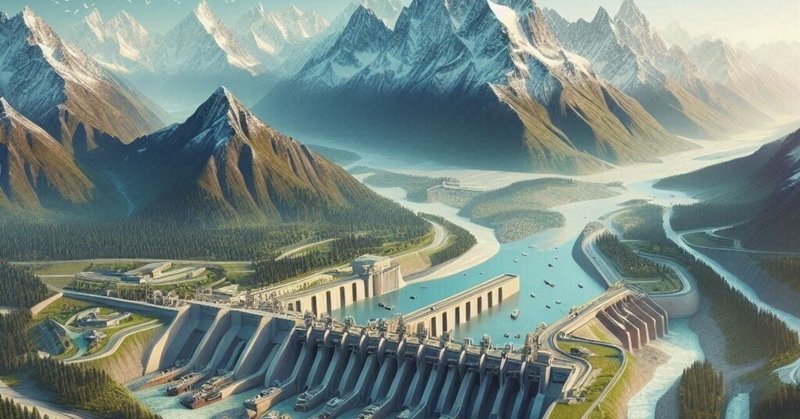
パルデアの歴史⑥ 治水と果実のパルデア史 前編
治水に奮闘してきたパルデア人たちの形跡
パルデア半島はモデルとなったイベリア半島と同じく基本的に乾燥地帯が多いが、シティクラスの3都市は必ず大きな水源沿いに存在する。それだけではなく、全体としてもいよいよ導入された三次元オープンワールドの特性を活かした「土地の高低による水の行き先」や人々の営みの中の「治水」をかなり意識して地形が作り込まれており、パルデアの歴史を考える上でも注目に値する。
今現在のパルデアの都市がどのように維持されているのか、どのように現在の形になったのかを、河川と治水の観点から考えていく。主な注目点は次の通りである。
オレンジとブドウの不在
過去のパルデア半島内の対立
自然災害や「四災」から生き残った人々の治水の戦い
主人公が阻止した現代のポケモン災害

いずれも物語中では何も語られない部分なので、基本的には「状況証拠的にそう見える」だとか、「メタ的に考えてそうじゃないと変」という程度のものの集積である。ご笑覧いただければ幸いである。
ハッコウ周辺の河川①灌漑水路と消えたオレンジ農園
2つの半島のオレンジの歴史の差異
ハッコウシティと言えば、鉱山資源の輸出のための港町から発展し、現在は有名なインフルエンサーがジムリーダーを務める、流行の最先端かつパルデアエステート本社ビルなどがそびえる現代的都市である。スペインにおいては「バレンシアオレンジ」の名の元となった都市のバレンシアにあたる。パルデア東部の最大の都市であるハッコウシティと同じく、スペイン屈指の港湾と経済の都市である。
そんなハッコウシティだが、現代のバレンシアと明らかに異なる点がある。それはオレンジの木がなく、郊外にも農地が全くない点である。主人公の家にすら生えていたのに。これはどういうことなのか。
まず注意すべき事柄として、「バレンシアオレンジ」はあくまでも「スペインのバレンシアをイメージした名前のついたオレンジというだけ」で、原産地はアメリカのカリフォルニア州であり、開発したのもアメリカ人のウィリアム・ウルフスキル氏である。別にスペインのバレンシア州で開発されているわけでも、大々的に栽培されているわけでもなく、その年代も1820年代頃と比較的新しい。なので、これ以降で言及する「オレンジ」はアメリカの「バレンシアオレンジ」のことではない。
スペインのバレンシア州のオレンジ栽培の歴史自体は規模はともかくとして「バレンシアオレンジ」よりも圧倒的に古く、この地を支配したイスラム教徒によってもたらされたと言われる。イスラム教徒にとっては「楽園の果実」であり、重要なものであった。同地での栽培についての最古の記録は11世紀であるというが、イスラム教徒がイベリア半島に侵攻し支配したのが8世紀からのことだから、それより前からであってもおかしくはない。オレンジ栽培に限らず、当時のイスラム教徒は灌漑技術に優れていたため、彼らの整備によってキリスト教徒が持て余していた同地の農業は飛躍的に発展した。
そして13世紀のキリスト教徒の作家フランセスク・アシメニス氏の記録によれば、レコンキスタによってイスラム教徒が敗北し、同地がキリスト教国のアラゴン王国となった後も、市内にはオレンジやレモンの農園があったことが報告されている。以降もバレンシアの地でオレンジが栽培されていた記録がいくつか残っており、その農業の歴史が支配者が変わっても途切れることがなかったことがわかる。18世紀からは産業化が進み、次第に現在の規模に成長した。品種は幅広く、日本で開発された品種も扱っているという。
そんな現在のスペインのバレンシアの歴史に深く根付き、「オレンジアカデミー」の名になり、「楽園」というスカーレットとバイオレットの物語の根幹のワードにまで絡むオレンジ畑がないわけがないのだが、ハッコウシティとその周辺には存在しない。身も蓋もないメタ的な視点から言えば、ゲームの売り方としてもオリーブ農園よりも見栄えがはっきりするはずだ。つまりこれは「あえて登場させていない」という可能性を考えてもよいのではないか。
自然的ではない川の形は灌漑農業の形跡?
そしてそのような視点で見ていくと、ハッコウシティの西部に灌漑農業の形跡を見出すことがどうやらできるのである。
現在のバレンシア農業もバレンシア近くを流れるフカル川を利用した灌漑から水を得ている。文明の要とも言える灌漑技術だが、前述の通りイスラム王朝時代に発展し、今日に至るまでバレンシアの豊かな農業を成立させてきた。

そしてハッコウシティ西部を見ると、パルデアの大穴の岩壁を水源地としてハッコウシティに向かって西から東へ流れる川の途中で、ほぼ直角に南進し、枝分かれする支流が確認できる。当たり前ながら基本的に川は直角には曲がらないので、これは人工的なものと言える。そんなことを人間が行うとすれば、それは広い領域に水を行き渡らせるためであって、そんな事業を行う目的とは農地の拡大以外にない。つまりこの枝分かれしている支流は、過去における灌漑水路であると言ってよいはずである。
同時に灌漑を行うような労働力の動員力は、中央集権的な構造があったことも示唆する。灌漑農業は大河周辺の古代文明の成立の証であるため、現時点では中世的な要素を持つパルデア帝国というよりは古代のパルデア王国によるものであると考えられる。実際、この灌漑水路地帯には放棄された古代の遺跡が存在している。現在のハッコウシティとの成立経緯との連続性は不明ではあるが、この遺跡がこの灌漑水路と無関係であることは考えにくい。
原因は自然現象か人為か四災か?
では、何故今日遺跡は放棄され、オレンジ農園も存在していないかについてだが、二通りが考えられる。
一つは水量の低下である。現在のこの川がやけに水位が低いことがその理由となるのではないだろうか。最初に訪れた際のコライドンおよびミライドンの能力では登れないくらいに地面の高さと水面の高さに差があり、結構な高低差である。これは現実のバレンシアでは常に問題となる旱魃の問題がモデルである可能性があり、このハッコウシティに隣接する元農業地帯についても何らかの原因で慢性的に川の水量が低下し、長らく放棄されているということではないか。この川の上流を追っていくと、向かって右に少し窪んだ経緯不明の場所があり、過去には別の水源として機能していたが、枯れてしまっているようにも見える。更に、古代遺跡の形成に関わっていそうな状況から、その「干上がり」の原因についていわゆる四災の一角であるチオンジェンが能力的に容疑者と言える事象でもある。

そしてもう一つの仮説は、水質と土壌の汚染による農地の放棄である。この川は汚染されているような描写があり、それは上流に鉱山が存在し、下流にはパルデアでも珍しいベトベターが生息していることである。ハッコウ川の一部不自然に川幅が膨らんだ形状は、過去において鉱山地帯からの大量の水の流入があったことを示唆しているように見えなくもない。
いずれにせよ、初めてこの地を訪れた時に違和感を感じる殺風景さの説明の一助にはなり得るのではないだろうか。現実のイベリア半島では数百年に渡り受け継がれてきたオレンジ農業は、パルデア半島はある時失ってしまった可能性が大きい。
ハッコウ周辺の河川② 市内に及んだ鉱毒汚染被害の気配
しるしのこだちは鉱滓ダムの決壊跡?
現在、ハッコウシティ北部の鉱山地帯を東へ流れる川は、よく見るとしるしの木立ちから鉱山地帯に流れる際に、「岩塊の壁の穴を通る」という不思議な経路を通る。この穴は侵食のためとは考えにくく、自然の光景としては不自然であり、人為的である可能性を考慮することが出来る。そして岩壁に穴をあけるという行為はまさに鉱業に従事する人々が得意とすることである。ではなぜその必要があったかであるが、前述の、ハッコウ川流域の汚染を防止することが目的ではないか。
しかしそんなことを言われてもそもそもどこに汚染があり、そうだとして何が原因なのか一見何もわからない。そこで、まずは根拠となる状況と図を先に提示する。
この地域の違和感のある状況としては以下のものがある。
・鉱山の上方にある「しるしの木立ち」の形状が「鉱滓ダム」に似ている。
・何故か毒タイプであるタギングルが特異的に生息している。
・毒タイプを扱うシュウメイが陣取っていた。
・ハッコウ川流域には灌漑水路と思しき不毛の土地がある。
・ハッコウ川沿岸に謎の大きな土砂の山がある。
・隣のハッコウ川下流の広範囲に毒タイプのベトベターが生息している。
何故かこの地域は「毒」タイプの気配がとても強いのである。ハッコウシティ周りは都会であるので、船舶の往来が多くそもそも海が汚染されている可能性は十分考えられ、これは港町のマリナードタウンにもベトベターが生息していることから恐らく正しい。だが、やや広範囲であることと、しるしの木立ちのタギングルが毒タイプであることの説明は難しい。
またこの鉱山地帯は、少なくとも現在のハッコウシティ経済の基盤を築いたことが明かされており、パルデア唯一の鉱山であり、古代パルデアの王が所有していたという金貨もここの金鉱石由来であるとするのが順当な考え方である。だが現在のハッコウシティがその産業を転換しているように、鉱山資源は有限であり、恐らく現在は貴金属の類は殆ど出ていないのではないだろうか。
そもそも鉱滓ダムとは、目的の金属を鉱滓と呼ばれる泥状の物質を谷のような地形に貯めて、固形部分を堆積させ、分離するものである。例えば、黄鉄鉱から金を取り出す際には「青化法」と呼ばれる手法を用いる。劇物であるシアン化合物に金を溶かし出すものであるが、その際に出る鉱滓をダム状の地形に貯める。
この手法は近代の鉱山において、金を取り出しやすい金鉱石が枯渇し、金の取り出しが困難であった黄鉄鉱しか出なくなってしまった際に開発されたものである。しかし、シアン化合物を含む極めて危険な排水とその堆積物を長時間ダムに貯めておくリスクの高い方法でもある。日本においても、昭和53年に静岡の金山で鉱滓ダムが決壊し、下流に甚大な環境被害を出した例があり、21世紀に入ってからも鉱滓ダムは世界中でたびたび甚大な被害を出している。そして、しるしの木立ちの地形は、ちょうどなだらかに傾斜のついた岩壁に囲まれた地であり、鉱滓ダムに似ているように見えるのである。

仮に現在の鉱山川の岩壁の穴がないとすると、それはしるしの木立ちの傾斜を下って溜まり始める。実際のところ傾斜の一番下となる場所、つまり西側には経緯不明の水溜まりがある。そして、更に水が溜まっていくことを想定すると今の地形上、少しだけ開いた岩壁の隙間から鉱山側へ流れ出していくことになる。図に表す通り、その先の鉱山の地形からするとハッコウ川の方に流れだしてしまう。ハッコウ川からハッコウシティへ流れる途中には謎の地肌の見える土砂崩れの形跡があり、過去において大きな水の流れがあったことを示すものではないか。
そして下流にそれら汚水が到達したことで前述の灌漑水路によって成立していた農地一帯も汚染されてしまい、放棄されてしまったことが考えられないだろうか。そして下流に到達したということは、ハッコウシティ市内にも汚染が及んだということになる。その場合、現在のような華やかな風景は存在しえなかっただろう。
ハッコウの産業の変化は二度である可能性
廃止された鉱滓ダムは単純に大量の土で埋めてしまい、森にしてしまうというのが一般的な手法であるそうだが、有害な重金属は地中にいつまでも残留してしまうので農地の真横で行うには、やはり極めてリスクが高いと言える。
この汚染水が何故流出したのかについては、物語としては金の供給源としてパルデア王が使用していたが四災時に破壊されてしまいオレンジ畑ごと失われた説がまず教訓的な話としてはそれらしいが、鉱滓ダムは近代的な手法であるし、放置されている遺跡が古代パルデア王国のものと考えればややオーバーテクノロジー気味である。
であれば、文字通り近代まではこの地にオレンジ畑が存在しており、古代からの建物も使用されていたがここ数百年のうちに鉱滓ダムの決壊事故が発生してしまい、いよいよ致命的なダメージを受け放棄されたと考えるべきであろうか。オレンジ畑を失ったのが近代であれば、現代のパルデア南部においてブドウと違いポツポツとオレンジの木が見られることに説明が付けられる。
そして鉱滓ダムの廃止が決定され、ハッコウシティも産業を転換していくことを強いられたのではないか。岩壁の発破と再整備によってナッペ山からの全水量は東に向けられて現在の鉱山川が形成され、前述の通りに鉱滓ダムは埋め立てられて森とされた。だが、地中に残留する重金属の毒タイプエネルギーが「毒のサル」であるタギングルを生み、現在の独特な森の状況を創り出したのではないか。現在のスター団のシュウメイら毒タイプを使用するトレーナーたちがここを陣地としたのも、彼らの手持ちポケモンの居心地がよかったから…と考えられなくもない。
検証が必要な事項
また、金鉱山の鉱滓ダムにおいては、少しでもシアン化合物の有毒性を低減するために石灰、ピロ硫酸ナトリウムや硫酸銅を添加してより毒性の弱いシアン酸へと分解するが、硫酸銅と言えば、結晶体の章で述べたキラフロルの名前の由来とされるカルカンサイト(硫酸銅五水和物)を容易に生むものである。しるしの木立ちは大穴にも近く、長年使用された鉱滓ダムへ添加された大量の硫酸銅がエリアゼロ近くの地下へ浸透し、結晶体のエネルギーによってキラフロルが生じた可能性もここで出てくる。本当にそこまで考えられていたとすれば、こちらも異常な作りこみのサブストーリーである。ただし、現在のしるしのこだちにはキラーメがおらず、どちらかというとキラーメはパルデアにおける「地下の岩盤が表出した箇所」に出現する節があるため、別に検証が必要である。
カラフ周辺の河川① オージャの湖に水没したブドウ農園?
パルデア半島のブドウの記憶
オレンジ農園がどうやら失われたらしいことはわかったが、パルデア南部では木自体は見かけることが出来る。だがブドウの木は完膚なきまでに存在していない。イメージだけは、テーブルシティに敷かれたタイルに少しだけその存在を見ることが出来る。
現実のイベリア半島においては、北西部を流れる同半島屈指の水量を誇るドウロ川とミーニョ川が広大なブドウ畑とそのワイン産業を支えており、その渓谷地帯は世界遺産にもなっている。
スペインのブドウ栽培の歴史はオレンジよりも古く、その始まりは紀元前の古代ローマ帝国の属州時代遡り、キリスト教徒たちにとっても象徴的な果実であったが、後からイベリア半島に進出してきた飲酒を禁じるイスラム教徒たちに疎まれ、イベリア半島のブドウ農園は破壊されてしまった。いくつかは生き残ったものの、その復活はレコンキスタ後になったが、前述の通り、現代ではスペインおよびポルトガルの主要な産業のひとつになっている。
バイオレットバージョンの世界のグレープアカデミーの名でもあるし、テーブルシティの広場にブドウを模ったタイルが存在するので、パルデアにおいてブドウが何らかの意味を持っていることは確かである。だがワインはおろか料理店のデザートにも出てこない。前述のブドウ産業が盛んなイベリアの北西部にあたるパルデアの北西部にはオージャの湖があるだけである。
ここから先に仮説を提示しておくと、オレンジと同じく、過去のパルデアにはブドウが存在していたのではないか?というものになる。
もう少し踏み込めば、ナッペ山を水源とした現実世界におけるドウロ川とミーニョ川と似た河川が存在し、ブドウ畑が営まれていたが、何かしらのタイミングでこれら河川の水量が激増し、農地ごとオージャの湖の下に沈んだのではないか?というものである。つまり、オレンジと同じく「いま存在しないこと」で暗に物語のテーマを描いているのではないか?ということである。ただしそれが本当に過去に失われたとして、まだいくらかは残っているオレンジと違い手掛かりは非常に乏しい。
三つの流路と小川のかけら
地道に地形を見ていくと、まずはオージャの湖から西パルデア海への三つの流路に不自然な点がある。
一番北のものが最も細く、川底には傾斜がついている。一番南のものが幅としては一番広く、こちらも川底には傾斜がついている。だが真ん中のものは傾斜ではなく滝のように流れ落ちる形になっていて、その流路の底を観察するとオージャとの境目はせり上がっている形になっており、長い時間をかけて削られた生じた流路ではないと言える。つまり真ん中の流路については、オージャの水位の急激な上昇によって水が通るようになり、その先の滝まで一気に形成された可能性が指摘できる。そして同構造は北の細い流路にも存在しており、緩やかに削られて生じた地形と言えるのは南の流路だけと言える。
次に、この地のぬしポケモンを探す際のことを思い出すと、オージャの湖の小さな島に立ち寄ることになっていた。そしてその島には一見不必要なモデリングが施されている。一部が何だか窪んでいる。なんだろうこれ?と思ったプレイヤーは多いのではないか。このような特徴を持った小島はパルデア全土でもここだけであり、何の意図でこの部分をヘコませているのだろうか。
ディンルーが「おじや」にしたブドウ農園?
まあここまで与太を重ねてきたのだ、迂遠な言い回しをしてももう後には引けない。つまり、この小島は古代の小川の断片だったんだよ!という仮説を立てざるを得ないのである。つまり四災の被災地としてのオージャの湖仮説である。

カラフシティの川の項目でも述べるが、このオージャの地にはディンルーが封印されていた。パルデア各地には彼らが残した爪痕と思われる箇所がいろいろと見られるが、ディンルーの能力は図鑑によれば次の通りである。
とても 重たい 頭を ゆっくり 振り下ろし 深さ50メートルの 長大な 地割れを 引き起こす。
例えば、遺跡が古代パルデア王国のものと順当に考えるとして、ナッペ山の南側の中腹にある雪に埋もれた遺跡はその能力からパオジアンの仕業であると言える。砂漠をはじめ不自然に干上がった箇所に遺跡があれば、四災の伝説と図鑑説明からチオンジェンの仕業であると推定できる。
では、ディンルーのそれは何かというと引用した通りだが、パルデアには表面上「深さ50メートルの長大な地割れ」が穿たれた場所がなく、この図鑑説明が何を指しているのか不明瞭である。だが、モデルのイベリアにない地形かつ、四災期にそれがあったと思われ、それが地面が穿たれることであったとすれば、ディンルーが封印される前にオージャの地でそれを行ったと考えることが出来る。そういった視点で地形を見ていくと、窪んだ小島だけではなく何もない湖なのに「人が降りていくためのスロープ構造」があることからも、過去に今よりも大きな陸地が存在していた可能性が少し現実味を帯びてくる。また、オージャの湖に注ぐフリッジタウンから流れてくる川についても直角に枝分かれしており、古代の灌漑跡と考えることができる。
更に踏み込めば、オージャの滝もディンルーによる被災時に同時に形成されたとすると、水位が上がっているように見えることにも説明がつく。大小2つのオージャの滝をその水源地から見ると、大きな方の滝は水源地から直で落ちてきている。順序を考えれば、先に大きな滝があったのなら、全量がそちらに向かい小さい方が形成されることは考えにくい。更に、同じ水源からはナッペ山の北側へ落ちる滝も出ているが、こちらの滝の落ちるところを見ると、枯れかけた滝のように細かく枝分かれて海に注いでいる。つまり、この北の滝は過去よりも水量が低下しているのである。

これらが指し示す状況をまとめると、ディンルーが巻き起こした災厄シナリオは次のように描ける。
オージャの地はパルデア北西部はモデルのイベリア半島と同様に大半が陸地であり、大規模なブドウ畑であった。
ディンルーがオージャの地に追い詰められ、抵抗した。
ディンルーの地割れを起こす能力でオージャの陸地の大半が掘り下げられてしまった。
破壊の一部がナッペ山の壁面をその上の水源地まで穿ち、小さい滝の横に新たな巨大滝が形成された。
これに伴い同水源地から北側に落ちていた滝の水量は減った。
オージャ側では、掘り下げられた地に大量の水が注ぐことになり、そこにあったものが完全に水没した。
パルデア半島からブドウ自体が消滅した。

以上から地形の辻褄を合わせると、四災前のオージャの川の経路、陸地の様子は図のようになる。現在の地形も高低差があるので渓谷地帯であったのではないか。不明瞭な箇所は多いのは否めないが、水位が上昇していることはどうやら確からしく、ブドウの不在の説明も他につけようがないことから、この辺りで結論とする。ここまでをまとめると、パルデアは象徴であるオレンジとブドウを失った歴史があることになり、セルクルタウンのオリーブ農園は最後に残った農地であると言える。
証拠に乏しいことは否定できないが、「オージャ」が「王者」でけではなく「おじや」のダブルミーニングとして「水がたくさん注がれている」と解釈すれば少しだけ真実味が出てくる気もする。「おじゃん」でもあったりして。
カラフ周辺の河川② カラフ1000年の苦闘と迂回水路
その意味は「水差し」だけでいいのだろうか?
カラフシティの「カラフ」とは某サイトにおいては「水差し」の意味であるという。確かにパルデア半島西部の唯一の水源を独占する立地にあり、隣接するロースト砂漠とは対照的な水が豊かな都市である。一見よくある砂漠のオアシスの町であるが、ここにも妙な点が存在している。それは自然的な川の要素がほぼないという点である。
不自然に動き回る「カラフ水路」
まずこの川はカラフの裏手の水源から市内に入る時は完全に舗装された水路を通り、最下層まで落ちていく。川が90度直角に曲がるわけがないので、ここは人為的である。
その後、砂漠を避けるかのようにV字谷を流れるが、このV字の谷は向かい合った斜面の色が異なっている。つまり違う土質の地表を均等に侵食している…わけがない。水流が二つの異なる土質にぶつかった時は必ずどちらか柔らかい方を削り、曲がって進んでいくはずである。だが綺麗にその中間を抜けて湖側に抜けていく。これは人工の技であると言わざるを得ない。
そして最後に湖側に落ちる…わけではなく、ナッペ山から流れてきた川に垂直に合流し、そのまま西進する。この合流後の川も、頑なにオージャの湖には落ちず、マリナードタウンの横を通って西パルデア海に落ちていく。
以上のように、どの点をとっても自然的ではなく、人工的に現在の流れが作られていると言わざるを得ない。ではその意図は何であるかだが、砂漠を迂回してマリナードタウンに水を送ることであろう。まさに「カラフ」の名に相応しいと思われる。だが不思議なのはいつから何故そうしているのか?と言うことである。
ここでロースト砂漠に目を向けると、円柱を数本備えた大型の遺跡と、転倒した物見塔がある。常識的に考えれば、地盤がどうとか言う以前の問題である砂漠に一本柱の建造物を建てる者は存在しない。このような頑丈な構造を作れる者たちであれば尚更である。つまり、ロースト砂漠とは物見塔が元々建っていた地が砂漠化した地であるということになる。
そして、遺跡についても、他の場所で見つかる円柱の長さから見るに埋もれている状況である。故にロースト砂漠の砂漠化は古代パルデア王国以後のことであると推測でき、砂漠を迂回する措置を取ったのもその後ということになる。
砂漠の古代都市の水源は?
さて、突発的な自然現象の他にはそのようなことができるのは物語上、時系列的にもチオンジェンくらいのものしかいないが、ここでは原因はあまり問題ではない。
ここで重要なのは、過去はパッとしなかったというカラフが「マリナードに対する水差し」ではなかったかもしれないということであり、ロースト砂漠の遺跡こそ「カラフ」が本来水を注ぐ対象であったこの地域のシティクラスの中心都市であったという可能性である。そして、そもそもの話としてカラフとは水差しというよりは「ワイン」を入れる器のことである。ワインといえばブドウであり、先に述べたオージャの湖がブドウ農園を擁した盆地であった仮説に繋がってくる。

実際のところ、ロースト砂漠が砂漠でないのであれば、カラフからは遺跡に向かって流れ出すのが普通である。すると流れ出るのは遺跡の西の斜面だが、ここから無秩序に水が落ちていくとマリナードタウンに直撃してしまい、地形的に辻褄が合わない。また確かにマリナードタウンは中央市場の建物が鉄筋コンクリートの近代のもので、住居も伝統様式へのアレンジをきかせるなど全体としての新しさがある。こういったことが砂漠化前にマリナードタウンの位置には急流の河川があり、都市が存在していなかったことを暗示しているのであれば、カラフを含めたパルデア西部の人々は何故、川を迂回させてまでマリナードタウンの地を造成せねばならなかったかという新たな疑問が生じる。
それはまず一つとしては港の確保であろう。いまだにハイダイがマリナードタウンへ買い付けに行くことからも、カラフシティの食料などライフラインはその多くがマリナードタウンの港湾機能に依存しているものと見られる。
カラフからセルクルタウンまでは非常に遠いし、周囲が砂漠であるなら尚更である。マリナードタウンが古代に無かったのであれば、別の港があったはずである。それがどこかというと、現実のスペインで言えばガリシアにあたる、パルデアの最北西部にある遺跡ではないか。この遺跡は北側が海に降りれるようになっており、水深としても古代港の機能としては十分と見られる。そしてオージャが盆地の農園であり、そこに水路があったとすれば運輸も問題なく行えたはずである。

だが、恐らく四災によってパルデア北西部は盆地が農地ごと沈んで主要港への道が寸断されてしまった。現代でもオージャの湖はにやけに凶暴な水ポケモンが多く住み着いており、その危険からも放棄されてしまったのだろう。
そして台地の上は砂漠化したことで中央都市を失い、内陸のカラフしか残らなかったのではないか。これであれば長い間カラフがパッとしなかった理由がわかる。
しかし地道な復興は進み、砂漠に飲み込まれるばかりとなったカラフからの川を迂回させて、台地から水が来なくなった西パルデア沿岸の斜面に繋いだ。そうして水源を確保し新しい港湾都市であるマリナードタウンを建設し、徐々に経済を回復させ、ようやく現代になってカラフが失われた遺跡都市の代わりにシティ規模を取り戻したという苦闘の歴史が見えてくる気がする。
そのように考えると、オージャの歴史と併せて「カラフ」が主役的ではなく、かつワインに絡みながら現状とは食い違っている理由が説明できる。四災によって恐らくほぼダメージを受けず新帝国が出現したパルデア南部とは異なり、北西部は現代に至る傷が残ったことが仄めかされているようである。
おわり
以上、前編は過去にパルデア人が失ったかもしれないハッコウシティとカラフシティ周辺のオレンジとブドウの形跡について仮説を提示した。後編では主人公が暗に救ったかもしれないテーブルシティを中心とするパルデア南部とその大河、ベイク高台の謎の構造について考える。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
