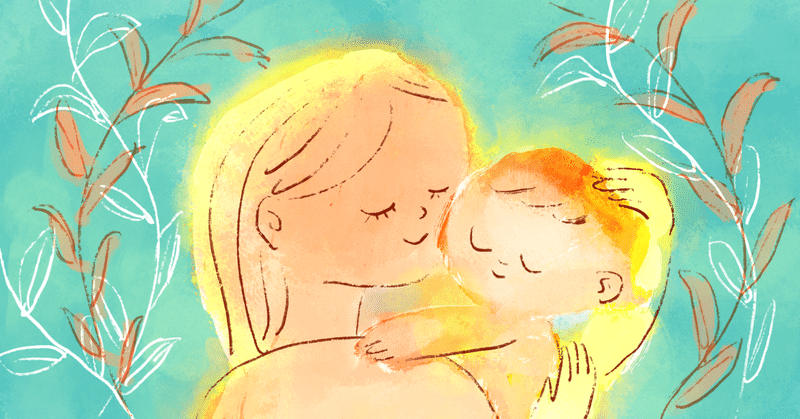
【読書録】『子育てコーチングの教科書』
おはようございます。
お読みいただき、ありがとうございます♬
さて、読書録です。
『子育てコーチングの教科書』
著 あべまさい
発行所 (株)ディスカヴァー・トゥエンティワン
読み終わってから読書録を書くまでに2ヶ月ほどかかってしまいました。
だって、
すごく良かった故にまとめるのが難しかった
のです。
ので。
結局まとめるなんてことは諦めて笑、
書きたいことだけ書こうと思います。
(いつも通り。笑)
*****
お仕事としてコーチングをされている著者の、
かざらない等身大の子育て。
娘さんという、小さくも1人の人間を前にしながら、
コーチングの知識や経験、先輩コーチの教えなどを、もう一度なぞっていかれるような、
そんな進み方になっています。
ここで、私のかなり個人的な見解をはさみますが、
子育て関連の本。
いくつか読む中で、
どこかしら「エッヘン!!!」の要素を含んでいるような気がしたり、
「言ってることはわかるねんけど、それが難しいんやんな〜」と、かえって落ち込んでしまうようなときがあります。
もちろんそれは、読み手(私)の問題。笑
そのときの子育ての状況や、精神状態を含め。
ですが。
今回の、『子育てコーチングの教科書』は、
うんうんと頷く場面あり、深い学びあり。
親の未熟さ・日々の大変さも認めてくれるような。
そんな本でした。
例えばこんなところ。
子どもを持ったことで、初対面の人、とくに年配の方から話しかけられることが増えました。赤ん坊から二、三歳ぐらいまでが話しかけられるピークのようです。(中略) 「今がいちばんいいときね」とはよく聞く言葉です。が、こっちは必死で毎日、自分の思いを通すか子どもの要求を呑むか、土俵際で汗をかいている日々で、いかにいちばんいいかを堪能していたわけではないような気がします。
わかる〜!!!!!…って思いません?
小さな子どもを持つお父さん、お母さん。
傍目に見ればとっても微笑ましく見えるような光景も、
本人たちはわりと必死。笑
よくある話です。
これは私の意見だけど、
新生児を見て、
「いつまででも見ていられる〜♡♡♡」
なんて言うのは、いつまでも見てない立場だから言えること。
でも、我が子が赤ちゃんではなくなった今、
新生児を見たら例外なく
いつまででも見ていられる〜♡♡♡
と思います、私も。
ああ矛盾。笑
本の話に戻って、
そういうこと↑↑も書きながら、あとがきには
書くことで、私にとって日々の生活、家事労働、暮らし、であったものに光が当たりました。光が当たると、それらは決して格好よくはないのですが、でも、おろそかにできない大切なものに満ちていると思えました。光を当てる作業が楽しくて…(後略)
とあり、
家庭・暮らしや子育て…仕事とは違う、ご自身の普段の生活への愛情をしっかり感じます。
というか、まず、この方の、
言葉の選び方、文章の書き方が本当に綺麗というか、私、すごく好きです◎
*****
本題へ。
1.ペーシング
ペーシングとは、相手の言うことや気持ちを受けとめる、もしそれが自分にとっては都合の悪いものであったとしても、できるだけの忍耐と思いやりを動員してしっかり受けとめる、そういうスキルです。
ここでは、仮に誰かを殴りたいと思ったとして、という例で
殴りたいという気持ちと、実際に殴るという行為の間には大きな開きがあります。実際に殴ったりはしないけれど、人はいろいろなことを頭の中で思うものです。思ったことを持ち続けるのが重いとき、誰かに話し受けとめてもらうことで初めて、正しい判断、中立的な判断に自分から戻っていけるのだと思います。
受け止めてもらうことで、自分から正しい判断に戻っていける。
よく共感が大事とか、まずは受け止めてあげること、とか見聞きしますが、
その真髄がここ↑にあるような気がしました。
なるほどね。
ここでは、この後、著者の先輩コーチの子どもさんとのやりとりも出てきていて、
コーチングの知識も経験もたくさん持っているであろう方が、
子どもを前にして、あ、あれ、無意識にペーシングをやってたんだな、とまた新たな気づきを得たエピソードも書かれていました。
知識がある方々でも、我が子の子育てに関しては、探り探り。
…少し安心します。
子どもたちのこだわりの土俵に自分から下りていく
素敵な表現だな〜と思いながら、
先日の帰宅時子どもたちが我れ先にと玄関に入っていく様子を見ながら
「どっちが先でもいいやん!!!」
と呆れながら言った自分を、少し反省。笑
余談ですが、ペーシングを変換すると
「ペー寝具」となって、ペラペラになった薄い寝具を想像してしまう…
なんてことを、この項目の最初に書かれている、
著者の感性が、ステキ。笑
2.質問
オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンのお話をされていました。
クローズドクエスチョンが、
はい・いいえ で答えられる質問であるのに対して、
オープンクエスチョンは、
5W1Hで答える質問。
そして、オープンクエスチョンの中でも「なぜ」に関しては注意が必要だとも書かれていました。
さて、著者、コーチの名に恥じないように笑、娘さんへオープンクエスチョンをします。
「宿題やった?」を改め、「宿題、どう?」と聞いてみます。
↑↑これだけで!!!
小学生の娘さんの反応が随分変わったそうです。
責められてる感じが、なくなったんでしょうね。
更に、質問について面白かったのが、この分類。
相手に自由に考えてもらう質問か
自分が情報を集めるための質問か
(コピペ上限超えたので手打ち。泣)
↑↑これ、耳痛い人、いません???
あれ?私、自分が情報を集めるための質問ばっかりしてたかな…??
と思うお父さんお母さん、多いのでは。
もちろん私もハッとしました。
忙しいと、どうしても親が把握せねばならないことばかり質問しがち。
でも親子のコミュニケーションの中に、
相手に自由に考えてもらうための質問っていう分類も存在することを、
ちょっと気に留めているだけでも、
この先少し変わっていける気がします◎
3.アクノレッジする
承認ですね。
結果承認
行動承認
存在承認
3種類について書かれていました。
素敵だなと思ったのは、
子どもから差し出されたものや言葉を受け取ること、
それもただ受け取るのではなく、大切にもらう、それを意識することが、子どもの存在を承認することになる
という記述。
私は、ありがとう〜♬と口では言いながら、結構受け流しがち。笑
受け流すんじゃない。受け取る。しかも大切に。
4.相手のために求める
コピペ上限超えたので、どんどんいきます。
相手のために求める。…え?どゆこと?
ってなりません?
…というか、求めるというワードに対して、
ちょっとネガティブ要因というか、こちらの勝手みたいな要素が含まれるように感じるのは、私だけでしょうか?
ここでの求めるは、
相手の力を信頼して、相手の未来のために求めること
という使い方のようです。
〜ねば、〜べき、の話ではない。
相手の力を信じること。
これは家庭でも仕事でも、ちょっと難しい。
自分の力を信じることも、難しい。笑
でも、信じているからこそ、その先を求めることができる。
ここで、ふと思い出したこと。
高校受験を控えていた塾の中での話。
私が通っていたのはアットホームなところで、
自習しながら、わからないところを先生に聞いて教えてもらうようなスタイル。
先生と生徒の会話は常に丸聞こえ。
そんな中で、同級生の男の子が、
自分は勉強ができないから…と、ちょっと卑屈?に言い始めた。
すると先生(母より歳上のおばちゃん先生)が、
「あんた!!自分が勉強できへんって言うけど、必死になって勉強したことあるんか!?
必死にやりもせんと、できへんって言うたらあかん!
あんたはやればできるねん!!!
勉強できへんなんていうのはな、必死にやってそれでもできへんかったときに言い!!!」
と、一喝するではありませんか!
この手の厳しさには、私は全然驚かないのだけど、
おおっ!!!と中学生ながらに思いました。
言い方は厳しくとも、その子の中に、その子の可能性を見ている言葉だから。
この先生は、私の進路に関しても
学校では難しい…厳しい…と言われていたのに
「絶対いける!!!大丈夫!!!」
といつも言ってくれた。
(そしておかげさまで志望校に行けた)
本の中身とも繋げて考えると、
自分を、自分の可能性を、信じてくれる大人が言うならば、
よし、頑張ってみよう!!!
って子どもは思うんじゃないだろうか。
そう考えると、相手のために求めるって素晴らしいこと。
*****
さて、無計画に書き進めていたら
随分長くなりました。
もう項目には分けませんが、
その他、心に残ったことは、
◎軸を持つこと。生き方にしても、子育てにしても。
そして、子育ての中で「関係を切らない」ということ。
(親子なので現実的に関係は切らないけど、
あ〜もう!勝手にして!!って、心の中で関係を切りたいとき、ありますよね…)
◎自分を抑えるということについて。
自分の気持ちを抑え込むんじゃなくて、
自分の気持ちを自覚して、そこに折り合いをつけていく、ということなのだと。
最後の章「子どもから学ぶ」では
◎親は子どもによって人生を問われ鍛えられて、
高いものへと向かわざるを得なくなっていく
◎自分のこだわりよりも、子どもが今望んでいることを適切に満たすことが、親の器を大きくする
◎自分が子どものコーチのように感じていたかれど、子どもこそが自分のコーチだった
というようなことが心に残りました。
*****
まだまだ書き切れていない、本書の素晴らしさ。
ご興味ある方は是非お読みください◎
小さな幸せがあふれる毎日でありますように。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
