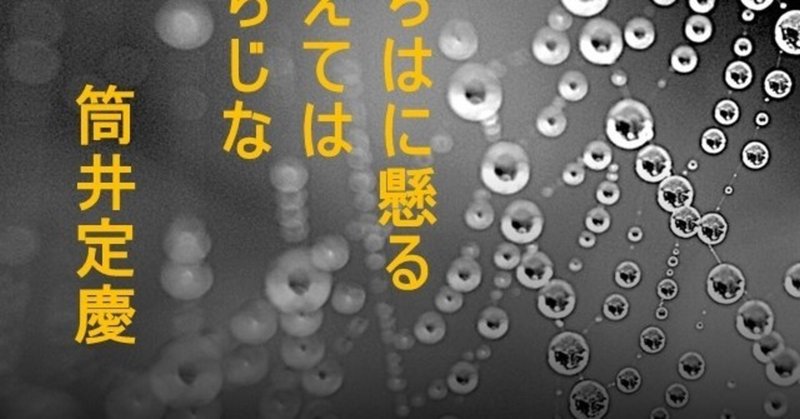
筒井定慶の辞世 戦国百人一首㊽
実は、筒井定慶(つついじょうけい)(1556?-1615?)は、よくわからない部分の多い人物である。生没年も断定できない。
つまり、この辞世がいつのものであるかもよくわからない。
だが、この歌を読んで作者の背景を知れば、歌の意味が腑に落ちるのではないだろうか。

世の人のくちはに懸る露の身の 消えては何の咎もあらじな
世間の噂にあがってしまったが、露のような運命のこの身。
消えてしまえば、何の罰も無いだろう。
筒井順慶のイトコ・福住正次が養子となって筒井定慶を名乗った。
定慶は「さだよし」と呼んでもいいが、順慶を「じゅんけい」と読むなら、定慶は「じょうけい」と読む方がいいと思い、そのつもりで書いている。
1584年に筒井順慶が亡くなってからは、定慶は豊臣秀長、その子秀保を経てた後には徳川家康に仕えた。
関ヶ原の戦いのあとで大和の郡山城主となっている。
1615年の大坂夏の陣では豊臣方からの誘いを断った。
すると、豊臣方の大野治房が定慶の郡山城を2000の兵で攻撃してきた。
定慶側は家康から預けられていた与力衆の36名とかき集めた1000人の浪人衆、農民衆、商人衆で迎え討つこととなった。
しかし、松明を掲げながら夜に行軍してきた豊臣軍を、実戦に慣れていない筒井側の物見が「豊臣軍は3万の兵!」と間違った報告をした。
もともと1000人では大城郭の郡山城は守りきることができない上、敵との兵力の差は大きすぎた。
総大将の筒井定慶は郡山城を棄て、筒井氏のもう一つの拠点である福住中定城へと移動したのである。
定慶の実弟で、やはり筒井順慶の養子となっていた筒井順斎は兄の不甲斐ない逃亡に激怒。しかし、残された兵は順斎に従わず、順斎自身も興福寺に逃亡せざるを得なかった。
その後、郡山城は大坂方の手に堕ちた。
定慶は、逃亡先の福住中定城で戦うつもりだったのだ。
1000の兵で城の守りを固めていたが、やがて徳川軍が大坂城を陥落したことを知る。
結局、一戦もすることなく郡山城を棄ててしまったことを後悔した定慶は、弟の順斎に遺書を残して大坂城落城の3日後に自害したと言われる。
定慶の辞世は、そういった事情を知った上で読むと己の行為を恥じながらも、死んでしまえば犯した過ちも許される、と望んだ彼の気持ちも分かるのではないだろうか。
本当に定慶が福住中定城で戦うつもりで準備していたのなら、全てが裏目に出てしまったことを悟った時の彼の絶望はどれほどのものだったろう。
勝った徳川方についていたというのに。
実は、定慶には自害のフリをして福住村に隠れ住んでいたという伝承もある。
弟の順斎も兄を追うようにして自害したというから、どちらにせよ、定慶が日本史上から消えてしまったことで、大名としての筒井氏は滅亡してしまった。
(*大坂夏の陣以降の定慶の動向については、逃亡が徳川家康の命令だった、定慶やその子が隠遁ののち尾張へいったなど諸説がある)
