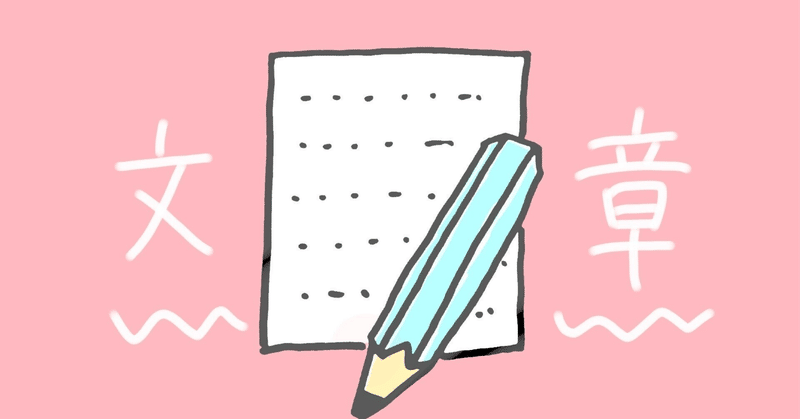
一文目は何を書けばいいのか
書き出しが難しい
文章の書き出しって、難しいです。
私は博士の院生なのですが、論文はなおさら悩みます。
1文目が上手く書けなくて、いつまでも着手できない。
どういう書き出しがいいのだろうかと、学会誌に掲載されている論文の1文目を片っ端からさらってみたりもしました。
なんとなく、こういう感じなんだなっていうのはわかります。
見よう見まねでは、書けない…!
そりゃそうですよね。
小説の出だしってこんな感じだよねって想像できたとしても、
「はい、じゃあ、あなた小説書いてみて」って言われて、
急にオリジナル作品なんて書き始められません。
イメージで理解してるのと、実際にやってみるのでは違います。
厳密に言うと、1文目だけなら書こうと思えば書けます。
昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいてもいい。
「やれやれ」とセリフから始めてもいい。
しかし、続くストーリーのことを考えると、とたんに難易度が高くなる。
それは1文目が書けている状態とは言えません。
論文執筆において、自分の研究はどういう風に始めるべきなのか。
なかなか良い落としどころを見つけられていません。
1文目で足並みをそろえる
家の本棚から適当にチョイスした本の1文目を読みます。
本書は入門者のための、平易に書かれた構造主義の解説書です。
文化ということばには、いろいろな意味や使い方がある。
「記号」ということばは、ひろくもせまくも、実にさまざまな意味につかわれることばである。
書籍の1文目において、読者が知っている唯一の情報は本のタイトルのみです。
まずは書籍の説明をするか、タイトルの中のキーワードから始めるのは自然だと言えます。
もちろんいきなり昔話を始めたり、クイズを始めたり、自由ですが、
スタンダードなのは上記のような文になると思います。
昨日、日本語の文章で大事なのは「場」なのではないだろうかという話を書きました。
特定の「場」の中において、文を組み立てていく。
自然な文章の流れを考えるときに、
最初が主題なのか、目的なのか、という文そのものの意味というより、著者と読者が同じ場所に立っているかが大事なのではないかと考えます。
論文の書き出しにおいても、様々なスタイルがありますが、
1文目から読者と距離が離れてしまうと、読者の理解が追いつくのに時間がかかるかもしれません。
これからどういう道をいくのか、今どういう世界に触れているのか、場を理解できると安心して読み進めていけます。
研究背景は論文の住所
研究背景の書き方として、マクロからミクロな話、一般的な背景からより具体的な問題意識へというアプローチをよく耳にします。
「場」の視点で考えると、これはつまり、日本の住所の書き方と同じですね。
研究の話をするにあたって、読者の方に自分と同じ位置に来ていただかないといけないので、まずは場所を正確に伝えるのは礼儀です。
日本全国の人に伝えるなら、都道府県から言うべきですし、
近くに住んでる人なら、あのマンションの301号室だよとだけ伝えればいい。
どのぐらいの範囲の人を想定して書くかによって、情報の出し方も変わってきます。
論文だと学会誌に投稿する、という場合がほとんどだと思うので、その学会に所属している人に伝わるところから始めるということになります。
書籍にする場合は、最初はその学問を知らない人にもわかる一般的な話をした方がいいでしょう。
何を書けばいいのかという中身にとらわれてしまいますが、
自分の場所をどう表現したら相手に伝わりやすいだろうか、という視点に立って最短ルートで進める方法を考えてみるというのも一つの案。
人の書き出しを真似しようとしても書けないのは、文章の土台となる「場」があることを見ていなかったからでしょう。
どういう場で書き始めている文なのかという視点で読み、そして自分の場合はどう始めるかを考えてみようと思います。
うまくいくかはわかりません(笑)
お読みくださりありがとうございました。
博士論文を書くために日々奮闘中です。
皆様の応援が研究の励みになります。
よろしければ、スキ、フォロー、サポートのほど、よろしくお願いいたします。
あかちゃん
よろしければサポートしていただけるとうれしいです。何卒よろしくお願いいたします。
