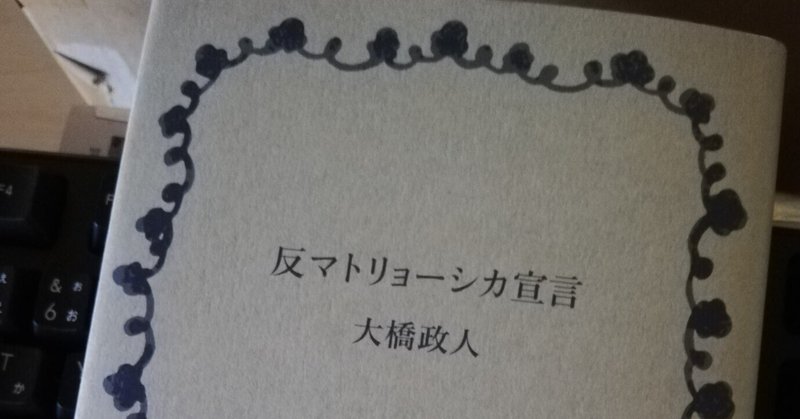
言葉の世界と実物の世界
大橋政人 詩集『反マトリョーシカ宣言』(思潮社)
「敬愛する」と自ら書くほど大橋は、まど・みちおに心酔しその詩法も近年益々接近している気がする。詩法のコアとなるのは〈言葉の世界と実物の世界〉の〈違いを見ずにはいられなかった〉不思議な世界を注視することであり、注視した後の自然の wonder を言葉に置換するムーブメントである。本書の随所に垣間みることができ、まどの世界をみている錯視感に筆者は何度も惑乱を感じた。〈海には/大きな魚が一匹/魚は/どんどん大きくなって/海の大きさと/同じになった〉(『雲とも言えない』冒頭の連)や、〈子どもたちは/危ないから/波打ち際で/海から/海面を/ベリベリベリと/引きはがしたりして/遊んでいる〉(『海』冒頭の連)は、幻視のようであるが幻視ではなく、詩的飛躍でありイマジネーションである。表現された世界のスケールの大きさもさりながら、実物の世界を注視することで固定観念や既成概念等の当然な顔で存在する世界が崩壊する。そうして崩壊した後には見知らぬ世界が立ち現れるだろう。これはつまり、社会や一般的な価値観からの視線ではなく、全てを引き剝がしたまど的視線で実物の世界をみることで現出した新しい世界像なのである。〈カタチがあって色がついたのか/色がまとまってカタチになったのか/カタチと色を/混ぜ合わせても/生きた花にはならない〉(『カタチを脱ぐ』五連目)との詩句が、それらのことを証明している。
近頃こんな事実があることを知った。植物の葉は緑色だが、緑の色がついているわけではないと。光の三原色は緑色だけが葉に留まり、他の色は反射されてみえなくなっているだけだと。まどと同じように大橋が気になっているという言葉よりも実物の世界から科学が生れ、言葉からは詩がうまれる。まどの作品や大橋の一部の詩にみることができるある種の科学的要素は、きっと同じ実物の世界から派生した二つの分野だかであるに違いない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
