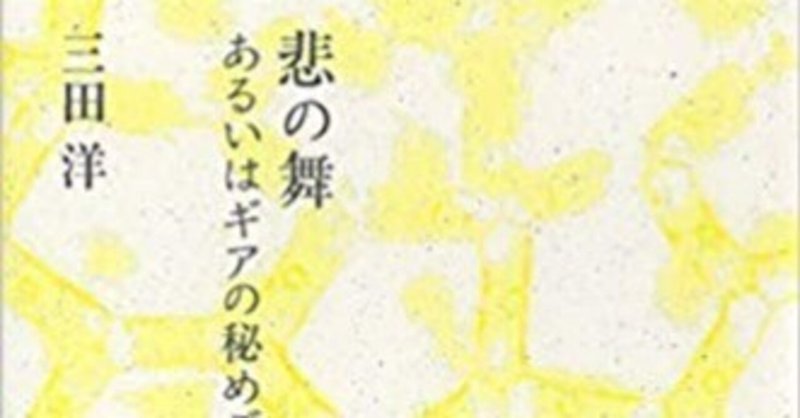
ハイブリッドな詩集
三田 洋 詩集『悲の舞 あるいはギアの秘めごと』(思潮社)
端的に述べれば実存と抒情とが併置したハイブリッドな詩集の印象をもった。その両者が詩作品によって各々の特徴をランダムに交差させ、実存が色濃くなったり抒情味が勝ったりしながら一冊を形成しているように感じた。ここでの実存は「じぶん」や「あなた」のレゾンデートルや関係性、または生の根源を問う疑問符の形を成して詩作品に顕現している。誰しも経験値によって深まった認識にも限界があり、それ以降は神の領域になる。ギリギリの磁場で表出されているのが次の表題作だ。〈悲は斜めうしろから/すくうのがよい/真正面からでは/身がまえられてしまう//悲は日常の爪先ではなく/白すぎる紙の指で/呼吸をほどこすように/すくうのがよい〉(一・二連)という姿勢をみせる。実存の疑問符は〈わたしとあなたの間〉で、〈1と2のあいだには/1.01など無数の数があるように/ひととひととのあいだにも/無数の意識や感性がつらなっている〉と関係性に楔を打つように表われたり、〈ひとりはどこにあるのか/ふたりを割るとひとりになるのか/ひとりを引くとひとりになるのか〉(一連)と、そのものズバリの作品名『実存抄』に結実したりする。しかしコアに存置するのは関係性であるよりもむしろ〈じぶん〉であるのは言を俟たない。〈これからも落下したじぶんと落下しなかったじぶんの相克はかぎりなく続くだろう(中略)わたしはいまもあの崖を落下し続けているのではないか〉(『相克の崖』より)といった懐疑となって表現されるのだ。
抒情味が勝ってくるのは『ⅲ はるかな涙』の章がある後半である。二番目の詩作品『はるかな涙――夢の地層』は〈きょうもどこかへいそいでいる/やわらかい水の領域をぬけて/手をつながれていたり/赤い焼け跡のようなところを/めぐっていることもある〉が、最後の箇所では〈問い自体が消えているのだ〉と空虚感や虚無感が滲むのは老境での感慨に浸されるからだろう。本書の絶唱であり抒情味が最も色濃い詩作品『帰郷――青海島原景』でも、最後の二行〈はたして/帰り着いていたのでしょうか〉と、答えのない問いで作品が閉じられる。この詩を読むと立原道造や中原中也の姿が瞼にチラついて仕方がない。抒情の神髄は地下水脈となって現代に通底しているからに違いない。著者は、山口県長門市生まれで金子みすゞと親戚にあたり、中也の生家がある山口市とは直線距離にして3~40㌔しか隔たっていない。時代の地層を濾過すれば水脈で行き来しても少しもおかしくはないのだ。詩心の魂も詩人同様に帰郷のベクトルを指し示して誰に憚ることがあろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
