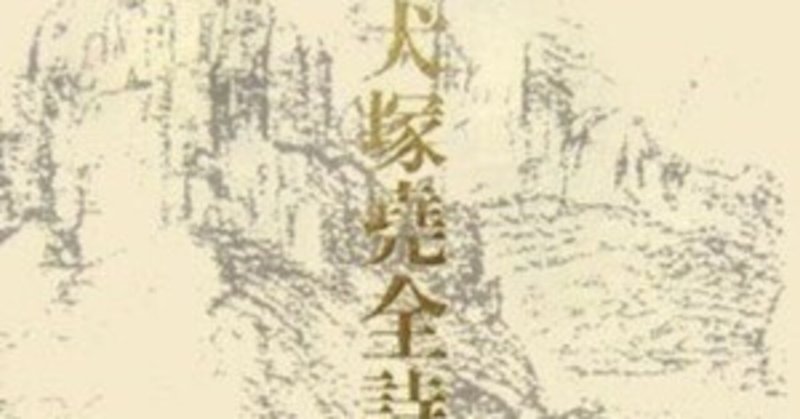
満州国、その「消えない記憶」の詩法
「てふてふが一匹韃靼海峡を渡つて行つた。」安西冬衛の、この詩を含む満州文学というカテゴリーがあることを、わたしは、川村湊や樋口覚の本を読むまで知らなかった。犬塚堯が、そこに属することはなかったが、同じ大陸からの引揚げ者である池田克己創設の「日本未来派」に犬塚の詩が特集され、詩壇の詩人たちに認知されることになるのも、なにかの因縁によるに違いなかった。
安西が満州に渡った五年後の大正十三年(一九二四)に、犬塚堯は長春で生まれている。父は、満鉄が経営していた大連の大和ホテルに勤務していた。父母ともに伊万里の出身で、彼自身も七歳の満州事変のとき、母や弟妹とともに母の実家に疎開している。さらに一高、東大卒業後に朝日新聞社入社、西部本社を希望し福岡総局の記者として社会人生活をスタートさせている。
四月に思潮社から出た『犬塚堯全詩集』を繙くと、H氏賞や現代詩人賞を受賞した四冊の既刊詩集が並び、未刊/未収録詩のほか、合唱曲/詩劇のためのかなりの分量の叙事的な長編詩が続くことに目を見張る。冒頭の第一詩集『南極』の一連目は、次のような書き出しで始まる。
鍋の中の大盗賊鴎は
まだ翼があるといい張っている
あざらしは
煮えても煮えても要求する
「海水をコップ一杯」
「南極の食いもの」より
硬質で乾いた抒情の、謎めく難解さを持つ犬塚の詩の特徴がここにはすでにある。大盗賊鴎、あざらし、それから牛、犬、虫、飛蝗、蚊、蛙、馬、熊、鼬、魚、駱駝、狼、蝿、銀狐、猿、ねずみと、大雑把に拾ってもこれだけの生き物が登場するが、それを単純な擬人法として片づけるわけにはいかない。
「鍋の中」で「いい張っている」のは大盗賊鴎であり、「煮えても」「海水をコップ一杯」と「要求する」のはあざらし自身であるからで、憑依するように自己の主体を瞬間移動し、「老眼で力なく刃をかかげた蝿が一匹/彼と僕は眼と眼を合わせた」(第四詩集『死者の書』「蠅」より)と、生き物と同じ目線で相対する視点を持つ詩を書いたりする。さらにつけ加えたいのは、「生と死の交わる領域」で、時空をたやすく超えるイマジネーションを展開する点だろう。
驚くのは
僕らの五体が石油になるということだ
何十万年もあとに
思念が油の中で揺れるというのだ
「石油」より
いつかまた僕は同じ刃で人を刺すだろう
何千年か前の冬
鼻の短い男ののどをつかんでそうしたように
「いつかまた僕は」より
犬塚の詩のピークは、これらの詩を含む第三詩集『河畔の書』だと思っているのだが、収載されている散文と年譜、付録の『資料』を読んで、憑き物が落ちるように腑に落ちたことがあった。
十七年間を過ごした満州時代の、「子どもが売られ」、若者が街路で見せしめの処刑をされる凄惨な光景を、自分のことのように感応して涙を流していたという幼少時代。その晩年でさえ、紙とエンピツに飢えた少年が心の深部に居座っていた。恣意的難解さ、韜晦的とさえ思えた寓話譚にも、生き物を躍動させる内面劇があり、生死と時空を超えて成立する彼の謎のような詩法が、虚構などではなく、実は消えない記憶の抜群のリアリティによって支えられていたのだ。
そのことを知って、彼の詩を嚥下して発症していたわたしの中の氷の痼が、春の訪れのようにゆっくり溶解してゆく思いがした。
読売新聞朝刊掲載
サブタイトル「犬塚堯全詩集を読んで」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
