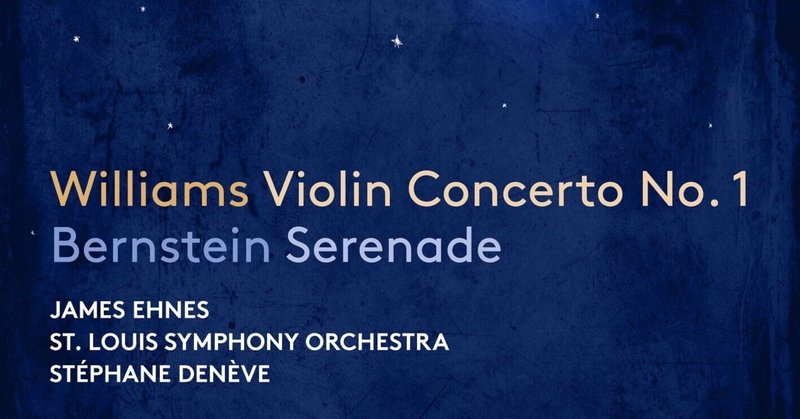
今日の1枚:ジョン・ウィリアムズ、ヴァイオリン協奏曲第1番ほか(エーネス独奏)
レナード・バーンスタイン:プラトンの「饗宴」による《セレナード》(1954)
ジョン・ウィリアムズ:ヴァイオリン協奏曲第1番(1974-76)
Pentatone, PTC5187148
ジェームズ・エーネス(ヴァイオリン)
ステファヌ・ドネーヴ指揮セントルイス交響楽団
録音時期:2023年1月、2019年11月
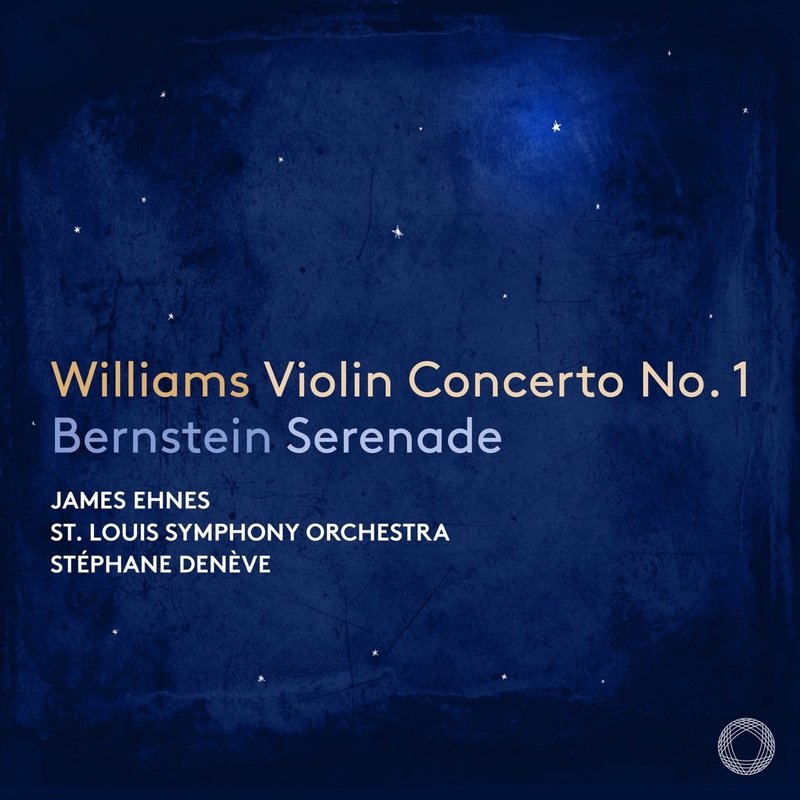
既に御年90歳を越えた作曲家ジョン・ウィリアムズは、いまだ矍鑠としてウィーンやベルリン、さらには日本まで自作を指揮しに訪れ、コンサート・ホールを熱狂の渦に巻き込んできました。しかしながら悲しいかな、そうした演奏会で採り上げられるのは彼が映画のために書いたスコアばかりで、その傍らで彼が書き続けたシリアス・ミュージックはほとんど顧みられません。ゴージャズな管弦楽法とキャッチーなメロディラインを持つ彼は、シリアス・ミュージックの分野においても引く手あまたで、特に名うての名手たちの依頼を受けて、協奏曲の佳品をいくつも世に送り出しています。その中には、既に楽器にとって中核的なレパートリーのひとつになりつつあるチューバ協奏曲もありますし、また2022年にリリースされた、アンネ=ゾフィ・ムッターのヴァイオリン独奏によって初演されたヴァイオリン協奏曲第2番の録音は、その年の協奏曲録音のベストといってもいい内容で聴き手を魅了しました。今回ジェームズ・エーネスが録音したのは1974年から76年、ジョン・ウィリアムズの作曲活動の初期に書かれたヴァイオリン協奏曲第1番です。管弦楽は作曲者と交流があり、日本では演奏会の指揮棒を彼と分け合ったことのあるステファヌ・ドネーヴが指揮するセントルイス交響楽団。
ヴァイオリン協奏曲第1番は、演奏家からの委嘱を受けて書かれた作品ではありません。ジョン・ウィリアムズの亡くなった妻、バーバラ・ルイック・ウィリアムズが生前、彼にヴァイオリンのための協奏曲を書くようにリクエストしたのが、作曲のきっかけでした。この曲を書き始めたのは妻が亡くなった直後のことで、完成した作品は彼女の思い出に捧げられています。とは言え、作品に追悼的な要素はほとんどありません。作曲家自身の言葉によれば「スタイルにおいても技法においても無調であるけれども、作品はロマン派の伝統に連なるものと思う」というこの曲は、「急ー緩ー急」の3楽章からなります。第1楽章はリリカルな第1主題と、より活発な第2主題を持ちますが、管弦楽は背景でドローン的な低音を鳴らすか、旋律楽器がヴァイオリン独奏に絡むかといった程度で、稀に訪れるトゥッティを除いては、ほとんどヴァイオリン独奏のモノローグがひたすらに歌い継がれるといっていい。第2楽章はエレジー風で、中間部に大きな高揚が置かれます。終楽章は鐘の音を模した不協和音の連続に始まり、常動曲的な独奏の動きを管弦楽が彩って、さまざまな曲想が明滅していきます。前述の協奏曲第2番が、熟達した管弦楽書法と独奏と管弦楽のバランス、そしてこぼれるようなロマンにおいてジョン・ウィリアムズの円熟を感じさせるものであるのに比べると、第1番はいくぶん中途半端で、ある種の不器用さすら感じさせるけれども、それだけにこの作曲家の出発点を示して貴重です。
この曲には今世紀になってギル・シャハム独奏、作曲者指揮ボストン交響楽団の録音が出されましたし、他にもいくつかの競合盤があります。エーネスとドネーヴ、セントルイス響の演奏は、明快に鳴らすと同時に甘さを抑制した管弦楽と、瑞々しい美音の中に芯の強さを感じさせる独奏とのコンビで、この作品に凜とした佇まいを与えることに成功しているように思えます。特に第2,3楽章での独奏と管弦楽の積極的な絡み合いは聴きでがあると言えるでしょう。
併録はレナード・バーンスタインの《セレナード》です。ミュージカル以外の作品ではもっとも人気のある曲のひとつであるこの曲は、プラトンの対話篇《饗宴》を基に、そこで交わされる「愛」についての諸説を、筋を追うことなく音化したとされます。エーネスは彼らしい芯の強い美音を振りまきつつも、ここではより嫋やかで、抑揚の大きい歌い口を駆使していきます。ドネーヴとセントルイス響はどちらかと言えばコンパクトに響きをまとめつつ、メリハリのある音楽を作り上げる。終楽章の見通しよく、美しいサウンドは聴きもので、特に独奏と弦楽器、打楽器が絶妙のバランスをみせ、十分に盛り上がりながらもキリリと引き締まったコーダに着地するさまは見事です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
