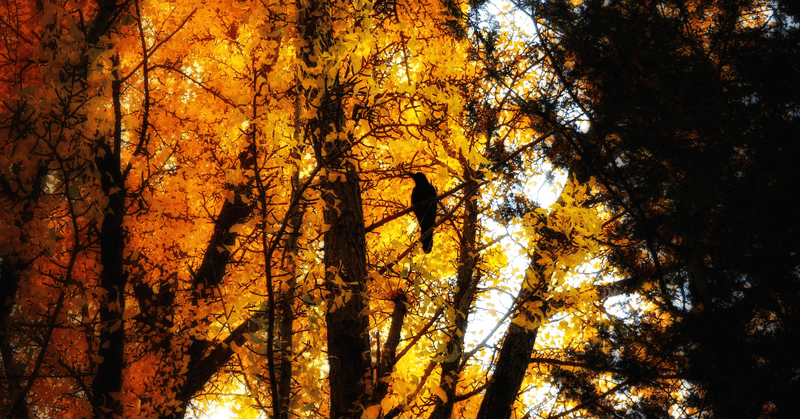
【小説】烏有へお還り 第15話
第15話
「じゃあ、家に鞄を置いたら集合ね」
三叉路の一つを直進していく栞と優愛が、振り返って手を振った。柚果も笑顔で振り返す。
昨夜、栞と優愛とスマホでやり取りをした。元気のない様子の柚果を見かけるたび心配していたと二人から伝えられ、嬉しくて泣きそうになる。久しぶりに幸せなひとときを過ごせた。
嬉しいのはそれだけではない。生徒会と部活でそれぞれ忙しい二人が予定を合わせてくれて、翌日の放課後、三人で遊ぼうという約束にまでなった。柚果にとっては楽しみすぎて、昨夜はよく眠れなかった。
見えなくなるまで二人に手を振り、柚果は駆け出した。早く鞄を置いて、二人と合流したい。
赤信号で足を止め、じりじりと足踏みをしていると、
「筧さん……よね? 筧柚果さん」
声をかけられ、飛び上がった。驚いて振り返ると、立っていたのは知らない人だった。中年の女性で、真っ白な肌をしている。
「びっくりさせてごめんなさいね」
驚いて身を引いた柚果に、女性もまた怯えたように瞬きを繰り返す。
「わたし、二年B組の高田志穂の母です」
柚果は目を瞠った。あの日、先生方に抑えられながら、廊下を連れ去られていく姿が浮かぶ。
あの時は顔までわからなかったが、こうして見ると目のあたりが志穂に似ていた。
『お願いします、ただ、聞きたいだけなんです!』
そう言って泣き叫ぶ声が耳に蘇る。大人があんな風に感情を露わにしている姿は、柚果だけでなくたくさんの生徒たちにショックを与えた。
騒然となった二年B組は、その後も授業どころではなく、志穂の死からまだ立ち直れていない生徒たちにとっては、まるで自死の原因について責められているかのように感じられたようで、次の日から何人かの生徒が休んでいる。
あの日、隣の教室で一体なにがあったのか。柚果の耳にも噂は届いた。英語の授業中、急に扉が開き、志穂の母が教室の中へ入ってきたという。
『突然ごめんなさい。高田志穂の母です』
教壇に立っていたのは柚果のクラス担任だった。呆気に取られている彼の横で、
『志穂と仲良くしてくれて、ありがとうございます。授業中にごめんなさいね。聞きたいことがあって来ました』
生徒たちに向かって志穂の母が話し始める。我に返った教師が慌てて止めようとするが、
『あの子の残したメモにね、話を聞いて励ましてくれた人がいたって書かれてたの。この中にいますか? お礼が言いたいのと、そのことについて詳しく教えて欲しいんです』
志穂の母は、かまわず一気にまくし立てた。教室は静まり返り、誰も口をきかない。
『高田さん、すみません。その件についてはB組の担任からご説明させていただいたと思いますが』
言いながら、教師が生徒たちの目から志穂の母の姿を隠すように立ちふさがる。
『ええ、わかってます。調べて下さったんですよね。けれども、クラスの一人一人に聞いてくれたわけではないんでしょう』
志穂の母の言葉に、教師が口ごもる。
『お礼が言いたいだけなんです。それで、ちょっと志穂の話を聞きたいだけなんです』
教師を押しのけ、志穂の母が生徒たちに訴え始めた。教師が彼女の腕に手をかける。
『すみません、ちょっとあちらでお話しましょう』
英語教師が志穂の母の背を押し、廊下へ押し出す。
『なにもしません。ただ、誰がどんな風にあの子の話を聞いて下さったのか、教えて欲しいだけなんです。お礼を伝えたいんです』
志穂の母は必死に抵抗するが、男性の力には敵わない。
『待って! お願いだから話を聞いて!』
志穂の母が扉にしがみつく。
『お母さん、落ち着いて下さい!』
その様子に、それまで驚き固まっていたクラスメイトたちが騒然とし始めた。
『ちょっと聞きたいだけなんです!』
『落ち着いて下さい、高田さん。別のお部屋でお話をお伺いしますから』
廊下を引きずられるように連れていかれる志穂の母が、
『お願いします! ただ、聞きたいだけなんです!』
涙ながらに訴えたのが、あの時柚果たちの耳に届いた声だった───。
教えてくれたのは伊藤さんと野口さんだ。志穂と同じ小学校だった二人は、志穂の母も知っており、同じ部活に所属する隣のクラスの人から聞いたという。
『ええ、わかってます。調べて下さったんですよね。けれども、クラスの一人一人に聞いたわけではないんでしょう』
説明済みだと主張する教師に向けた、志穂の母の言葉。思い当たるのは、志穂が亡くなってから行われたアンケートだ。
『あなたはこの学校で、いじめを目撃したことはありますか』
『自分がいじめられていると思ったことはありますか』
『あなたには誰にも言えない悩みごとがありますか』
明らかに志穂の自死についての調査だと感じた。けれども生徒の気持ちを配慮したためか、アンケートの内容は直接的な言葉を避けた曖昧なもので、柚果自身、書き終えた時は、これで本当によいのかと戸惑いが残った。
志穂の自死の理由はなんだったのか。知りたいのは柚果だけではないはずだ。けれども学校は、保護者相手には説明したようだが、生徒たちに対しては志穂の死の原因が自死であることすら明言しない。
「突然ごめんなさい。筧柚果さん。あの子と仲良くしてくれたのよね」
志穂の母が何度も瞬きしながら言った。驚いて言葉が出ない柚果に、志穂の母は「ありがとうね」と言いながら柚果の手を両手で握りしめる。
「あの子がね、亡くなる一箇月くらい前に話していたのを思い出したの。隣のクラスの子と仲良くなったんだって」
志穂の母がそう言って目を細めた。握りしめる手から熱が伝わる。志穂と同じ、熱い手のひら。
「その時、名前までは聞いていなかったんだけど、体育で一緒に倒立をしたって、そう言ってたの」
それでは、柚果の名は誰に聞いたのだろうか。背中から嫌な汗が噴き出した。
「ね、それってあなたのことよね」
柚果の足が震えた。
「でも……わたし」
言葉を探しても、なにも浮かばない。志穂の母は唇を噛み、涙を浮かべた。
「ありがとうね。志穂と仲良くしてくれて」
もう一度そう言って、両手を握りしめたまま頭を下げる。
『柚果ちゃん』
廊下で顔を合わせるたび、そう言って合図をしてきた志穂───。
「ね、あの子の話を聞いてくれたっていうのは、柚果ちゃんなのかな?」
志穂の笑顔は、いつも無理に作ったようにわざとらしく、目はどこを見ているのかわからない。
「……違います」
あの笑顔。見ていると胸がざわついた。だからいつも、おざなりに手を振っていた。
「教えてくれるかな。あの子の話。どんなことでもいいの」
志穂の母が柚果の顔を覗き込む。必死で顔をそむけた。
「ごめんなさい、わたし、志穂さんとそんなに親しくしていたわけじゃないんです」
志穂の母が瞬きを繰り返す。眉尻が下がるのを見て、心が痛む。
「ごめんなさい、わたし、もう行かなきゃ」
栞と優愛が待っている。頭を下げ、踵を返した。信号が青に変わる。立ち去りかけた柚果の背中に、志穂の母の声が響いた。
「誕生日だったんです」
強い口調ではなかった。それでも、柚果の足が止まる。
「亡くなったあの日は、志穂の誕生日だったんです」
志穂の母が鼻を啜った。
「あの子の残したメモに、こう書いてあったの」
柚果はそっと顔を向けた。志穂の母の目から、はらはらと涙がこぼれた。
「『話を聞いてもらえてすっきりした。わかってもらえてウレシかった』って」
青信号が点滅する。けれども、柚果はその場から動けなかった。
「あの子の話を聞いてくれた人は誰なのか、それだけでも知りたいんです……」
引き絞るような志穂の母の声に、柚果は息を呑んで立ち尽くした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

