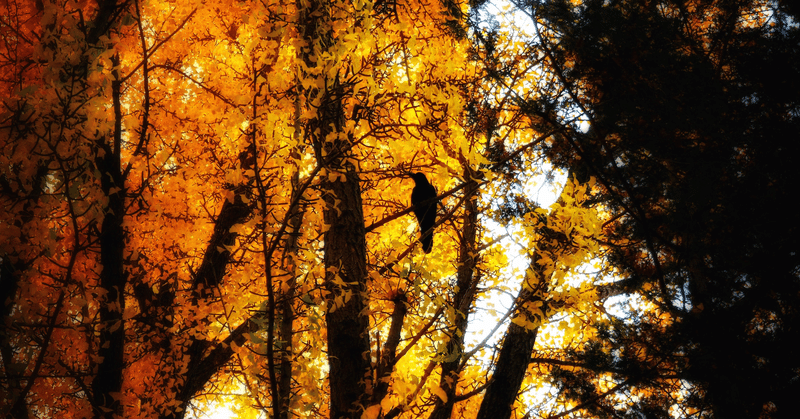
【小説】烏有へお還り 第2話
第2話
張り出した屋根の下で待っていると、目の前にダークグリーンの車が停まった。運転席の吉川が手で合図をする。
後部座席には女の子が二人乗っていた。髪の長い方の子には見覚えがある。確か、ドリンク売り場にいた子だ。
「すみません、ありがとうございます」
助手席に乗り込み、雨が振り込まないように慌ててドアを閉めた。後部座席の二人にも「こんにちは」と挨拶をすると、
「こんにちはー。てか、お疲れさまでーす」
長い髪の女の子がそう言って、指を使ってなにかのポーズをした。
もう一人の眼鏡をかけた女の子は、さな恵に目を向けようともせず、黙ったまま窓の外を眺めている。
「さな恵ちゃん、ごめんだけど、ちょっとセンターの方に寄ってもいいかな? 置いてこなくちゃいけない荷物があって」
車を発進させた吉川が、前を向いたまま親指で後方を差す。後部座席ではなく、その奥のトランクを意味しているのだろう。
「ええ、もちろんですよ」
「ごめんね。すぐ済むから」
ひまわりセンターこと、フリースクールの入っている生涯学習会館は、お祭りの会場となったふれあい広場の目と鼻の先だ。
「あーお腹空いた」
後部座席で長い髪の女の子が言った。さな恵がバックミラー越しにちらりと目をやると、彼女はしきりに髪を触りながら、
「あーあ、せっかく気合いの巻き髪だったのに、雨のせいでめちゃ崩れたー。サイアクー」
独り言のように呟く。
「急に降ってきたものね。濡れちゃったよね」
女の子はさな恵の相槌が耳に入らないかのように、
「お腹空いたー。お昼なにも食べてないし」
「えっ、どうして」
さな恵は驚いて振り返った。シートベルトの中で身体をよじり、女の子に顔を向ける。
「そんなに忙しかったの?」
目の前にお腹を空かせている年少者がいると思うと、心が痛む。ほんの六年くらい前は、さな恵も目の前の女の子と同じ高校生だった。運動部に入っていたためか、いつでも腹を空かせていた。持参した弁当の他に購買部でパンを買い、部活動が始まる前と後にこっそり食べたものだ。
「そっか……ドリンクの方、大変だったのね。代わってあげたらよかった」
さな恵の言葉に、女の子はシートから背中を離して前のめりになると、
「ううん、違う。アサミ、お金ないんだもん。お母さんがね、お金くれないの。だからアサミ、いつもお昼食べられないの」
耳を疑った。横目でちらりと吉川を見たが、彼女の目は前方の信号に向いている。ワイパーが拭ったフロントガラスに、ぽつりと小さな雨粒がつく。
「だからね、アサミ、みんなはいいよ、お昼ご飯食べてて、だってアサミはお金ないからご飯食べられないしって、ずっと一人で『いらっしゃいませー!』ってやってたの。したらめっちゃお腹空いた」
返答に困り、もう一度吉川に目をやった。視線に気づいたのか、吉川がさな恵に目配せをする。少しホッとした。
果たして本当のことなのか、それとも冗談なのかはわからないが、どうやら吉川はこのアサミという女の子のことを把握しているのだろう。
「いつもはね、みんながお昼食べてる時は一人で時間つぶすの。だってヒマじゃん」
アサミは止まらずに話し続けている。戸惑いながらも、さな恵は後部座席に顔を向けた。
「いつもって……」
「いつも、センターにいる時。でもアサミ、あんまりお腹空かないの。最初はつらかったけど、今はなんか食べないのが普通、みたいな」
聞き手のことなどアサミは気にしていないようだった。さな恵の反応などおかまいなしに、一人で話し続けている。
車は生涯学習会館の駐車場に入っていった。エンジンが止まり、カーステレオから流れていた音楽がふつっと静かになる。
「ごめん、ちょっとここで待っててね」
吉川がそう言い置いて、車から出ていった。水溜まりを避けながら、建物に向かって走っていく。
「あーあ、家に帰ってもお母さんいないだろうな。アサミいつも一人で夜まで待ってるけど、もし冷蔵庫になんも入ってなかったらさすがに死ぬ」
アサミの独り言は止まらない。どこまで本当なのか。もし本当のことだとしても、どこまで深刻に扱っていいのか、さな恵はただ困惑するばかりだった。自分はただ、今日一日お祭りの手伝いにやってきただけなのだ。
息苦しさを感じて、少し窓を開けた。すると、雨がやんでいるのがわかった。
「家に帰ってドア開けると、お母さんの煙草の吸殻で家中がすごい匂いで、アサミ急いで窓開けるの。でも雨の日は」
「ね、雨やんでるよ。ちょっと外の空気吸おうか」
止まらないアサミの話を聞いていたら、少し気分が悪くなってきた気がした。なんだか車の中の空気が淀んでいる気がする。考えてみたら、閉め切った小さな軽自動車に四人も乗っていたのだから当然だ。
アサミともう一人の女の子の返事を待たず、さな恵は助手席のドアを開けた。雨上がりのひんやりした空気を鼻から吸い込む。
「ほら、二人とも。外の空気が気持ちいいよ」
話の腰を追って逃げた罪悪感をごまかすように、後部座席に向かって明るく声をかけると、アサミは素直にドアを開けて外に出てきた。意外にも、もう一人の女子高生もドアを開けた。
「あれ、こっちでも模擬店出してたのかな」
生涯学習会館の入り口の屋根の下に、ワゴンが置いてあった。寄ってみると、駄菓子がいくつか入っている。
「売れ残りを運んできたのかもしれないね」
さな恵の言葉に、
「あーお腹空いた。なんか買いたいなー。でもお金ないし。あっ、これ一つくらいなら十円で買えんじゃね」
早口で言ったアサミが、お菓子の大袋を手に取った。袋の上部を両手でつまみ、肘を張る。
「あっ、ダメだよ!」
慌てて制止したが、遅かった。ばりっという音と共に袋が開いた。中からアサミが個包装された駄菓子を取り出す
「ダメじゃない、勝手に。センターのものかどうかもわからないのに」
アサミの手からお菓子を奪い返した。なんてことだろう、大人である自分がついていながら。
「だって、お腹空いたんだもん」
悪びれない様子に嘆息した。個包装された駄菓子と、大袋をそれぞれ手にしたまま、助けを求めて建物の中に目を凝らす。ひまわりセンターは三階だと言っていた。しかし吉川が戻ってくる気配はない。
よく見ると、廊下の奥で一室だけ明かりが漏れている扉があった。職員がいるようだ。
「これ、売ってもらえるかどうか聞いてくるから、二人は車に戻ってて」
言い置いてから、さな恵は明かりのついている部屋へ向かった。ノックして扉を開けると、ひっつめ髪の年配の女性が一人だけ座っていた。
「すみません、これ、入り口に置いてあったお菓子なんですけど、ごめんなさい、開けちゃったんです。売ってもらうことってできますか」
さな恵が尋ねると、年配の女性は困惑したように、
「あー……そうねえ、どうしたらいいかしら」
と首をひねっている。
「おいくら払ったらいいでしょうか」
さな恵の言葉に、女性はますます困ったようになり、
「ごめんなさい、わからないわ。値段なんて書いてないものね」
お菓子の袋を裏返しにする。
「そしたら、ちょっと多めに置いていきますので……」
財布から硬貨を取り出したさな恵に、女性は慌てたように、
「ちょっと待ってて。誰か他の人に聞いてくるから」
と言い、部屋を出て行ってしまった。しばらく待つも、女性は一向に戻ってこない。さな恵は時計に目をやった。窓の外はすっかり暗い。
あの場に残って、吉川が戻ってくるのを待って聞けばよかった。自分の判断ミスを嘆いた。扉を開けて廊下を窺うが、女性は戻ってこず、ここから離れるわけにもいかない。
じりじりしながら待ち続けると、やっとさっきの女性が別の若い男性職員を連れて戻ってきた。話が伝わっていないらしく、さな恵がもう一度事情を説明すると、男性も困惑した顔になる。
「すみません、どうすればいいのか、僕もちょっとわからないですね」
必死で落胆を隠しながら、
「わかりました。あの、そしたらひまわりセンターの吉川さんに聞いてみます」
そう言って、さな恵は二人に頭を下げた。未会計のお菓子を持ち去ることに抵抗があったが、開けてしまったものは置いていけない。持って行って吉川に聞くしかない。
ともかくこの場を離れられることにホッとする。玄関を出て、吉川の車に向かった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

