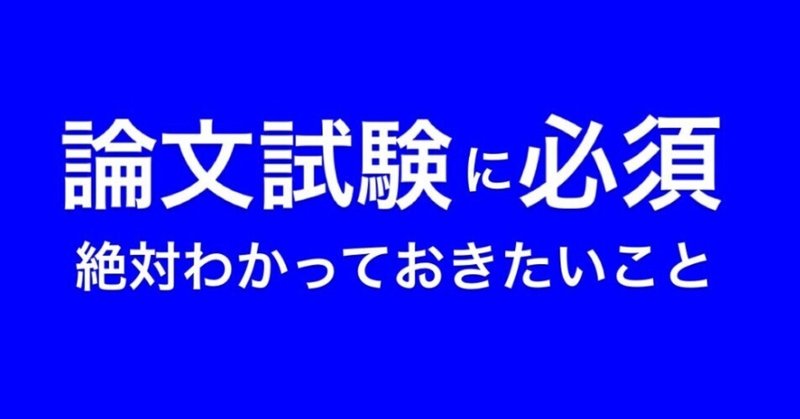
弁理士試験攻略のポイント
この弁理士試験noteのここまでの総括です。
#001では、弁理士試験合格のカギは短答合格であることをお話しました。しかし、「短答式試験の勉強」だけをしていても短答には合格できず、「論文式試験の勉強」こそが、短答合格のための王道であることをお伝えしました。
#002では、弁理士試験(特に論文)は、「知識を問う試験」ではなく、「具体的な事案に対する知的財産権法の適用について問われる試験」であることをお話しました。つまり、知識の勉強であるインプットにいくら時間を割いても不十分であり、アウトプットの勉強をいかにこなすかが重要であるとお話しました。
#003では、具体的な事情に条文を適用を検討するときは、その条文だけではなく、必ず競合する他の条文との関係で問題となるため、その条文だけを理解しても、具体的な事情を解決する答えは出せないとうお話をしました。これを解決するには条文の真の理解(制度全体における当該条文の位置付けの理解)を手に入れる必要があり、これはアウトプットの勉強を通じて、少しずつ、少しずつ、視野を広げていくことが重要であるとお伝えしました。
#004では、具体的に、弁理士試験では何を求められているかという観点で、「趣旨」に裏付けられた「法解釈」の展開についてお話しました。以下、重要な点でなので、#004の記事のまとめを引用します。
弁理士試験は、「具体的な事案に対する知的財産権法の適用について問われる試験」です。しかし、条文の文言は抽象的であり、具体的な事案にそのまま適用することはできません。そこで、条文の文言を「解釈」し、検討している事案に適用できるように言い換える必要があります。そしてその「解釈」は、条文の「趣旨」をどのように捉えるかによって決まります。「趣旨」は、その条文を解釈する時点における様々な要素を考慮して、総合的に判断する必要があり、その代表的な考慮要素として、①立法者の意図(青本を参照)、②当該条文の効果、③他の制度・条文との関係、を少なくとも検討する必要があります。論文試験では、上述のプロセスを言語化すればよいだけです。
#006では、この弁理士試験noteで1番お伝えしたい、法的三段論法について詳細に説明しています。法的三段論法をマスターすれば、はじめてみる問題も正解にたどり着くことができます。法的三段論法は、以下のテンプレートで練習することができます。

各記事では具体例も記載しつつ、書籍なら編集者に削除されるくらい、繰り返し詳細に記載しています。
上に書いた短いまとめでピンとくるところがなければ、あなたはその点を理解していない可能性がありますので、ぜひとも各記事に飛んで読んでいただきたいです!
みなさんの受験勉強に少しでもお役に立てれば嬉しいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
