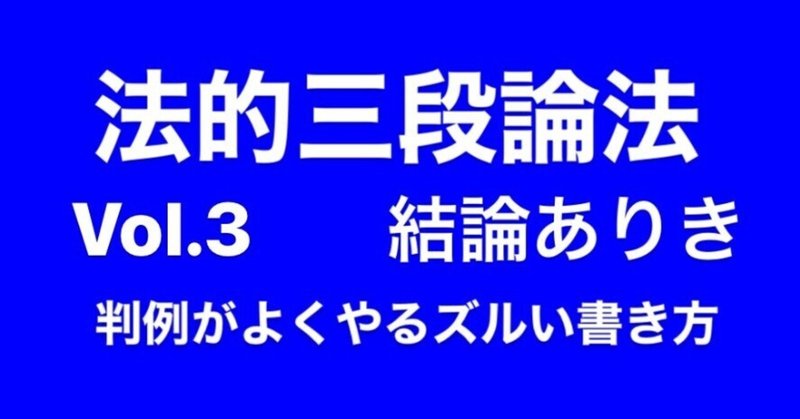
【弁理士試験】#008 法的三段論法、三段目
#006と#007では、長々と法的三段論法の話をしてきました。本日は、補足として、判決がよくやる結論ありきの法的三段論法の話をします。
この記事は、法的三段論法の本質について、少しレベルが高い話も含まれているので、まずは#006や#007を読んでいただき、余力がある方にお付き合いいただきたい内容です。
さて、本日のきっかけは、法的三段論法テンプレートにおけるステップ(Ⅱ)・(Ⅲ)「趣旨・例外」「必要性・許容性」につき、その違いについて質問をいただいたことです。みなさんにも共通した疑問になると思われますので、個別の解答ではなく、noteでまとめます。
(質問ありがとうございます!このような質問をいただくことで、noteシリーズの質が向上していくと考えていますので、大変助かります。)
法的三段論法における趣旨・例外の意義
法的三段論法は、以下の(Ⅰ)~(Ⅵ)で構成されることをお話しました。
ステップ(Ⅰ)問題提起
ステップ(Ⅱ)・(Ⅲ)趣旨・例外
ステップ(Ⅳ)モノサシ
ステップ(Ⅴ)当てはめ
ステップ(Ⅵ)結論
そして、法解釈は、抽象的な条文の文言が、検討対象である事実にそのまま当てはめられないため、当該条文の文言を検討対象である事実に当てはめられるようなモノサシを示すことが根幹です。
すなわち、まずは適切なモノサシを提示することが重要となります。
しかし、ここでいう適切なモノサシとは何でしょうか?
実務であれば、訴訟であれば、原告と被告が、それぞれ自分に都合の良いモノサシを提示して、裁判所が最終的に決めることになるでしょう(裁判所は当事者が提示したモノサシを用いても、勝手に作っても良いです。)。つまり、そこには絶対的な正解などなく、裁判所の価値判断があるだけです。
したがって、「適切なモノサシ」とは、どれだけ裁判所に説得的な理由と共にモノサシを提示できるかという点にいきつくものです。
これは弁理士試験であっても同じであり、どれだけ採点者に説得的な理由と共にモノサシを提示できるかという点が重要です。
すなわち、これでもうお分かりのとおり、ステップ(Ⅱ)・(Ⅲ)とステップ(Ⅳ)のつながりが重要となります。
この点、一般的な受験指導において、このnoteシリーズのようにステップ(Ⅱ)・(Ⅲ)を2つのステップに分けずに、単に「趣旨を書け」とするものを多く目にします。しかし、これでは説得的なモノサシを提示できないのです。
なぜでしょう?
法律の抽象的なルールは既に一定の完成度があります。
各事象について、どのような要件がそろえば、どのような結果を生ずるか、理想的な事案については処理が考えられているのです。
しかし、その理想的な事案から一歩外れると、そうはいきません。
ある条文が想定する事案と、条文が想定しない事案がちょうど重なる部分は、条文が適用できるのかがグレーとなります。ここがまさに法解釈が必要な部分であり、試験の題材になり、紛争となって判例となります。
このような部分は、条文が想定する事態と、条文が想定しない事態という、二つの利益対立が必ずあります。(利益対立がなければ、解釈がそもそも不要な場所といことです。)
この利益対立の中での落としどころこそが、モノサシになるわけです。
したがって、法的三段論法では、この利益対立を示し、その中間にモノサシを提示すれば、説得的な論述になるというわけです。
このような理由から、このnoteシリーズではステップ(Ⅱ)・(Ⅲ)を分けています。#007の最後でも紹介しましたが、判例も必ず利益対立が意識され、その間にモノサシが示されています。
※なお、このnoteでは、条文上の文言とは別に、自分で立てた規範として「モノサシ」という言葉を使っています。条文上の文言とモノサシを併せて法規範です。
趣旨・例外の本質
法的三段論法テンプレートにおけるステップ(Ⅱ)・(Ⅲ)の本質は、利益対立を示す点にあるといえます。
さて、法的三段論法テンプレートでは、皆さんが簡単に法的三段論法を書けるようにするために、テンプレートという形で、ステップ(Ⅱ)・(Ⅲ)では趣旨と例外を書けとお伝えしました。
また、趣旨と例外で書きにくい場合は、必要性と許容性を書けともお伝えしました。
ステップ(Ⅰ)問題提起
ステップ(Ⅱ)・(Ⅲ)必要性・許容性
ステップ(Ⅳ)モノサシ
ステップ(Ⅴ)当てはめ
ステップ(Ⅵ)結論
この点は、少し分かりにくかったかもしれませんが、本質は、対立する利益を書くことにあり、そこに大きな違いはありません。みなさんの答案が書きやすくなるよう、あえて、趣旨・例外パターンと必要性・許容性パターンと名付けているだけにすぎません。
趣旨・例外パターンであれば、当該条項の趣旨を書きつつ、例外としてそれを貫徹してはいけない場面を指摘すれば、その貫徹してはいけない場面がモノサシになります。
必要性・許容性パターンであれば、当該条項をこのように解さなければいけない必要性があると指摘しつつ、そのように解釈しても弊害がない(少ない)から許容できるという許容性を指摘すれば、その解釈そのものがモノサシになります(必要性と許容性を指摘することで、必然的に、対立する利益を比較することになります。)。
「何の」必要性・許容性?
必要性・許容性の主語は、今まで意図的に省略していました。仮に書くとしたら、「『モノサシ』のように解すべき必要性・許容性」や、「ある価値観(モノサシの根本的価値基準)があると解すべき必要性・許容性」になるでしょう。
ステップ(Ⅰ)問題提起
ステップ(Ⅱ)・(Ⅲ)モノサシのように解する必要性・許容性
ステップ(Ⅳ)モノサシ
ステップ(Ⅴ)当てはめ
ステップ(Ⅵ)結論
僕が主語を今まで省略した理由は、本来の論理の流れは「必要性・許容性⇒モノサシ」となるべきところ、あたかも「モノサシ⇒必要性・許容性」という流れになるのではないかと混乱が生ずることを懸念したからです。
本来の論理の流れは形式的には、「必要性・許容性⇒モノサシ」になることは疑いの余地はありません。しかし、#007でも説明しましたが、論述を構築する際は、結論ありきで、「モノサシ⇒必要性・許容性」と考えることが有用かつ必須です(実際、このように逆算する視点がないと、論理的なつながりの緻密さが作れません。)。
したがって、必要性・許容性パターンでは、露骨に、本来あるべき論理の流れが逆転していることに、違和感を覚える方もいるのかもしれません。
強いてイメージをお伝えすると以下の感じです。

趣旨・例外パターンでは、趣旨でカバーされる部分に入るべきではない領域を例外で指摘し、その境目をモノサシに落とし込みます。
必要性・許容性パターンでは、対立する2つの利益の境目にモノサシを先に作り、そのモノサシが適切かを必要性と許容性から確認する論述になります。
どっちのパターンを使うべき?
それはまさに書きやすさの問題です。
判例では、繰り返し述べているように、あらゆる事案に合致するモノサシではなく、その事案限りにモノサシが示されるものです。したがって、結論ありきで、「本件では少なくとも~は~を意味する。」とモノサシが価値判断として先にあり、その理由付けとして、「なぜなら、このように解する必要があり、このように解しても問題はない。」という思考があるためか、必要性・許容性パターンで書かれていることが多いと感じます。
#007で紹介したドワンゴ知財高裁判決は、必要性・許容性パターンで書かれていると理解しています。
モノサシとして、「『生産」に該当するか否かは、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるかで判断する。」という結論があり、そのモノサシの価値観(根本的価値基準)である「属地主義を厳格に解してはいけないこと」につき、必要性と許容性が述べられています。
※上記で、必要性・許容性の主語は、「モノサシの根本的価値基準」の場合もあるかのような言及をしました。これは、モノサシそのものの必要性・許容性を論じてしまうと、結論ありきであることが露骨になってしまうため、「とある価値観」について必要性・許容性を述べ、その上で、「とある価値観」を別の言葉で表現しなおしモノサシとする例が多いです。例えば、後述するドワンゴ判決はまさにそうであり、モノサシ「当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるか」について必要性・許容性を述べているのではなく、そのモノサシの根本的価値観である「属地主義を厳格に解してはいけないこと」について必要性・許容性を述べています。
そのような視点で、もう1度読んでみてください。
特許権についての属地主義の原則とは、各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味するものであるところ、我が国の特許法においても、上記原則が妥当するものと解される。 前記(イ)aのとおり、本件生産1の1は、被控訴人FC2のウェブサーバが、所望の動画を表示させるための被告サービス1のウェブページのHTMLファイル及びSWFファイルを国内のユーザ端末に送信し、ユーザ端末がこれらを受信し、また、被控訴人FC2の動画配信用サーバが動画ファイルを、被控訴人FC2のコメント配信用サーバがコメントファイルを、それぞれユーザ端末に送信し、ユーザ端末がこれらを受信することによって行われているところ、上記ウェブサーバ、動画配信用サーバ及びコメント配信用サーバは、いずれも米国に存在するものであり、他方、ユーザ端末は日本国内に存在する。
ステップ(Ⅰ)
すなわち、本件生産1の1において、上記各ファイルが米国に存在するサーバから国内のユーザ端末へ送信され、ユーザ端末がこれらを受信することは、米国と我が国にまたがって行われるものであり、また、新たに作り出される被告システム1は、米国と我が国にわたって存在するものである。そこで、属地主義の原則から、本件生産1の1が、 我が国の特許法2条3項1号の「生産」に該当するか否かが問題となる。
ステップ(Ⅱ)
ネットワーク型システムにおいて、サーバが日本国外(以下、単に「国外」という。)に設置されることは、現在、一般的に行われており、また、サーバがどの国に存在するかは、ネットワーク型システムの利用に当たって障害とならないことからすれば、被疑侵害物件であるネットワーク型システムを構成するサーバが国外に存在していたとしても、当該システムを構成する端末が日本国内(以下「国内」という。)に存在すれば、これを用いて当該システムを国内で利用することは可能であり、その利用は、特許権者が当該発明を国内で実施して得ることができる経済的利益に影響を及ぼし得るものである。 そうすると、ネットワーク型システムの発明について、属地主義の原則を厳格に解釈し、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在することを理由に、一律に我が国の特許法2条3項の「実施」に該当しないと解することは、サーバを国外に設置さえすれば特許を容易に回避し得ることとなり、当該システムの発明に係る特許権について十分な保護を図ることができないこととなって、妥当ではない。
ステップ(Ⅲ)
他方で、当該システムを構成する要素の一部である端末が国内に存在することを理由に、一律に特許法2条3項の「実施」に該当すると解することは、当該特許権の過剰な保護となり、経済活動に支障を生じる事態となり得るものであって、これも妥当ではない。
ステップ(Ⅳ)
これらを踏まえると、ネットワーク型システムの発明に係る特許権を適切に保護する観点から、ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、特許法2条3項1号の「生産」に該当するか否かについては、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、①当該行為の具体的態様、②当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、③その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法2条3項1号の「生産」に該当すると解するのが相当である。
ステップ(Ⅴ)
これを本件生産1の1についてみると、①本件生産1の1の具体的態様は、米国に存在するサーバから国内のユーザ端末に各ファイルが送信され、国内のユーザ端末がこれらを受信することによって行われるものであって、当該送信及び受信(送受信)は一体として行われ、国内のユーザ端末が各ファイルを受信することによって被告システム1が完成することからすれば、上記送受信は国内で行われたものと観念することができる。 ②次に、被告システム1は、米国に存在する被控訴人FC2のサーバと国内に存在するユーザ端末とから構成されるものであるところ、国内に存在する上記ユーザ端末は、本件発明1の主要な機能である動画上に表示されるコメント同士が重ならない位置に表示されるようにするために必要とされる構成要件1Fの判定部の機能と構成要件1Gの表示位置制御部の機能を果たしている。 ③さらに、被告システム1は、上記ユーザ端末を介して国内から利用することができるものであって、コメントを利用したコミュニケーションにおける娯楽性の向上という本件発明1の効果は国内で発現しており、また、その国内における利用は、控訴人が本件発明1に係るシステムを国内で利用して得る経済的利益に影響を及ぼし得るものである。
ステップ(Ⅵ)
以上の事情を総合考慮すると、本件生産1の1は、我が国の領域内で行われたものとみることができるから、本件発明1との関係で、特許法2条3項1号の「生産」に該当するものと認められる。
このように、判例は、必要性・許容性パターンが用いられていることが多いように感じます。
他方、弁理士試験では、趣旨が直接試験でも聞かれる程に趣旨単体でも重要なため、趣旨を披露するという観点から、このnoteでは趣旨・例外パターンをテンプレートとして推しています。
※書きやすさの点については、個人的に、例えば、特許法29条の2については、「そもそも、先願の特許請求の範囲が確定するまで後願を処理できないと解すると迅速な権利化の観点では弊害があることから、先願の当初明細書の範囲に先願の地位を与えて後願を排除する必要がある。もっとも、このように解しても、当初明細書の内容は出願公開されることから、当初明細書に記載された発明に係る後願は何ら新しい発明を公開するものではなく保護価値が低いといえるため、弊害は少ない。」と、必要性・許容性パターンが書きやすいです。他方、特許法29条の2につき「発明者同一の場合は適用されないこと」については、反対に、「そもそも、29条の2の趣旨は、先願の当初明細書に記載された発明に係る後願は、何ら新しい発明を公開するものではなく保護価値が低いことから、登録を認めないという点にある。もっとも、関連する2つの発明をした出願人が、先願に係る発明つき明細書で別発明を用いて詳細に説明したがゆえに、後日当該別発明を出願できないとすれば、特許発明の詳細に公開した者に不利益が生じかねず不当な結果となりかねない。」と趣旨・例外パターンが書きやすいように感じます。このようにどちらが書きやすいかは一概にはいえないと考えています。
なので、本当にどちらで書いても問題はありません。
趣旨・例外パターンは、「そこで、①~と、②~を備える場合には、●に該当する。」と、要件を含んだモノサシ(条件付きモノサシとでもいいましょうか。)で書きやすいです。
他方、必要性・許容性パターンは、「そこで、●は、●と解する。」と、要件を含まないモノサシ(確定的モノサシとでもいいましょうか。)で書きやすいように思きょよい
もっとも、条件付きモノサシパターンであっても、「そもそも、①~と、②~を備える場合には、保護する必要がある。もっとも、①~と、②~を備える場合には、XXは問題とならない。」という流れで必要性・許容性パターンでも書けますし、確定的モノサシであっても、「そもそも、本条は●●を趣旨としている。もっとも、XXとして本条を適用することは前述の趣旨にはそぐわない。そこで、●は、XXの場合は適用せず●と解する。」と書けるでしょう。
しつこいですが、こればかりは書きやすさの問題です。問題ごとに、その都度、頭の中で両パターンを考えてみて、書きやすそうな方を都度選んでみてください。重要なことは対立利益を示し、その間のモノサシを示すことです。
※なお、強いていえば、上述のとおり、弁理士試験では、趣旨・例外パターンで書けるのであれば、こちらを選び、趣旨を理解していることをストレートにアピールするのがよいかなと思います。
必要性・許容性パターンの具体例
#007の例題4を必要性・許容性で書いてみましょう。
まず、この事案は判例があることから、モノサシは以下に決まっています。
この点は、#007で説明していますので、確認してみてください。
「そこで、『発明の実施である事業の準備』とは、①即時実施の意図を有しており、かつ、②その意図が客観的な事実から認識できる程度に表れていた場合に、認められると解する。」
なので、ステップ(Ⅱ・Ⅲ)は、「モノサシのように解する必要性・許容性」を指摘することになります。つまり、このように解すべき必要性と、このように解しても問題ないこ(許容性)を利益対立を意識して書くだけです。
※上述のとおり、必要性・許容性パターンは、露骨に順番が逆転します。
冒頭でも述べましたが、モノサシを提示する基準は裁判所の価値判断であり、多くの場合は結論ありきなのです。
必要性について、「特許法79条は特許権者と先使用権者の公平を図る点にあるところ、特許出願の際に現に実施していないものであっても、即時実施の意図を有してる者であれば、同じく保護する必要がある。」とできるでしょう。そして、必要性が認められる条件こそが、モノサシの要素になります。
また、許容性については、①問題点を指摘しつつ、②どの問題点をどう回避する条件、を記載するとおさまりがいいように思います。そして、当該条件こそが、モノサシの要素になります。
「実施していない者にも先使用権を認めた場合は先使用権の発生する範囲が不明確に広がる可能性があるという問題があるものの、即時実施の意図が客観的な事実から認識できる程度に表れていた者に対してのみ認めるとすれば、かかる問題は限定的である。」
このように、モノサシの条件を、必要性と許容性に振り分けて記載するときれいな論述になります。
これは、偶然ではなく必然であり、ほぼすべての法律の要件や、判例のモノサシの要件は、この必要性・許容性の観点から置かれているものです。
みなさんも、短答の勉強の際には、条文の各要件が、必要性の要件が、許容性の要件かを考えながら読むことで、一層条文への理解が深まることでしょう。
※なお、必要性の要件と許容性の要件は、明確に正解があるというわけではありません。「その意図が客観的な事実から認識できる程度に表れている」という要件は、内心に留まる意図は保護に値しないがそれが客観的に表れていた場合には保護に値するという説明で、必要性の要件と捉えることも可能です。これは、みなさんがどう理解し、どう表現するかの問題であり、自分の中で一貫した理解ができていればよいという話です。この点、少し難しい話をしているので、あまり気にする必要はありません。
さて、これで論述を組み立てると、以下になります。
ステップ(Ⅰ)
いわゆる先使用権は、①特許発明に係る発明を自らその発明し、②特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業の準備をしている者に認められる(特許法79条)。乙は、特許発明イと同一の構成である器具Xに係る発明を自ら開発してることから、要件①を満たす。他方、特許発明イに係る特許権Pの出願(平成29年3月1日)の際、乙は、日本国内において装置Xの製造装置を設置していたことから、「発明の実施である事業の準備」をしていたと認められるか、「発明の実施である事業の準備」の意義が問題となる。
ステップ(Ⅱ)
そもそも、特許法79条の趣旨は特許権者と先使用権者の公平を図る点にあるところ、特許出願の際に現に実施していないものであっても、即時実施の意図を有してる者であれば、同じく保護する必要がある。
ステップ(Ⅲ)
もっとも、実施していない者にも先使用権を認めた場合は先使用権の発生する範囲が不明確に広がる可能性があるという問題があるものの、即時実施の意図が客観的な事実から認識できる程度に表れていた者に対してのみ認めるとすれば、かかる問題は限定的である。
ステップ(Ⅳ)
そこで、「発明の実施である事業の準備」とは、①即時実施の意図を有しており、かつ、②その意図が客観的な事実から認識できる程度に表れていた場合に、認められると解する。
以下略
できあがった解答案をみてもらうとわかると思いますが、大して違いはありません。以下が前回検討した趣旨・例外パターンです。
ステップ(Ⅰ)
いわゆる先使用権は、①特許発明に係る発明を自らその発明し、②特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業の準備をしている者に認められる(特許法79条)。乙は、特許発明イと同一の構成である器具Xに係る発明を自ら開発してることから、要件①を満たす。他方、特許発明イに係る特許権Pの出願(平成29年3月1日)の際、乙は、日本国内において装置Xの製造装置を設置していたことから、「発明の実施である事業の準備」をしていたと認められるか、「発明の実施である事業の準備」の意義が問題となる。
ステップ(Ⅱ)
そもそも、特許法79条の趣旨は、先願主義を貫徹すると先に発明した者であったとしても既存の事業設備を無用に廃絶しなければならないという弊害があることから、特許権者と先使用権者の公平を図る点にあるところ、先使用権者が実際に特許発明の実施をしておらず、その準備を進めている段階であっても、かかる公平を図る必要があることに変わりはなく、保護を与えるべきであるといえる。
ステップ(Ⅲ)
もっとも、先使用権者が、特許発明に係る発明の実施を直ちに行わないのであれば、引き続き、先使用権者の利益を保護する実益がないことから、先使用権者における即時に実施する意図が客観的に認められる場合に限り、保護を与えれば足りるといえる。
ステップ(Ⅳ)
そこで、「発明の実施である事業の準備」とは、①即時実施の意図を有しており、かつ、②その意図が客観的な事実から認識できる程度に表れていた場合に、認められると解する。
以下略
どちらがよいでしょうか?
まず書きやすさの点について、僕は、本問は、必要性・許容性パターンが書きにくかったです。なぜなら、趣旨・例外パターンでは、「その意図が客観的な事実から認識できる程度に表れている」というモノサシの要件を導き出すことにつき、ステップ(Ⅲ)の「例外」において特に詳述しなくてもおさまりがよかったですが、必要性・許容性パターンでは、この点を真正面から記載しなければならなかったからです。必要性・許容性パターンでは、先使用権者の範囲が不足に広がらないため、という許容性を無理矢理ひねりだして記載しました。
さて、できあがって見比べてみると、モノサシの当該要件について、論理的な説明があるのは、やはり必要性・許容性パターンでしょうか。その点では、必要性・許容性パターンが優れていそうです。他方、趣旨・例外パターンでは、79条の趣旨について、詳細に述べています(流れとして、必要性・許容性パターンではモノサシの必要性・許容性が重要であり、趣旨の重要性が落ちるからです。)。弁理士試験という性質を考えると、趣旨・例外パターンの方が読み味がよい気もします。
どちらが好みか皆さんも考えてみてください。
※少し脱線しますが、判例はその事案限りにモノサシを示すものであることから、その事案を離れても使えるようなモノサシを嫌う傾向にあります(汎用性のある具体的なモノサシを提示すれば、それはもはや立法になりかねないためです。)。したがって、判例では、抽象的なモノサシを提示しつつ、考慮要素として具体的な事項を挙げることが多いです。このようなモノサシにすれば将来の判例との矛盾も回避でき、裁判所にとっては非常に合理的な考え方です。上記のドワンゴ判決もモノサシは「『生産」に該当するか否かは、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるか」という非常に抽象的なものであり、あくまでも考慮要素として具体的な「①当該行為の具体的態様、②当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、③その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響」を挙げています。これは、答案でも使える手です。例えば、本問であれば、「発明の実施である事業の準備」を厳格に解してはならないという根本的価値について必要性・許容性を論じ、「直ちに発明の実施をするものと認められるか否か」をモノサシとすることも考えられます。この場合は、「そもそも、特許法79条の趣旨は特許権者と先使用権者の公平を図る点にあるところ、特許出願の際に現に実施していない場合には先使用権を認めないと厳格に解することは公平を害することになる。もっとも、単に実施する意図を有している場合であっても先使用権を認める場合は、いち早く出願した特許権者の利益を軽視するものであり妥当ではない。そこで、「発明の実施である事業の準備」とは、①即時実施の意図を有しており、かつ、②その意図が客観的な事実から認識できる程度に表れていた場合等、直ちに発明の実施をするものと認められる場合に認められると解する。」となるでしょう。このように論述は、最高裁判決とも整合しており、かつ、最高裁判決の価値観を理解しつつ再構築しているものであり、個人的には悪くないと思います。
最後に
本日は以上となります。
また質問や疑問をいただいたら、適宜補足記事を記載したいと思います。
法的三段論法については一旦ここで中断し、判例関係の記事を投稿した後に、法的三段論法を短くまとめる方法について投稿する予定です。
よろしくお願いします!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
