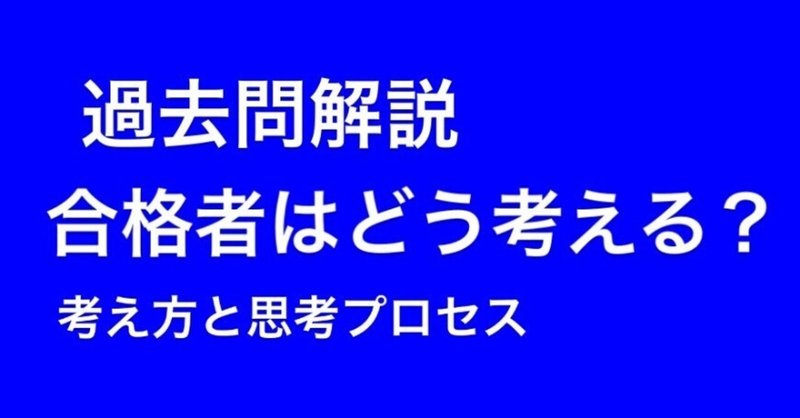
【弁理士試験】#005 合格者の思考過程
#004では、「法解釈」とは何かということを説明しつつ、そこで不可欠な条文の「趣旨」の理解についてお話しました。
またアウトプットの重要性もしつこく唱え続けてきました。
ここまでお付き合いしてくださった皆様なら、そろそろ答案を書きたくなっているのではないでしょうか?
今日は、答案を書いてみましょう。
解く問題は、ほんの一部ですので、気軽にご参加ください。
令和2年度弁理士試験論文式筆記試験問題
特許法 問題Ⅰ 設問1(1)
今日は、ひとまず書き方をつかんでいただくために、ちょっと古いですが、令和2年の特許法を例に(この問題を選んだ理由はパッと見て書きやすそうだったからです。)、答案を書いてみます。いずれは、各年の問題全部を通しで解説するnoteを投稿したいと思っていますので、よろしくお願いいたします!
なお、今回はあくまでも書き方や試験問題との向き合い方にフォーカスして解説するので、内容面についての学習は各自で必要となります。
また、なるべく合格者の思考回路を言語化するようにしています。
思考のトレースをして、何か感じるものがあれば、とても嬉しいです。
さあ、早速はじめましょう!
問題はココからご覧いただけます。
このnoteのつづきを読む前に、ぜひともご自分で書いてみてください。
時間は30分くらいが良いと思います。
【問題Ⅰ】
1 .甲は、新規な化合物α(以下「発明イ」という。)を発明した。
その後、甲は、化合物αが抗ウイルス作用を有することを見出し、化合物αを含有する抗ウイルス剤(以下「発明ロ」という。)の発明をした。
甲は、令和2年(2020 年)1月に、請求項1に発明イ、請求項2に発明ロを記載して、日本国に特許出願Xを行った。
一方、パリ条約の同盟国の国籍を有する在外者乙は、甲とは独立して発明イをし、発明イについての最初の出願として、平成 31 年(2019 年)3月に、請求項1に発明イを記載して、特許出願Y1をパリ条約の当該同盟国に行った。
その後、乙は甲とは独立して発明ロをし、令和2年(2020 年)2月に、請求項1に発明イ、請求項2に発明ロを記載して、出願Y1に基づくパリ条約による優先権を主張して日本国に特許出願Y2を行った。
ただし、発明ロは、いわゆる当業者が発明イに基づいて容易に発明をすることができたものではないものとする。
以上を前提に、以下の各設問に答えよ。ただし、各設問はそれぞれ独立しているものとし、各設問に示されていない事実をあえて仮定して論じる必要はない。
(1) 甲は、平成 31 年(2019 年)2月に発明イの内容を、日本国内において一般の研究者を対象にして、口頭で学会発表した(以下「発表a」という。)。この場合、出願Xの審査において、発表aが拒絶の理由の根拠となるか否か、各請求項について説明せよ。
ただし、甲は、出願Xの発明イについて、発表aに基づく発明の新規性の喪失の規定(特許法第 30 条第2項)の適用に関する手続を適法に行っていたものとする。
(2) 乙は、平成 31 年(2019 年)4月に発明イ及び発明ロの内容を、研究論文にまとめ、インターネット上で一般に対して公開した(以下「論文b」という。)。この場合、出願Xの審査において、論文bが拒絶の理由の根拠となるか否か、特許法第 30 条の適用の有無について言及しつつ、各請求項について説明せよ。
(3) 出願Y2にパリ条約第4条の優先権が適用されることにより、出願Xは甲に特許権を生じさせるものではなく、甲は出願Xの発明イについて特許権を得られないことについて、パリ条約の規定に基づき説明せよ。ただし、出願Xの請求項2について論じる必要はない。
解答すべき点を網羅するコツは問題を読み終える前に論点をリストアップすること
同一発明について2以上の出願が競合する事案の論点は、アレしかない!
さて、まずは問題文を読んでいきます。
甲については、新規な化合物α(発明イ)を発明し、さらに、化合物αを含有する抗ウイルス剤(発明ロ)の発明をしたこと、そして、2020 年1月に、請求項1に発明イ、請求項2に発明ロを記載して、日本国に特許出願Xを行ったことが記載されています。
他方、在外者乙が登場します。
乙は、甲とは独立して、発明イをし、発明イについての最初の出願として、2019 年3月に、請求項1に発明イを記載して、特許出願Y1をパリ条約の当該同盟国に行い、その後、乙は甲とは独立して発明ロをし、2020 年2月に、請求項1に発明イ、請求項2に発明ロを記載して、出願Y1に基づくパリ条約による優先権を主張して日本国に特許出願Y2を行ったことが記載されています。
※これは日本法の試験ですので、外国の出願Y1の取扱いが直接問われることはありません。あくまでも、直接問題となり得るのは、日本の出願Y2のみであり、優先権や、外国での公報発行が29条との関係で検討が必要となってくるにすぎません。したがって、出願Y1は一旦は忘れます。
つまり、日本において、①特許出願X<2020 年1月>(請求項1:発明イ、請求項2:発明ロ)と、②特許出願Y2<2020 年2月>(請求項1:発明イ、請求項2:発明ロ)が競合していることになります。
僕は、ここで一旦、問題を読むのをやめます。
そして、まず、同一発明について2つの特許出願が競合する場合に問題となり得る条文(論点)をリストアップします。
・39条(先願主義)
・29条の2(拡大先願)
・29条1項3号/29条2項(公開公報に基づく新規性・進歩性違反)
⇒拒絶理由(49条)
※ここで29条を含めているのは、一方の出願の前に既に他方の出願公開がされている場合も理論上あり得るからです。また、これらが拒絶理由通知の対象となることもしっかり記載します。なお、試験では空白にこのリストを記載していました。
これができたら、問題文を読み進め、関係がないものを削除していきます。
このような方法をとることで、漏れなく、回答することができます。論点を落とさないコツです。問題文を読みきってから論点を考えると、問題文の事情にひっぱられてしまい、視野が狭くなることが起こりがちです(昔の僕はそうでした。)。
なので、問題を読み終える前のリストアップは、大変おすすめです!
小問⑴:原則と例外を意識
問いに正面から答える:この時点で文末は確定
さて、小問⑴です。甲は、2019 年2月に発明イの内容を、日本国内において一般の研究者を対象にして、口頭で学会発表した(発表a)とのことです。そして、問いは、「出願Xの審査において、発表aが拒絶の理由の根拠となるか否か、各請求項について説明せよ。」です。
まず口頭で「発表」と新規性喪失事由が登場したら、考える前に、先ほどと同様に問題となり得る論点をリストアップします。
・29条1項(新規性)
・29条2項(進歩性)
ここで、29条2項をリストアップすることを忘れないようにしましょう。
なぜなら、発表した発明を少し改良したものを出願する場合は多くあり、この場合は29条1項ではなく、29条2項が問題となるからです。
次に、これだけでは十分でありません。これを回避する例外的な制度があれば、同時にリストアップしましょう。
・29条1項(新規性)←30条(新規性喪失の例外)
・29条2項(進歩性)←30条(新規性喪失の例外)
これで準備は万端です。答案を作成していきましょう。
※冒頭でリストアップした2つの出願が競合する場合の論点は、本問では関係ないようです(きっと後で出てくるはず!)。
まず、回答に際して最も重要なことは、この問いに対して答えることです。つまり、答案の語尾は、「出願Xの審査において、発表aが拒絶の理由の根拠と[なる。/ならない。]」のどちらかで終わる必要があります。また、出願Xについて聞かれていいるので、出願Yには触れる必要がないし、むしろ触れてはいけません。また出願Xについては、請求項ごとに回答しなければいけません。
現時点で、答案はこんな感じになります。
※このように請求項1と2で、見出しを付けて分けると見やすいでしょう。
設問1
小問(1)
ア 請求項1について
・・・・・・
よって、審査において、発表aが拒絶の理由の根拠と[なる。/ならない。]
イ 請求項2について
・・・・・・
よって、審査において、発表aが拒絶の理由の根拠と[なる。/ならない。]
原則と例外を考えるための4つのステップ
さて問題文に戻ります。検討に必要な事実は以下です。
・特許出願X<2020 年1月>(請求項1:発明イ、請求項2:発明ロ)
・発表a<2019 年2月>(発明イを学会で口頭発表)
また、特許法の取扱いを聞かれる場合は、以下の思考回路が役に立ちます。
1.原則としてどのような取扱いになるか
2.原則の取扱いを変更する例外規定はあるか
3.例外規定を適用するための要件を充足するか
4.例外規定の効果は何か
それでは、順番に検討しましょう。
請求項1:発明イについて
発表aでは、発明イを発表しているので、新規性のみが問題になりそうです。この段階で、29条2項について、解答案から削除します。
・29条1項(新規性)←30条(新規性喪失の例外)
・29条2項(進歩性)←30条(新規性喪失の例外)
ステップ1:原則としてどのような取扱いになるか
発明イについては、出願日が2020 年1月であり、発表aが2019 年2月であることから、29条1項に該当し、新規性を喪失しているかが問題となります。
ここで、「甲は、特許出願Xの出願前に発明イを発表していることから、発明イは新規性(特許法29条1項1号)を有さない。」と書いてしまう人がいます。これは、非常に悪い例です。特許法上の取扱いは条文に記載されており、具体的にどの条文がどのように適用されるかを明確に記載する必要があります。「新規性」という言葉は、私たちは当たり前のように使いますが、条文には登場しません。
それでは、「甲は、特許出願Xの出願前に、発明イを発表していることから、発明イは特許出願前に日本国内において公然知られた発明に該当し、新規性(特許法29条1項1号)を有さない。」ではどうでしょうか。これでもまだ不十分です。なぜ「公然知られた」といえるのでしょうか?条文の文言は抽象的であり、具体的な事案にそのまま適用することはできません。つまり、条文をそのまま引用してもダメです。解釈が必要です。この点、ピンとこなければ、#004でまとめているのでご確認くだ塁尾。
すなわち、解釈を展開した、以下のような回答がベストです。
「特許出願前に公然知られた発明は、新規性を有さないとして拒絶理由を有することになる(特許法29条1項1号、49条)。ここでいう『公然知られた』とは、不特定又は多数の者に発明の内容を現実に知られることをいう。本件では、発明イは、2020 年1月に出願されている一方で、甲は、発明イを、2019 年2月に、不特定又は多数の者が出席する学会において、口頭で発表していることから、特許出願前において、出席者において発明イの内容が現実に知られていえ、『公然知られた』に該当する。したがって、発明イは、新規性を有さず、拒絶理由を有する。」
※「日本国内において」という条文の要件は、日本であっても外国であっても結局は地球上の発表であれば特許法29条1項1号に該当することになり、実質的に指摘する実益がないため、字数を減らすために触れていません。本来であれば触れる方が丁寧ですね。
※さらにいえば、「公然知られた」とは不特定又は多数の者に発明の内容を現実に知られることを意味すると解釈できる理由を、条文の「趣旨」から導きだせば完璧な回答になるでしょう。
しかし、実際の試験では、ここまで書いている時間はないので短くなることは仕方がないことです(上記の例でも趣旨を踏まえた解釈の展開は既に省略しております。)。ここに時間を使って時間切れになるのであれば、ここまで書くことはデメリットになります。
そこでこれを短くすると、「特許出願前に現実に知られた発明は、『公然知られた発明』に該当し、拒絶理由を有するところ(特許法29条1項1号、49条)、甲は発明イを、特許出願前である2019 年2月に、学会において口頭で発表していることから、発明イは、特許出願前に出席者において現実に知られており、拒絶理由を有するといえる。」
同じ簡素な回答でも、上述のように、書けない人と、書けるけど省略した人とでは、内容の奥深さに差が出ていることがお分かりになるかと思います。
現時点で答案はここまで書けます。
設問1
小問(1)
ア 請求項1について
請求項1に係る発明イについて、特許出願前に現実に知られた発明は、『公然知られた発明』に該当し、拒絶理由を有するところ(特許法29条1項1号、49条)、甲は発明イを、特許出願前である2019 年2月に、学会において口頭で発表していることから、発明イは、特許出願前に出席者において現実に知られており、拒絶理由を有することになる。
・・・・・
よって、審査において、発表aが拒絶の理由の根拠と[なる。/ならない。]
イ 請求項2について
・・・・・・
よって、審査において、発表aが拒絶の理由の根拠と[なる。/ならない。]
ステップ2:原則の取扱いを変更する例外規定はあるか
例外の取扱いは、先に作成したリストをみます。
例外は30条の1つだけです。
本問は、例外を思いつくのは簡単ですが、難しい問題ではこの段階で例外を考えていると、見落としてしまうものが出てくるかもしれません。
なので、最初に漏れなく網羅的にリストアップをし、問題文を読み終えたあとは、そのリストの中から選ぶだけでいいのです。
・29条1項(新規性)←30条(新規性喪失の例外)
・29条2項(進歩性)←30条(新規性喪失の例外)
30条について、本問では、甲が発表aを行っているので、2項「出願人の行為に起因する新規性喪失」が検討対象となります。
つまり、現時点で答案はここまで書けます。
設問1
小問(1)
ア 請求項1について
請求項1に係る発明イについて、特許出願前に現実に知られた発明は、『公然知られた発明』に該当し、拒絶理由を有するところ(特許法29条1項1号、49条)、甲は発明イを、特許出願前である2019 年2月に、学会において口頭で発表していることから、発明イは、特許出願前に出席者において現実に知られており、拒絶理由を有することになる。
他方、甲による上記発表について、特許法30条2項の新規性喪失の例外適用されるか検討する。
・・・
よって、審査において、発表aが拒絶の理由の根拠と[なる。/ならない。]
イ 請求項2について
・・・・・・
よって、審査において、発表aが拒絶の理由の根拠と[なる。/ならない。]
ステップ3:例外規定を適用するための要件を充足するか
要件は、条文に明確に載っています。
(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
要件には、(Ⅰ)実体的な要件、(Ⅱ)手続的な要件、の2種類があります。条文では、これらの要件は、項を分けて書かれていることが多いです。要件がこの2種類に分けられることを知っていれば、30条2項のみの実体的要件を指摘しつつ、別の項に書かれた30条3項の手続的要件を見落とすことがなくなるでしょう。そのような意味で、要件の分類は、指摘する要件に漏れがないかを確認する便利なツールとなります。
(Ⅰ)実体的な要件 ⇒制度の適用を受ける資格・適格に関する要件
(Ⅱ)手続的な要件 ⇒制度の資格があることを前提に求められる要件
※なお、これは、必ずこのように整理してとらえなければいけないというものではありません。どちらの要件も、条文の効果に等しく作用するものであり、あくまでも、要件を漏れなく把握する上で、参考となる分類にすぎません。(例えば、手続を行うことを、制度の適用を適格と捉えれば、(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらに該当するといえるか曖昧になります。)なので、どのように整理するかを悩む必要は全くありません。
さて、問題に戻ると、実体的要件は30条2項に、手続的な要件は30条3項に書かれています。
(Ⅰ)実体的な要件
①29条1項1号に該当するに至つた日から1年以内に出願すること
(Ⅱ)手続的な要件
②出願と同時に本制度の適用を受ける旨を記載した書面を提出すること
③出願から30日以内に所定の証明書を提出すること
要件①について、発表aは2019 年2月にされ、特許出願Xは2020 年1月にされていることから、1年以内の出願であり、充足しています。
要件②・③については、「甲は、出願Xの発明イについて、発表aに基づく発明の新規性の喪失の規定(特許法第 30 条第2項)の適用に関する手続を適法に行っていたものとする。」と問題文に記載されているので、充足しています。
※要件は①~③と3つに分けてリストアップしましたが、実際の答案では②と③をまとめています。分けて記載する趣旨は、あてはめが読み手にわかりやすいよう指摘することにあり、本問では、問題文に、要件②と③を満たすことが書いてあるため、あえて分けて記載しても分かりやすくならないためです。
つまり、現時点で答案はここまで書けます。
設問1
小問(1)
ア 請求項1について
請求項1に係る発明イについて、特許出願前に現実に知られた発明は、『公然知られた発明』に該当し、拒絶理由を有するところ(特許法29条1項1号、49条)、甲は発明イを、特許出願前である2019 年2月に、学会において口頭で発表していることから、発明イは、特許出願前に出席者において現実に知られており、拒絶理由を有することになる。
他方、甲による上記発表について、特許法30条2項の新規性喪失の例外適用されるか検討する。同項の適用を受けるためには、①出願に係る発明が29条1項1号に該当するに至つた日から1年以内にされ、かつ、②出願人において30 条2項の適用に関する手続(特許法第 30 条3項)がなされる必要がある。本件では、発明イは、前述のとおり、2019 年2月に特許法29条1項1号に該当するに至っているところ、その1年以内の2020年1月の特許出願Xにおいて特許出願がされており、また、出願人甲は、30 条2項の適用に関する手続を適法に行っていることから、当該新規性喪失の例外規定が適用される。
・・・
よって、審査において、発表aが拒絶の理由の根拠と[なる。/ならない。]
イ 請求項2について
・・・・・・
よって、審査において、発表aが拒絶の理由の根拠と[なる。/ならない。]
※本文中に、「①」、「②」といった記号を使うことに抵抗がある方もいるかもしれませんが、読み手に分かりやすく伝えることを考えれば、そのような配慮を躊躇する理由はありません。
ステップ4:例外規定の効果は何か
最後に効果を検討します。
「新規性喪失の例外規定の適用の効果は、新規性違反が解消すること!」
これは不正確です。というか、間違いです。
アウトプットをしていない人がやりがちなミスです。
(短答式試験でも、上記のような理解で、枝を間違う人がいます。枝の解説をみても、自分がなぜ間違ったか、根本的な原因まで見出すことは難しいしょう。それは、問題文の読み落としでもなければ、「新規性喪失の例外」という制度を理解しきれていなかった、という単純な問題ではありません。これは条文の「効果」についての条文に即した正確な理解をするクセがないことに起因するミスの可能性が高いです。この悪いクセがあることを認識し、このクセを治す意識・努力をしない場合は、新規性喪失の例外だけではなく、他のすべて制度についても、同じように間違う可能性があるという点で、非常に重要です。)
インプット覇者は要件の暗記は正確にしていることが多いものの、その効果については漠然と暗記している人が多いです。
これは、多分、制度の名称や、論点の名称が、条文の効果を匂わす表現がされているせいで、効果について条文に即して正確に理解せずとも、何となく漠然と捉えやすいということに起因するのではないでしょうか。
しかし、条文の効果を漠然と暗記しているだけでは、アウトプットでは通用しません。
30 条第2項の効果を条文に即して正確にみてみましょう。
(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
まず、30 条第2項の主語は、「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずじゃち、えするに至つた発明」であり、その述語は、「同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。」です。そして、述語を読み解くには、「前項」を読む必要があります。
30 条第1項の主語は「特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明」です。述語は、「同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。」と定められています。
ここで、「同項及び同条第二項の規定の適用」(29条1項・2項)をみてみましょう。
(特許の要件)
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
本問で問題となるのは、29条1項のみなので、この点にフォーカスします。
そもそも条文は、具体的な事実について、要件を満たせば(1段目)、効果が発生する(2段目)、という2段階処理が記載されています。
つまり29条1項の構造は、ある発明が、29条1項1号に該当した場合は(要件:1段目)、29条1項の本文が適用され、特許を受けることができないという効果が発生する(効果:2段目)という2段階がかかれています。
この構造を意識して30条1項に戻ります。
30条1項の「特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明」は、「同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。」という文言は、つまり、29条1項における2段階の処理について、「特許を受ける権利を有する者の意に反して第29条1項1号に該当した場合」は、本体であれば、要件(1段目)に該当したとして29条1項の適用(2段目)に自動的に進むべきところ、当該2段目には進みません。ということを規定していることになります。
つまり、特許を受ける権利を有する者の意に反して公然知られた発明になった場合は、かかる原因に限っては、新規性を喪失しないということが規定されているといえます。
言い換えれば、特許を受ける権利を有する者の意に反して公知となった発明であれば、何でもかんでも新規性が否定されるものではありません。この違いが伝わりますでしょうか…?
例えば、新規性喪失に該当するにいたった根拠が複数ある発明について、そのうち1つでも特許を受ける権利を有する者の意に反して公知となった根拠があれば、他の根拠も含めて、完全に新規性が否定されるものではということです。自己の意に反して公知となった発明について30条1項の適用を受けたとしても、重ねて自ら学会で口頭発表し別途29条1項1号に該当するに至った場合は、後者を理由に29条1項に基づき新規性を喪失してしまうのです。
(ステップ4の冒頭で、「新規性喪失の例外規定の適用の効果は、新規性違反が解消すること」は誤りと述べましたが、これはまさに、特許を受ける権利を有する者の意に反して公知となった発明であれば、何でもかんでも新規性が否定されると誤解を招く表現といえるからです。自己が発表した発明について新規性喪失の例外の適用を受けて出願をしたとしても、出願前に第三者が独自にした同一発明を論文で発表していれば、当該出願には新規性違反があるこになるわけで、効果を「新規性違反が解消すること」と捉えた場合は、新規性違反に該当するという結論になることを正確に説明できないことになります。)
以上から、新規性喪失の例外規定の適用の効果は、正確に答えるとすれば、「新規性喪失の例外規定の適用の効果は、1項又は2項が規定する事由に限り、新規性喪失の判断根拠にはならないこと。」になるしょうか。
(揚げ足のような細かい話と思うかもしれませんが、非常に大事なことです。このような解釈ができるからこそ、例えば、①自己の意に反して公知となった発明について、②重ねて自ら学会で口頭発表し、特許出願をする場合は、30条1項の適用があっても、加えて、別途30条2項に関する手続が必要という結論が出せます。この手続を忘れた場合は特許を取得できないという大問題が発生します。)
さて、答案に話を戻すと、30条2項の効果も、30条1項と同様であり、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して29条1項1号に該当するに至つた発明については、当該事由は、29条1項で新規性喪失を否定する根拠とはならないということになります。
つまり、本件では、発表aによって特許法29条1項1号に該当するに至ったことについては、29条1項において新規性違反の拒絶理由の根拠とはならないということです。
この時点で、文末の問いの答えは「審査において、発表aが拒絶の理由の根拠とならない。」と確定できます。
あとは、効果を書いたら、最後は、問いの答えの部分とつながるように、答案を書きます。
設問1
小問(1)
ア 請求項1について
請求項1に係る発明イについて、特許出願前に現実に知られた発明は、『公然知られた発明』に該当し、拒絶理由を有するところ(特許法29条1項1号、49条)、甲は発明イを、特許出願前である2019 年2月に、学会において口頭で発表していることから、発明イは、特許出願前に出席者において現実に知られており、拒絶理由を有することになる。
他方、甲による上記発表について、特許法30条2項の新規性喪失の例外適用されるか検討する。同項の適用を受けるためには、①出願に係る発明が29条1項1号に該当するに至つた日から1年以内にされ、かつ、②出願人において30 条2項の適用に関する手続(特許法第 30 条3項)がなされる必要がある。本件では、発明イは、前述のとおり、2019 年2月に特許法29条1項1号に該当するに至っているところ、その1年以内の2020年1月の特許出願Xにおいて特許出願がされており、また、出願人甲は、30 条2項の適用に関する手続を適法に行っていることから、当該新規性喪失の例外規定が適用される。特許法30条2項の適用されれば、自己の行為に起因して29条1項1号に該当するに至つたとしても、この点を根拠に29条1項により新規性違反と判断されないことから、本件では、甲による上記発表に基づき新規性違反と判断されることはない。
よって、審査において、発表aが拒絶の理由の根拠とならない。
イ 請求項2について
・・・・・・
よって、審査において、発表aが拒絶の理由の根拠と[なる。/ならない。]
いい感じに答案が形になりました。
しかし、実際の試験では、この小問(1)の半分でこの分量は現時的ではありません。練習ではこのくらい書けることが望ましいですが、以下のように短くまとめることになるでしょう。しかし、「法的三段論法」を習得できていない人であれば、今の時点で短く書くのは絶対にやめてください。お願いします。次回以降に説明します。
(短くまとめることはそれなりのテクニックが必要です。単に短くした場合は、重要な部分も消してしまうことになるでしょう。短くするコツは端的にいえば、重要な部分を残すことです。では何が重要な部分でしょうか?これは論理の流れを作る部分です。この論理の流れについては、まず、「法的三段論法」を理解する必要があります。これは次回以降、このnoteの最大の目玉として、しっかりと伝授します。その後、「法的三段論法」を踏まえて、どこが重要な部分であり、どこを消してもよいのかと、改めて短くするコツをお話します。今回は参考までに記載しています。)
設問1
小問(1)
ア 請求項1について
請求項1に係る発明イについて、甲は発明イを、特許出願前である2019 年2月に、学会において口頭で発表していることから、発明イは、特許出願前にその出席者において現実に知られているといえ、原則として、特許法29条1項1号に基づき拒絶理由を有する(特許法29条1項1号、49条)。
しかし、甲は、当該発表から1年以内の2020年1月に特許出願Xをし(30 条2項)、また、30 条2項の適用に関する手続を適法に行っていることから(30 条3項)、新規性喪失の例外規定が適用され、当該発表を根拠に29条1項が適用され新規性違反と判断されない(30 条2項)。
よって、審査において、発表aが拒絶の理由の根拠とならない。
イ 請求項2について
・・・・・・
よって、審査において、発表aが拒絶の理由の根拠と[なる。/ならない。]
つづけます。
請求項2の発明ロについて
上述のとおり、これが取扱いを考えるステップです。
1.原則としてどのような取扱いになるか
2.原則の取扱いを変更する例外規定はあるか
3.例外規定を適用するための要件を充足するか
4.例外規定の効果は何か
まずステップ1です。
発表aでは、発明イを発表しているので、発明は非同一であり、新規性は問題となりません。
・29条1項(新規性)←30条(新規性喪失の例外)
・29条2項(進歩性)←30条(新規性喪失の例外)
あとは、進歩性の問題があるか、検討します。
(特許の要件)
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
進歩性の要件は、正確には、①「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」において、②「前項各号に掲げる発明に基いて」、③「容易に発明をすることができた」です。
1つずつ確認すると、要件①につき、「化合物αを含有する抗ウイルス剤」の分野における通常の知識を有するってなんでしょうか。こんなのわかるわけがありません。
※つまり、弁理士試験はもちろん、具体的な実務でない限り、進歩性の要件充足性を論ずることはまず不可能でしょう。なので、問題文のどこかに、進歩性をどう判断すればよいか、書いてあるはずです。弁理士試験では、進歩性が問題になる際は、必ず問題文の隅々まで目を凝らして確認しましょう。
この点、問題文には、「ただし、発明ロは、いわゆる当業者が発明イに基づいて容易に発明をすることができたものではないものとする。」と記載があります。なので、要件①~③が総括的に否定されております。
※仮に検討するとしたら、①「化合物αを含有する抗ウイルス剤」の分野における通常の知識を有する者の目線で、②発明イに基づいて、③容易に想到できたか、を問題文の事実から検討していくことになるでしょう…
以上、ステップ1の時点で、問の答えである「審査において、発表aが拒絶の理由の根拠とならない。」と確定できてしまいます。
あとは答案を書きましょう。
「29条1項1号に該当する発明に基づいて、出願前に当業者が容易に発明をすることができたときは、進歩性が否定され、拒絶理由を有する(特許法29条2項)。本件では、請求項2に係る発明ロは、出願前において、当業者が発明イ(上述のとおり29条1項1号に該当する。)に基づいて容易に想到することができたものではないと明示されていることから、進歩性は否定されず、拒絶理由を有さないといえる。」となるでしょうか。
また、進歩性違反について「発明ロは容易に想到することができたものではなく進歩性はある」等と、何に基づいて容易に想到するか、明確に記載しない受験生がたまにいます。あくまでも、「29条1項各号に該当する発明に基づいて」容易に想到することができるかが問題となるので、この点は明記する必要があります。
さらに、「発明ロは、発明イに基づいて容易に想到することができたものではなく進歩性はある」とだけ記載する人は結構います。これは、不十分です。条文の文言は「29条1項各号に該当する発明に基づいて」ですので、発明イが、「29条1項各号に該当すること」を指摘することは必須です。これを落とすと、要件へのあてはめができていないことになります。要件へのあてはめは法律家であれば精査して当然なので、採点者がこのような答案を読んだ場合は「この受験生は単にあてはめを忘れたのではなく、法律というものを何も理解していないんだな」と思われてしまってもおかしくありません。非常に危険なミスです。
経験上、例えば先使用権の要件であれば、あてはめを落とす受験性は少ないと気がしますが、とりわけ、この29条2項については、この点を忘れる受験生が非常に多いです。(「容易に想到」というキーワードが強すぎるせいで、「29条1項各号に該当する」が霞んでしまうのでしょうかね?)今ここで心に刻みましょう。
僕は、文章でうまく納まりが悪い時は、「発明イ(上述のとおり29条1項1号に該当する。)」とカッコ書でねじこみますので、参考にしてみてください。
※ちなみに、発明イは、新規性喪失の例外の適用を受けているので、29条1項各号に該当した発明ではないと思った方はいますでしょうか。上で詳細に条文の構造を読み解きましたが、新規性喪失の例外の効果は、29条1項各号に該当したとしても、29条1項本文の適用をしないことなので、「29条1項各号に該当した」ということもまで消してくれるものではありません。もう1度読み直してみてください。
これで答案は以下のとおりになります。
設問1
小問(1)
ア 請求項1について
請求項1に係る発明イについて、特許出願前に現実に知られた発明は、『公然知られた発明』に該当し、拒絶理由を有するところ(特許法29条1項1号、49条)、甲は発明イを、特許出願前である2019 年2月に、学会において口頭で発表していることから、発明イは、特許出願前に出席者において現実に知られており、拒絶理由を有することになる。
他方、甲による上記発表について、特許法30条2項の新規性喪失の例外適用されるか検討する。同項の適用を受けるためには、①出願に係る発明が29条1項1号に該当するに至つた日から1年以内にされ、かつ、②出願人において30 条2項の適用に関する手続(特許法第 30 条3項)がなされる必要がある。本件では、発明イは、前述のとおり、2019 年2月に特許法29条1項1号に該当するに至っているところ、その1年以内の2020年1月の特許出願Xにおいて特許出願がされており、また、出願人甲は、30 条2項の適用に関する手続を適法に行っていることから、当該新規性喪失の例外規定が適用される。特許法30条2項の適用されれば、自己の行為に起因して29条1項1号に該当するに至つたとしても、この点を根拠に29条1項により新規性違反と判断されないことから、本件では、甲による上記発表に基づき新規性違反と判断されることはない。
よって、審査において、発表aが拒絶の理由の根拠とならない。
イ 請求項2について
29条1項1号に該当する発明に基づいて、出願前に当業者が容易に発明をすることができたときは、進歩性が否定され、拒絶理由を有する(特許法29条2項)。本件では、請求項2に係る発明ロは、出願前において、当業者が発明イ(上述のとおり29条1項1号に該当する。)に基づいて容易に想到することができたものではないと明示されていることから、進歩性は否定されず、拒絶理由を有さないといえる。
よって、審査において、発表aが拒絶の理由の根拠とならない。
これで、小問(1)は完了です。
めっちゃ長くなりました!
小問(2)は記事を分けます。しかし、その前に先に、「法的三段論法」のお話をしようと思います。これは受験生必読ですので、よろしくお願いします!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
