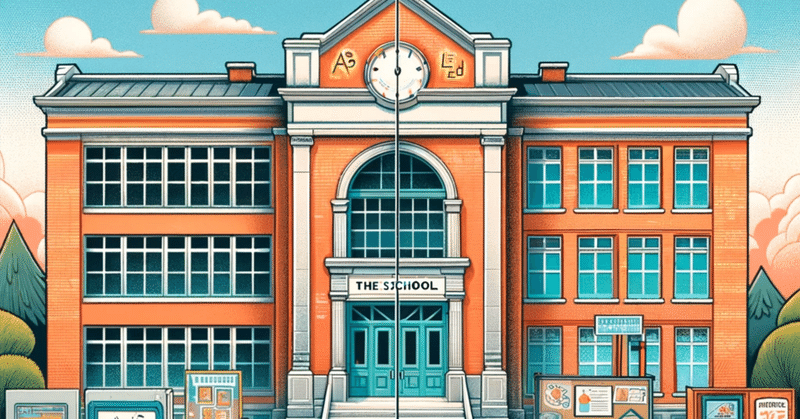
学校におけるAED普及の現状と課題
目次
学校におけるAEDの普及状況
AED設置の課題
学校におけるAED普及のための提案
1.学校におけるAEDの普及状況
日本国内の多くの学校ではAEDが設置されていますが、校舎内に複数台設置されており、誰もがその場所を知っていて、いつでもアクセスできる環境となっているケースは多くありません。
公益財団法人日本学校保健会 学校における心肺蘇生(AED)支援委員会が平成30年に実施した「学校における心肺蘇生と AEDに関する調査報告書」によると、AEDの設置状況についての回答では1台設置の学校が全体で77.1%と最も多く、2台設置の学校が18.4%と大きな差がありました。
また、同調査では2台以上の設置が必要と考えているとの回答が60%以上となっており、設置状況とのギャップが生じています。
2.AED設置の課題
AEDの設置を義務付ける全国的に統一された法令はまだ存在しません。
学校内に設置されているAEDの多くは、施設が施錠されてしまうと使用できなくなってしまうケースが多く、敷地内や近隣で発生した事案に対して必ず使用できる状況ではないことも課題となっています。
また、設置後の維持管理や定期的なトレーニングに関する体系的なサポートが不足しているのが現状です。
3.学校におけるAED普及のための提案
AEDの普及を促進するためには、トレーニングプログラムの提供、および定期的なメンテナンスの支援が必要です。また、AEDの重要性に関する意識啓発活動も重要な役割を果たします。
しかし、教職員全体への救命講習の実施が実現できていない現状と、多忙を極める労働環境を鑑みると教職員による生徒への普及啓蒙活動は困難を極めます。
消防職員による救命講習を実施している学校が多い一方、救急隊の出動件数も急増しているため、救命講習を開催できる民間団体との継続的な講習開催体制の構築が鍵となります。
政府や教育機関による資金援助を行いながら長期的に運用できる環境を整備することで、学校教育における救命講習の位置付けを改善し、地域コミュニティにおける自助、共助に寄与できる人材の創出が可能となるのではないでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
