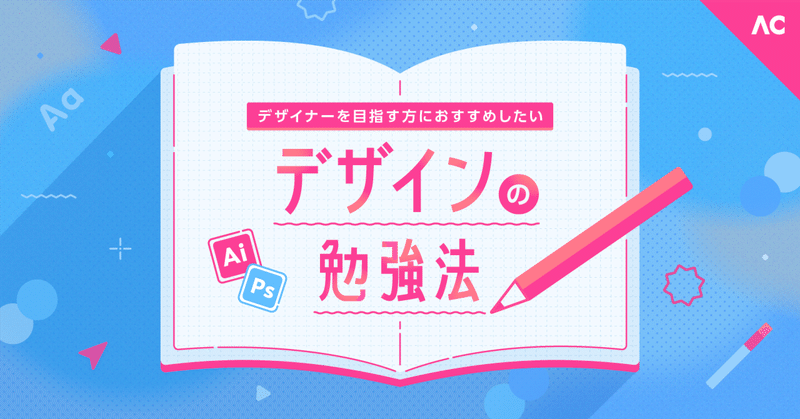
デザイナーを目指す方におすすめしたい、デザインの勉強法
こんにちは!ADWAYS(アドウェイズ)のデザイナーのヨッシーです。
「どうしたら、デザインが上手になれるのだろう?」
「そもそも、何から始めたら良いのだろう?」
こういったお悩みを持つ方は結構多いのではないでしょうか?
私自身もデザイナーを目指し始めたばかりの頃は、何をしたら良いのかが全く分からず不安でした。
デザイナーになるためには特定の試験に合格しなければならない!とか、
美大を必ず出なければならない!といった基準があるわけではないため、
必要なスキルが分かりづらいのだと思います。
そのため、今回の記事ではデザイナーになるために必要なスキルや、おすすめのデザイン勉強法をご紹介したいと思います。
これからデザインを学び始めたい方におすすめの内容となっておりますので、ぜひご一読ください!
1.デザイナーの種類を知る
デザイナーという括りの中には様々な種類があります。例えば、
・ポスターやチラシをデザインするグラフィックデザイナー
・WEBサイトをデザインするWEBデザイナー
・雑誌やカタログをデザインするエディトリアルデザイナー
などなど……お仕事の内容は多岐に渡ります。
そのため、デザイナーの種類を大まかに知っておくと、後々どんなデザイナーになりたいかを考える際の参考になると思います!
デザインを学び始めてすぐに「○○デザイナーになるぞ!」と決める必要はありませんが、目指す方向が決まると身につけるべきスキルも固まってきやすいので、少しずつ考えてみると良いかもしれません。
▼参考
ちなみにADWAYSの場合は、大きく分けて5種類のデザイナー職があります。(2023年7月現在)
・グラフィックデザイナー
・動画デザイナー
・WEBデザイナー
・UIUXデザイナー
・3Dデザイナー
※募集している職種は、タイミングによって異なります。
ADWAYSのデザイナー職にご興味のある方は、下記の採用情報をご覧になってみてください!
ADWAYS 2024年 新卒採用情報
ADWAYS 中途採用情報
2.デザイン制作ツールの使い方を学ぶ
デザイナーを目指すための第一歩として、デザイン制作ツールの扱い方を学ぶことがおすすめです!
上記で紹介した通りデザイナーには様々な種類がありますが、最も使用されることが多いツールは、Adobeが提供している「Illustrator」と「Photoshop」だと思います。
▼Photoshop / Illustratorの特徴に関しては、こちらの記事が分かりやすかったです。
なお、WEBデザインではFigmaやDreamweaver、雑誌のデザインではIndesignなど、Photoshop / Illustrator以外のツールを併用する場合も多いようです。
そのため、なりたいデザイナーの種類がハッキリと決まっている場合は、実際の現場で使われているツールの扱い方を学んでいくと良いと思います。
デザインの現場で使用するツールは企業により様々ですが、就職する前に上記2つのツールを使えるようになっておくと、ポスターやバナー広告、チラシなど基本的なものは一通り制作できるのではないでしょうか。
なお、上記ツールを初めて触る場合は分からないことが多いと思いますが、私は書籍やWEBサイトを参考にしながら操作してみることで、ほぼ独学で少しずつ使えるようになっていきました。
個人的なポイントとしては、実際に制作しながらツールを触ってみる→初心者向けの書籍やインターネットで分からないことを調べる→また制作してみる、と繰り返していくのがおすすめです。
▼ご参考までに、初心者向けのPhotoshop / Illustratorのおすすめ本をご紹介します!
3.様々な媒体でデザインノウハウを学ぶ
ツールの使い方だけでなく、レイアウトや色の決め方など、デザインの基本を学んでいくことも大切です!
このパートでは、私がデザインの勉強に使っている媒体と、その利用方法をいくつかご紹介したいと思います。
■書籍やWEBサイトを利用する
日々のインプットや細かな調べ物に最もよく利用するのは、書籍とWEBサイトです。
参考となる作品を集める、ツールの使い方を調べる、日々のトレンドを追う……などなど使い方は様々ですが、まずはデザイン関連で気になる本を数冊買ってみることから始めるのがおすすめです。
▼こちらの記事で、おすすめの本をご紹介しています!
またインプット方法として個人的に気に入っているのは、電子書籍ではなく紙の書籍でデザイン集や雑誌を購入することです。
たくさんのデザインを見ることは電子書籍やWEBサイトでも可能ですが、実際に本を手に持って様々なデザインを見ると、自分が好きだと思える作品に出会った時の感動や憧れの感情が大きくなるような気がします。
そしてその時の気持ちは、制作のモチベーションに繋がります。
本屋さんやインターネットで気になる本や雑誌に出会った時は、ぜひ手にとってみてください!
■セミナーを受講する
デザインのセミナーは数多くありますが、講師にデザイナーとしての実績や知識がある場合、受講する価値はとても高いと思います!
▼特に私はセミナーを受講するためにこちらのサイトをよく利用しています。(スマホ用のアプリもあります!)
こちらで公開されているセミナーは、リアルタイム生放送であれば無料で視聴できます。
デザインの基礎から応用まで幅広く学べるだけでなく、文章の書き方や思考法など、デザイン以外にも興味深い内容が盛りだくさんなので、気になった方はぜひインストールしてみてください!
私はこちらのセミナーを視聴することで、デザインの歴史やフォントの使い分け方、ブランドイメージに沿ったデザインの作り方などを学ぶことができました。
また、他の有料セミナーを受講してみるという手段もあります。
その場合、プロのデザイナーから技術や知識を学べる、自分の作品に対してフィードバックをもらえるなどのメリットもありますが、どんな人が講師をしているのか?受講料は自分に合っているか?といった点に注意し、運営元や評価についてしっかり下調べを行ってから受講することをおすすめします。
■YouTube動画を視聴する
YouTubeには、デザインに関する動画が数多くアップされています。
書籍やWEBサイトに比べると直感的に内容を理解しやすく、またセミナーよりも手軽ということで、よく利用しています。
個人的におすすめな利用方法としては、ご飯を作りながらor歯磨きをしながら動画を視聴することです笑
勉強目的で動画を視聴するのは、結構パワーが必要なので……勉強をするぞ!という気持ちで始めるよりも、何かをしながらゆるい気持ちで視聴する方が続けていける気がしています。
せっかくなので、私がよく視聴しているチャンネルをいくつかご紹介しようと思います!
気になるチャンネルがあれば、ぜひ覗いてみてください。
Youtubeでデザイン知識を発信しているチャンネルは多いので、色々と動画を見てみることをおすすめします!
■SNSで情報を収集する
SNSでデザイン系のアカウントをたくさんフォローしておくと、デザインのノウハウだけでなく企業やデザイナーが行うセミナーの情報などもキャッチすることができます。
例えばデザイナーやアートディレクター、Adobeやフォントメーカーなど、デザインに関連するアカウントを幅広くフォローしておくことがおすすめです!
SNSは日常的に覗くことが多いと思うので、無意識にデザインのインプットも増えていくような環境を作ることはスキルアップに有効だと思います。
▼デザイン初心者の方におすすめのYouTube・書籍・その他SNSなどを更にたくさん紹介している記事があるので、ご興味がある方は是非ご一読ください!
4.とにかく作品を作る
ここまではインプット中心のお話でしたが、アウトプットとして実際にデザインの制作を行うことも大切です!
私がこれまで実践してきた中で、効果があったと感じる制作のルーティーンをご紹介したいと思います。
■まずは作品を作ってみる
学校の課題や自主制作などを通して作品を作ることが、何より上達の近道だと感じます。
脳内では思いつかなかったアイデアが手を動かしていると自然と浮かんできたり、逆に脳内では素敵なデザインを思い描いていたのに、実際に制作してみると微妙だったり……手を動かしてみないと自分の実力は分からないなぁと常々感じます。
また、美大に通っていない、学校で課題が出ないという方には、以下のような自主制作をおすすめしたいです!
・お気に入りの映画やキャラクターなど、自分の好きなものを広報するポスターを作ってみる
・お出かけや旅行の記録を1枚の画像にまとめてみる
・好きな言葉をロゴ風にデザインしてみる
💡アイデアの参考を探すときは、Pinterestを使うのがおすすめですよ!
作品を制作すると、最初は特に思い通りに作れず悲しくなることも多いと思いますが、少しずつでも必ず上手になるぞ!と強い気持ちを持って制作を続けることが大切だと思います。
自分はデザインが下手だなぁと落ち込んだ時は、まだまだ成長の途中であることを意識すると少し気持ちが楽になるかもしれません。
■制作して終わりではなく、必ず振り返りを行う
学校の課題や自主制作などで作品を作った時は、振り返りを行うと良いと思います。
特におすすめなのは、制作の途中に気づいたことや悩んだことをメモしておき、作品が完成した後にまとめて振り返りを行うことです。
そうすることで、自分の苦手な部分や次に活かせるポイントなどを発見できます。
さらに、制作過程の作品を定期的に画像として書き出しておき、完成後に時系列で並べてみることもおすすめです。
自分がどのように作品をブラッシュアップしていったかという気づきを得ることができるので、次の制作で悩んだ時、前回を参考に作品のクオリティを上げることが可能になります。
■出来上がった作品を誰かに見てもらい、意見をもらう
できれば自分よりもデザインスキルが豊富な先生や先輩に作品を見てもらえると良いですが、そういった環境にない場合は、友人や家族など、身内の人に見てもらうのがおすすめです。
デザイナーではない人に見てもらう場合、専門的な意見をもらうことは難しいかもしれないですが、客観的な意見をもらうことができます。
デザイナーになった場合、完成品を見るのはデザイナーではない方々が大半のため、そういった方々の視点や意見を知ることはとても大事だと思います。
■デザインのアルバイトをする
ある程度ソフトの扱いに慣れ、作品が作れるようになってきた場合、デザイナーとしてアルバイトしてみるのもおすすめです。
他の一般的なアルバイトと比較するとあまり募集は多くないですが、インターネットで探してみると見つかるかもしれません。
デザインのアルバイトをすると、実務の中でスキルアップを目指せるだけでなく、デザインを通して問題解決を行うことや、コミュニケーション能力も鍛えることができると思います。
また、アルバイトを行うことが難しい場合は、友人・知人から依頼を受けてデザインを制作するのもおすすめです。
私の友人は学生時代に、自営業を営んでいる知り合いの方に頼んで依頼を受けたと言っていました。
店内に掲示するポスターを制作したそうです。
実際に依頼主がいる環境で制作を行うことは勇気がいると思いますし、初めてのことに挑戦すると上手くいかないこともたくさん出てくると思いますが、そういった経験はデザイナーとして大きな成長に繋がると思います。
5.デザインの模写練習を行う
上でご紹介した方法は自分で1から作品を制作する中でデザインを学ぶ方法でしたが、レイアウトや配色の感覚を掴むためには、素敵だと思える作品を真似してみるのも良いと思います。
デザイントレースや模写が有効ということはよく言われていますが、私はそれらを1つに合体した練習をよく行っていました。
以下に具体的な方法を記載します。
①お手本となる作品を1つ選ぶ
複雑な作品だと真似しづらいので、最初はできるだけシンプルな構成の作品を選ぶのがおすすめです。
▼今回は例として、ソフトクリームの画像を用意しました。
あくまで一例なので、自分が素敵だなと思う作品を1つ見つけてお手本にすると良いと思います!

②お手本と同じサイズのキャンバスをIllustratorもしくはPhotoshopで用意し、画像内の文言を全て書き写す
お手本内に自分で用意することができない写真やイラストがある場合は、その部分だけPhotoshopで切り抜いておくと便利です。(今回の場合はソフトクリームの写真)

③お手本を数分間じっくり観察する
レイアウトや文字のサイズ、配色などを覚えましょう。
④3分経ったらお手本を非表示にし、記憶だけを頼りに同じものを作ってみる
お手本と同じフォントがない場合、できるだけ似たものを選びましょう。

⑤納得がいくまで制作するか、これ以上は思い出せない!と思った時点でお手本を表示します。
⑥自分が制作したものとお手本を見比べ、違っている部分を書き出します。

⑦お手本を再度非表示にし、④以降を繰り返す
⑧最終的には、お手本を表示したまま細かい部分まで同じになるよう詰めていく
自分の制作物とお手本の違いは何だったか?など、気づいたことをメモし、次に活かしましょう。
この練習を行うと、色の選び方やフォントサイズの感覚を身につけることができ、同時に自分がデザインする際の癖なども知ることができるのでおすすめです!
番外編 ポートフォリオ作りを意識する
ここまではデザイナーになるためにおすすめしたい練習法などをご紹介してきましたが、番外編として普段からポートフォリオ用の素材集めを意識する重要性についてご紹介したいと思います。
就職活動を行う際は、自分がこれまでに制作してきた作品を1冊の本にまとめる必要があります。
その際、作品そのものだけでなく実際にその作品が使われている様子や、制作過程の様子、デザインに込めた意図などを掲載すると、説得力が増します。
そのために、普段からポートフォリオの存在を意識しながら制作を進めることが大切です。
例えばポスターであれば実際に掲示されている写真を撮影しておく、作品の依頼主がいる場合はその方の依頼内容をメモしておく、自主制作のラフやスケッチも捨てずにとっておく、などです。
実際にポートフォリオを作らなければならなくなった際、焦らないように準備を進めておくと良いのではないでしょうか。
同時に、なりたい職種に合わせた作品を作ってみることも有効です。
実際にお仕事として制作に関わることが難しくても、架空の広告・雑誌・WEBサイトなどを制作してみると、職種ならではの学びを得ることができるだけでなく、ポートフォリオに入れる作品にすることもできます。
就職活動では単純なデザイン力だけでなく、業界に対する理解が深かったり、ポートフォリオに載っている作品の方向性が合っていたりすると、熱意が伝わりプラスの評価に繋がるのではないでしょうか。
おわりに
今回の記事では、デザイナーになるためのおすすめ勉強方法をご紹介しました。もし気になる方法があれば、ぜひ試してみていただけると嬉しいです!
また、練習や勉強はデザイン上達のために必須ですが、疲れている時・やる気が出ない時はインプットに徹することもおすすめです。
例えばご飯を食べながらデザインにまつわる動画を視聴したり、休憩時間にのんびりデザイン集を眺めたり……心や体に負担がない方法でぼーっと見るだけでも良いと思います。
毎日続けると知らぬ間にデザインの引き出しが増え、いざ制作という時に新たな表現が身についていたり、ツールをスムーズに扱えたりします。
また美術館や展示会、街中の広告など、日常の中で素敵だと思えるものを探すこともおすすめです。「良いな」と思える作品に出会ったら、どうして良いと思ったのか、色やレイアウトを観察したり、制作意図などを考えてみるのも楽しいですよ〜!
楽しいデザインライフが送れるよう、応援しております!
・・・
『デザインの力で課題解決に取り組む』ADWAYSクリエイティブチームでは、同じ志を持つ仲間を探しています。
(その他に関するお問い合わせはこちらにお願いします )
今後も、noteやTwitterでメンバーや環境、取り組んでいることなどをお届けする予定です。ぜひチェックしてみてください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
