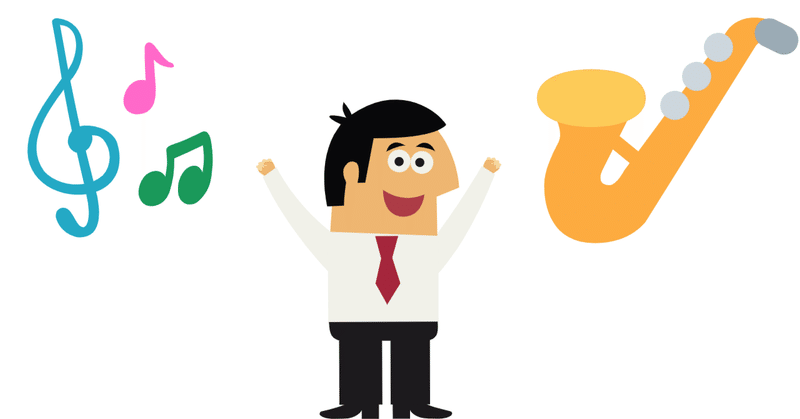
あなたの"それ"はマネジメントなの?
マネージャー、上司。そんな言葉を聞いてあなたはどんなことを思い描くでしょうか?
マネージャーの仕事ってなんなんだろうな、と私は常に考えています。なぜなら1番面白い仕事だからです。
マネジメントの本を読んだり、経営者のリーダーシップ論を聞いたりして今の私が思うことは、マネージャーの仕事は安心感をもたらすことだと定義するのが、1番しっくりきます。
その中でもドラッカーの論は、僕の中で拠り所にしている最も大きな物です。
ドラッカーの経営思想に影響を受けた経営者は数多くいますが、その中でも有名な経営者の発言を3個紹介します。
ドラッカーを敬愛する経営者
ユニクロの柳井正社長は、ドラッカーの言葉を信じて経営していると明言しています。彼は「私が尊敬してやまないピーター・ドラッカー。(中略)商売をするようになって、ドラッカーの言葉がいかに正しかったか。それを日々、実感している。」と語っています。
GEの元CEOであるジャック・ウェルチ氏は、CEO就任後すぐにドラッカーのもとに教えを請いに行きました。ドラッカーは彼に「世界で1位か2位になるつもりの事業だけ残して、あとはすべて捨てたらどうか」とアドバイスしました。
ウェルチ氏はそのアドバイス通りにGEを経営し、大成功を収めました。
日本マクドナルドホールディングスの原田泳幸社長は、ドラッカーの神髄を理解し、体現している経営者と言われています。彼は「企業の基本機能はマーケティングとイノベーションにある」というドラッカーの言葉を実践し、ブランドイメージの立て直しや新商品開発などで難局を乗り切りました。
ドラッカーが考えるマネージャーの仕事
このように多くの偉大な経営者に愛されてやまないドラッカーですが、ドラッカーはマネージャーの仕事を
①目標を設定する。
②組織する。
③動機づけとコミュニケーションを図る。
④評価測定する。
⑤人材を開発する。
と定義しています。これらは全て安心材料でもあります。
①目標を設定する。これは仕事においてマネージする必要がある人(部下など)に混乱を招かないためです。
目標がなければ何が達成(ゴール)なのか?なにがいけないこと(未達)なのか?それがはっきりしません。つまりなにを成果とするか?が明確でないと誰もなにをすれば良いのかわからないのです。それでは安心できません。
もちろん、それは測定可能(測ることができる)でないといけません。測れる物でなくては誰もわからないからです。
②組織する。ドラッカーはこんなことも語っています。「組織の目的は凡人をして非凡なことを行わせることにある。」
組織とは、他の人の強みで他の人の弱みを無意味にすることなのです。つまり補い合い他者同士で安心させることなのです。相互に安心させることなのです。
また、それ(組織する。)には必要な資源や人員やプロセスを配分することが必要です。組織は、柔軟で効率的で創造的な構造を持つべきだからです。
③動機づけとコミュニケーションを図る。組織のメンバーに対して、目標に対する意義や責任感や自信を与える。また、組織内外のステークホルダーとの間で、情報やフィードバックや意見を共有することです。
コミュニケーションは言わずもがな、メンバーがなにを考え、何に不安感を覚えているか?をわからなければ責任感も自信も生まれません。
情報の共有についてですが、責任というものは情報量の違いです。メンバーに情報を共有するということは、責任を共有するということです。「俺はこんなに頑張っているのに、なぜメンバーは誰もわからないんだ!」って人は情報を正しく共有できているか?を考えた方がいいです。
夫婦間で妻が負担を抱えがちなのは、夫と妻の情報量の違いから生まれます。「明日はご飯がいるからご飯炊いて、それから長袖と半袖も入れとかないと。コップもここに準備して、上の子は明日の宿題やったかな?」
その間夫はなにをするか?は、その情報を持っていないのでスマホを寝転がっていじり続けます。そして妻の逆鱗に触れるのです。
このように情報量の差は責任感の差に直結するのです。
④評価測定する。目標に対する組織のパフォーマンスや進捗状況を定期的に評価し、測定し、分析すること。評価測定は、客観的で公正で透明な方法で行われるべきである。とドラッカーは言います。
当然ですよね。評価と測定が無ければ成果、成長に対する次のアクションは場当たり的になります。
例えば、ダイエット。毎日体重を測り、鏡を見るからうまくいっているかどうかわかるのです。それが気分が乗った時だけ体重を測っていたらどうなるでしょう?当然のことながら、次に鏡を見た日には太った別人が立っていることでしょう。
⑤人材を開発する。組織のメンバーに対して、スキルや知識や能力を向上させるための教育やトレーニングやメンタリングを提供すること。また、組織のメンバーに対して、キャリアや成長や満足度を向上させるための機会や支援を提供すること。
メンタリングは数々の成功例があります。
例えば、
離職防止のためにメンター制度を導入したサービス業の事例を紹介します。この事例では、新卒社員に先輩社員がメンターとなり、仕事やキャリアに関する相談やアドバイスを行う制度を設けました。メンター制度の導入により、新卒社員の離職率は3年間で約10%から約3%に低下しました1。メンター制度の効果として、新卒社員は仕事に対する不安や悩みを解消できるだけでなく、自分の成長や目標に向かって努力できるようになりました1。また、先輩社員もメンターとして後輩の育成に責任を持ち、自身のスキルや経験を活かすことができました。
心理的安全性
これまでにドラッカーの言葉、
①目標を設定する。
②組織する。
③動機づけとコミュニケーションを図る。
④評価測定する。
⑤人材を開発する。
について説明して来ました。これらは一つ一つ見ていくと、当たり前に感じることかもしれません。しかし、その当たり前こそ難しく、またその当たり前を愚直に行えばメンバーの安心感はあがります。
なぜメンバーを安心させる必要があるのか?ですが、逆に言えばなぜ安心させない必要があるのでしょう?
経営において心理的安全性は、従業員の能力に大きな影響を及ぼします。心理的安全性が高いと、従業員は自分の考えや意見を自由に発言でき、チームのコミュニケーションやイノベーションが向上します。
逆に、心理的安全性が低いと、従業員は自分の発言が拒否されたり批判されたりすることを恐れて、発言を控えたりミスを隠したりするようになります。これは、チームの成果や生産性に悪影響を与える可能性が高いです。
少し事例を紹介したいと思います。
事例1:Google社は、成果の高いチームと低いチームの違いを調査した結果、心理的安全性が最も重要な要素であることを発見しました。心理的安全性が高いチームでは、メンバーがお互いに信頼し合い、失敗や問題を恐れずに共有し、多様なアイデアを尊重することができました。これにより、チームのパフォーマンスやイノベーションが向上しました。
事例2:リクルートグループでは、「フィードバックカルチャー」を推進しています。
フィードバックカルチャーとは、メンバー同士がお互いにフィードバック(意見や感想)を積極的に伝え合う文化のことです。リクルートグループでは、フィードバックカルチャーを育むために、「フィードバックシート」というツールを活用しています。
フィードバックシートとは、メンバーが自分の強みや改善点などを記入し、他のメンバーからフィードバックをもらうためのシートです。このシートを使って定期的にフィードバック会議を行うことで、メンバーは自分の成長や課題に気づきやすくなります。また、他のメンバーからフィードバックをもらうことで、信頼関係やコミュニケーションも深まります。
これらの事例から読み取れるのは、安心感というのは成果をもたらすということです。
マネジメントの目的は安心感
私が行うマネジメントもこれ(安心感)を重要視しています。
私の経験談からですが、職場で全員からできないヤツの烙印を押された部下がいました。しかし、どう見ても私から見ればコミュニケーションが弱みなだけであって、実務能力的には他の人と大差がないと思えました。
その時行ったマネジメントは、できる作業をやらせながらチャレンジさせる範囲を広げていくでした。これを続けることにより、自分の業務能力に安心を覚え《できない》という思い込みが外れていきました。
それにより、他の業務もできるようになり、そのことでコミュニケーションも徐々に、ですが取れるようになっていきました。
それは安心感を作り出す、というマネジメントの成果だったと確信しています。人間は誰しも《できない》という思い込みを勝手に作り上げます。そうやって業務範囲を勝手に狭め、できない人になっていくのです。
やらない=できないと同義です。やらなければ誰もできるかどうか判断できないからです。やってみてできなければ、また新たにできることを探せば良いだけです。
もう一度おさらいしましょう。
②組織する。ドラッカーはこんなことも語っています。「組織の目的は凡人をして非凡なことを行わせることにある。」
組織とは、他の人の強みで他の人の弱みを無意味にすることなのです。
安心感を作り出す。それがマネジメントです。私はそう定義します。このnoteもそうです。あなたの安心感を作り出すためにあるのです。
たぶん。
それでは、また、次回。
あどりでした。
《最後まで読んでいただき、ありがとうございました!もしあなたのハートが少しでも動いたならハートをタップしていただけると幸いです。もしくは右上の…をタップしてフォローしていただけると少しあなたの人生のお手伝いができると思います。Twitterなどで共有していただけると嬉しいです。今回もありがとうございました。》
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
