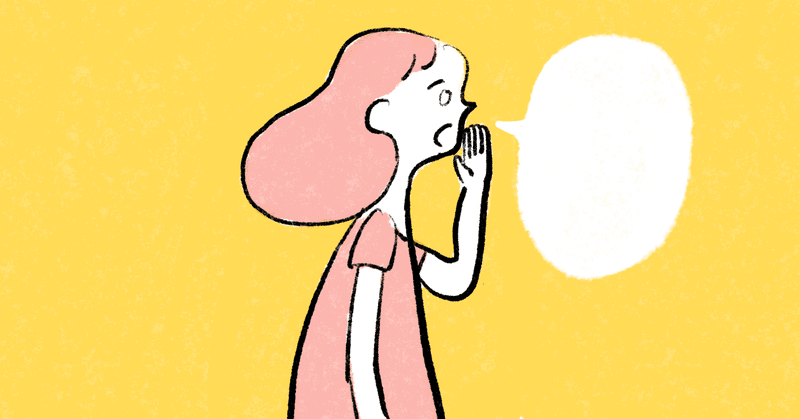
自分の声は好きですか?~日本人の約8割が自分の声が嫌いと答えるのはなぜか。
録音した自分の声を聞くと嫌悪感を表す人もすくなくない。声の研究者・山﨑広子さんが、なぜ自分の声が嫌いと答える日本人が多いのか。その社会的背景を考察します。エース2022年春号・特集「わたしの声って。」より
私が行った調査によると、約1万人(日本の男女10~70代)のうち84% が「自分の声が嫌い・どちらかというと嫌い」と答えました。その主な理由は、自分の声をちゃんと知らないということもありますが、もっと探っていくと、録音した自分の声が「作り声」に聞こえるからという方が多かったのです。例えば、自分の声だという感じがしない、気持ち悪い、という人がいます。それは、録音した声に慣れていないということだけでなく、作り声であることに脳が拒絶反応を示しているからでもあるんですね。
録音された自分の声を初めて聞いた人は、「わたしってこんな声だったの!?我慢できない!」などと言うことも多いです。普段、自分が話しながら聞いている声は、「骨導音」といって自分の中を通って聞こえている音と、「気導音」といって口から外に出た声が空気を伝わって耳から入ったものとの両方が合わさっています。骨伝導は低い周波を通すので、自分の声はもうちょっと低い声だと思っている人が多いんですが、録音して聞く声は、骨伝導の低い周波が入らない気導音だけです。だから、「こんな薄っぺらい浅い声だったの」と驚く人が多いのです。
日本女性の声は世界一高い
会社などで電話に出る女性の声は普段より随分高いですよね。これは、相手に対する配慮や、自分は強くないですよ、という無意識のアピールです。小さい個体、未成熟である子どもは人間でも動物でも声が高い。これは生物の共通認識なんです。そして日本人女性の声が世界一高いというのは海外でもよく知られています。大きな要因としては日本社会が求める女性像ということがあります。女性は男性よりも弱く小さく、かわいらしくあれといった価値観がいまだに根強いですよね。
ただ、アメリカの男性対象のアンケートでは「昔、母親が電話に出るときは1オクターブ高い声だった」という回答がありました。つまり日本と同じく、女性は高い声を出すという時代がアメリカにもあったわけです。でも、1960~70 年代に起きたウーマンリブをきっかけに、アメリカでの価値観は変わり、女性の声は大変低くなり、社会にもそれがしっかりと根付いているようです。
作り声の自覚がない人がほとんど
私のところには発声障害の方がよく相談にみえます。今多いのは痙攣性発声障害や舌ジストニアといった症例です。声帯や舌には異常がないのに、話すときだけ声がかすれたり震えたり、あるいは舌が前に出てきてしまう。それでうまく話せなくなって仕事や日常生活に支障が出てしまうのです。発声障害の方にほぼ共通するのは、「作り声」で話していることです。カウンセリングで何が一番難しいかというと、ものすごい作り声で話しているのに本人がそれに気付いていないこと。ある若い女性の例ですが、「彼氏が週末家に来て楽しかった」なんて言っても、症状はどうでしたかと聞くと、「楽しかったのに全然しゃべれなかった」と言うんです。
彼女は楽しいと言うけれど、家族や彼氏といても、恐ろしくなるほどの作り声で話していることに気が付いていない。その声はいつからですかと聞いたら、「ずっとこの声でこれが地声です」とキョトンとしている。そういった方に共通するのは、とても周りに気を使っていて、周りの人が求めるような行動をしなくてはいけない、と思い込んでいること。そうやって、人に求められる自分になりたい、求められる自分であろうと生きてきた方に症状が出るんですね。身体に合わない声を出しているので、苦しくないですかと聞いたら、「いつもしゃべるときは苦しいんだけど、何がいけないか分からなかった」と。おそらく、その苦しさからもう解放してほしいという脳の叫びが、発声障害となって現れているんです。そういう方にはまず自分の本当の声を見つけてもらうように指導しています。
教育によって声を抑圧されてきた
小学生の頃から国語の授業で音読がありますよね。自分の声もよく知らないまま、上手にコントロールもできなくて、ここでこういう感情を表すためには、こういうふうに声を出せばいいと考えることもなく、棒読みをしてしまうことがほとんどです。むしろ間違えずに読めればよしとされています。ちょっとでも感情を込めたりすると、みんなに笑われたり先生から普通に読んでと言われたりするわけです。欧米では、基礎として、どのように自分の思いを伝えるかをきちんと教えます。
それに比べ、日本の国語教育は、「伝える」教育をしていないのではないでしょうか。幼稚園や保育園で「大きな声で、みんな揃えて」から始まり、小学校に行けば「大きな声で、はっきりと」だけ。これでは自分がどんな声を出したいかを考えることもなく、周りと合わせるためだけに声を抑圧していってしまう。言葉の意味だけ伝わればいい、というような生気の通わない教育をしている感じがします。思いを伝える声を使えることは、自身にも、後に出ていく社会にとっても大事なので、個性豊かに声を育てる教育を期待します。
解説:
山﨑広子さん(やまざき・ひろこ)
一般社団法人「声・脳・教育研究所」代表。音が心身に与える影響を音響心理学、認知心理学をベースに研究。特に声と心身のフィードバックに着目、3万例以上を分析。著書に『8割の人は自分の声が嫌い』『声のサイエンス』『心を動かす「声」になる』ほか。
https://www.yamazakihiroko.com/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
