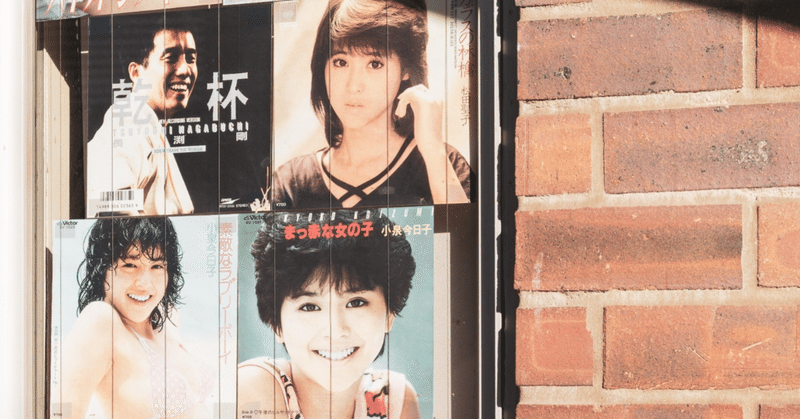
アーティストの歌声分析 ~歌声には話し声以上に多くの情報が埋もれているらしい。誰もが知るあの歌声を分析します!
「歌う」という大変な行為
必要な音程を得るために声帯の張力を変えること、呼気のエネルギーの使い方、声量の調整、共鳴のさせ方、発音と響きのバランス、音色など……。歌い手の脳は自分の声を聴覚フィードバックで微調整しながら声で音楽を作り上げています。歌を歌うという行為はとても大変なことで、身体と脳にかかる負荷の大きさは、話し声とは比較になりません。
それだけに、歌声にはその人に関するさまざまな情報が隠されており、歌声を分析することで、その時の心身の調子はもちろん、時にはこれまでの生き方までをもうかがい知ることができます。何人かの歌声を分析してみました。解説:山﨑広子さん(やまざき・ひろこ)一般社団法人「声・脳・教育研究所」代表。/エース2022年春号・特集「わたしの声って。」より
弱さと強さを併せ持つ
松任谷由実の歌声
曲を作り始めた頃の松任谷由実さんは、自らが歌うことを考えておらず、自分の声にコンプレックスを持っていたそうです。そのせいか、デビューまもなくの初期には少し声を作ろうとしているところが感じられましたが、最近の楽曲は地声が前面に出ています。おそらくどこかのタイミングで、あまり好きではなかった自分の声を受け入れた瞬間があったのでしょう。
ただ、松任谷さんは呼気が強く、音感もよいのですが、発声に関してはとても不器用です。聴覚から受け取った情報を神経に伝え、筋肉を動かす、その反射神経が少し遅いのかもしれません。うまく出せない音や響きの部分は短く切ったり、フェイドアウトさせてしまったりしている。そこに彼女の弱さが出ているように感じられます。しかし同時に、自分の声を受け入れているからこそ出せる、強く張った地声からは、彼女の芯の強さを感じます。弱さと強さの両方を持っているのが松任谷さんの声です。
だからこそ、松任谷さんの歌には親近感のようなものを覚えます。「これが私だから」という気取りのなさと、音楽的才能が合わさっていることが、長く支持され続けている理由かもしれません。
この声ありきで生まれたアイドル
松田聖子の歌声
若くしてデビューしたアイドルの中には、周囲が求めるままの歌声や歌い方に自分をピッタリはめ込んで、変わらずずっとそのまま、という方が少なくないような気がします。
松田聖子さんも18 歳でデビューしたアイドルですが、ただ彼女の場合は、元々かなりの歌唱力があることに加え、歌うことに対する強い意志を持っていたのだと思います。デビュー前の歌のレッスンで滑舌の悪さを指摘されたため、即座に舌小帯を切る手術を受けたという話を聞きました。舌小帯とは舌の裏側についているヒダで、これが短かったり長かったりすると、特にラ行の発音がきれいにできないのです。そういう逸話からも彼女のプロ意識の高さが感じられます。
当初は“アイドル・聖子ちゃん”のイメージを作り上げるため、周囲からの要求もいろいろと多かったことでしょう。しかしデビューしたての頃の歌声を聞いても、型にはめられた窮屈さは感じられず、比較的自由に歌っている様子。聖子さんの声は、伸びのあるいい声です。歌に関しては、周囲の方々もその声を尊重し、より活かせるような良い楽曲を彼女のために用意していったのだと思います。
どこを切ってもロックンロール
甲本ヒロトの歌声
甲本ヒロトさんの歌声は、THE BLUE HEARTSでデビューした時から現在のザ・クロマニヨンズまで、30 年以上たってもまったく変わらず劣化していません。むしろ味が加わりパワーアップしている感じすらします。通常、声は経年に伴って変わっていくものなのに。しかし、彼には何かを意図して鍛えたという気配がない。そして不思議なほど無理が感じられない歌声です。出している本人にとって最も気持ちよく、身体に無理な負荷をかけない声を、甲本さんは持っています。
甲本さんは「ロックンロールが僕の目的なんだ。ロックは手段じゃない」と言っているそうです。ロックが生きる目的であり、若くしてそれを見つけ、純粋に自分にとって気持ちがいいからずっと続けている。その声を無理やり何かに例えるなら「幹細胞」でしょうか。幹細胞とは器官を再生する細胞のこと。甲本さんの声には幹細胞が無数にあり、どこを切ってもロックとして再生するのです。
甲本さんの歌声は、私たちが社会生活を営んでいく上で避けられないしがらみから解かれて、一人の人として立った時にあるべき人間の姿を感じさせます。「世間も常識も関係ない。人にも社会にもおもねる必要などない。心臓が打ち続ける限り生きてやれ」という、単純にして至高の姿。だからこそ理屈ではなく、もはや一つの生体として、多くの人、とりわけ生きづらさを抱えやすい悩める若者たちの心をつかんできたのではないでしょうか。
全てを肯定して笑う
ルイ・アームストロングの歌声
ルイ・アームストロングの歌声はどの曲でも笑っているように聞こえます。彼の吹くトランペットも同様です。それがどこから来ているかというと、呼吸。呼吸は自律神経の働きであって、自分ではコントロールできないものですが、笑う時の呼吸が歌声にも表れているあたりに、彼の肯定感を感じます。生きていることに対しての強い肯定感です。
1901年アメリカに生まれて育った黒人の彼には、相当の苦労があったはずです。しかしそれを乗り越えての、あの笑顔と歌声。彼はレコーディングでも、すごく楽しいと、実際にニコニコしながら歌っていたのだと想像します。代表曲「この素晴らしき世界/What a Wonderful World」は、小さなものの中に美しさや幸せを見いだしてこの世界は素晴らしいと歌う曲。その詞のように、彼は自分だけではなく、この世の生きとし生けるもの全てを肯定していたのではないかと思います。
原始的な叫びを感じる
宮本浩次の歌声
以前、エレファントカシマシでの宮本浩次さんの歌声を分析した時には、自ら壁を作ってそこにぶつかって行くみたいな感じが前面に出すぎていて、正直、聞き続けるのがやや苦痛だったのですが、最近のソロ作品の歌声にはとても大きな衝撃を受けました。私にとっては甲本ヒロトさん以来の衝撃です。
エレファントカシマシの時に比べ、ソロ作品での声の方が格段に素直になっているように思います。バンドでは意識的にしろ、無意識的にしろ“こうあるべし”というのがあるのに対して、ソロでは自分の歌いたいように歌えているのかもしれません。嘘のない声、素直な声は聞く者の心をダイレクトに揺り動かします。
また、宮本さんはテクニックがあるのに、あえてそれを使わずに歌います。技術的な完成度だけを求めているわけではないからなのでしょう。歌声を聞きながら、私の脳裏には原始の人間の姿が思い浮かびました。言語を持たず、声だけで身を守ったり仲間とコミュニケーションを取ったりしていた頃の人間の姿。何かそういう、プリミティブな叫びが感じられたのです。
自分が出しやすい音域の中で曲を作って効率的に歌うとか、喉を守るための発声を体得するとかといったことを、宮本さんは一切されていません。喉にかかる負荷も含め、多くの人が一生懸命隠そうとするものを、宮本さんは、どうだ!と言わんばかりにさらけ出す。ここまで自分を包み隠さず皆さんの前に出しているのは本当にすごいことだと思います。そして、自分の全てを見せてあげるというところに、ファンに対する彼の正直さ、懐を開放するようなやさしさを感じます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
