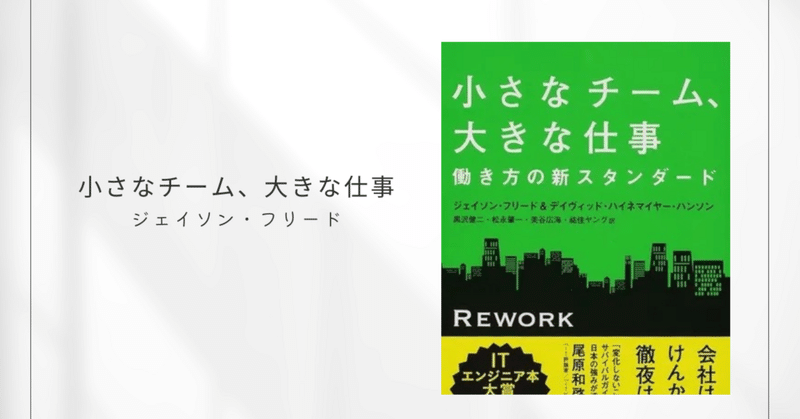
ジェイソン・フリード『小さなチーム、大きな仕事』
ジェイソン・フリードさんは、37signalsというソフトウェアスタートアップの創業者で、37signalsは従業員16人ながら300万以上の顧客を有する未公開大企業です。
37signalsは自己資金のみ、小さなチーム、週休3日の省エネ稼働で大きな仕事を成し遂げている会社ということで名を馳せている会社でして、本書はその秘訣、ベースになる考え方を連ねた啓発本というのが正しいでしょう。
特に緻密なロジックに基づいた何かという訳ではないので、いくつか印象的だった部分について引用して取り上げることで本書の振り返りとしたいと思います。
「失敗から学ぶこと」は過大評価されている・・・失敗は成功の源ではない。・・・一度失敗している人は、何もしなかった人と同じぐらいにしか成功を収めていない。成功だけが本当に価値のある体験なのだ。
なぜ行なっているのかはっきりとはわからないけれど、何かに取り組んでいることに気づいたことがあるだろうか?誰かがあなたにそれを行うようにといったから?・・・だからこそ、なぜそれに取り組んでいるのかを自問してみるのが重要だ。なんのために行うのか?誰のためになるのか?その裏にある動機は?
僕らは全員、見積もりが下手だ。それについてまったく何も知らないのに、それがどのくらいかかるかを予想することができると僕らは考えている。
顧客には耳を傾けるが、そのあとは人々が言ったことは忘れてしまうほうがいい。・・・スプレッドシートやデータベース、ファイリングシステムは必要ない。本当に気にしなければならない顧客の要求はあなたが繰り返し聞くことになるものだ。しばらくすると、それらを忘れなくなる。あなたの顧客があなたの記憶となるのだ。
「なるたけ早く」と連呼してはいけない。・・・どんな要請の終わりにもいちいち「なる早で」と付けていたら、全ての要請が最重要だと言っているのと同じだ。
ケースバイケースだよなぁと思いながらも、一面ではどれも正しい内容だなぁと思っていました。やはりどうしてもやった方が早いのに手続主義的に手続きを踏んでいることとかもあって、その辺りは「やった方が早そうなので進めてます」で進めるのが正解なんだろうなと。
あとは顧客要望については全く同じことを思う一方で、ROIという指標で意思決定をする組織なのであれば、計測は必要だよなぁと感じます。37signalsもそうですし、先日LayerXに訪問した時にもROI以外の基準として「顧客の使いやすさ」に投資している的な話を伺って、そういう話はどうしたら通せるのだろうか?というのがとても疑問です。「失注はしないしチャーンもしないけど、この機能は絶対にあった方がいいよね」みたいな案件。
以上〜!
※本noteで利用しているAmazonリンクはアソシエイトリンクを利用しています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
