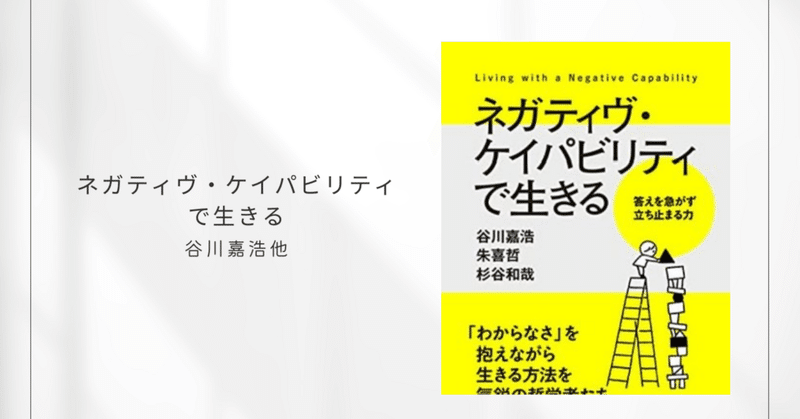
谷川嘉浩他『ネガティヴ・ケイパビリティで生きる』
立て続けに読書会をやることになり、今月は一冊にかけるクオリティを高める方向性で読書をしている感じがします。
ゼミの先輩から読書会にお誘い頂いたことがきっかけで読んでみることに。今月末の会が楽しみです。
さて、ネガティヴ・ケイパビリティだなんて言葉、自分は始めた耳にしました。なんだか変な言葉ですよね。
読み終わった後でも、なぜこんなネーミングなのかあまりしっくり来ないのですが、ひとまず定義を引用しておきましょう。
ネガティヴ・ケイパビリティは、物事を宙づりにしたまま抱えておく力を指しています。つまり、謎や不可解な物事、問題に直面したときに、簡単に解決したり、安易に納得したりしない能力です
本書の主旨から外れてあえて一言でまとめると、「分かりやすい答えに逃げない」ことです。一問一答的な世界観、二元論的理解などはやはり我々人間からすると理解が簡単なので、魅力的なです。ただ、そのような安易な答えに飛びつかずモヤモヤとし続ける力の重要さを著者らは語ります。
この本を読んで、自分の仕事を振り返ると安易な答えに逃げてしまっているシーンが多いなぁと反省しました。
日頃、検証業務を担うことが多い自分の役割は、組織を正しい意思決定にいち早く導くことです。
すなわち、とある検証をした時にAという結果だった場合にはオプション①という意思決定を、Bという結果だった場合にはオプション②という意思決定を行うということを想定しながら業務を行います。
しかし、毎回毎回綺麗にAかBみたいな結果になる分けではありません、「Aよりの結果ではある」とか「なんとも言い難い」みたいな結果であることも正直多い。
こうした時に、自分の役回りとしては、とは言っても検証結果を踏まえて意思決定する必要がある。また、上司への説明をする際にも「検証の結果、なんとも言えません」みたいなことは言いづらいし、「シンプルに伝えること」が求められる。故に、なんらかの証拠を集めてそれらしい仮説を作らないといけない。
そうしているうちに、なんとも言えない結果だったことを忘れて「結果Aだったよね」だからオプション①を取るんだよね、といったことが組織内でコンセンサスを得てしまうことがある。本当はもっとフワッとした曖昧な状態なのだけども、フワッとした曖昧なものを組織で共通認識することは非常に難しいので、理解しやすいそれらしい解釈でコンセンサスを作り出してしまう。
こんなことを振り返りながら思いながら、本書を読みました。
本書で述べられていましたが、社会の要請として「分かりやすく伝える」ことが非常に強いなぁと感じます。
分かりやすさは魅力的なのだけども、それによって失われるものの大きさをケアした上で、分かりやすさに操られないように、問いを持ち続けなければならないなぁと思うのでした。
内省を迫られるいい本でした!
※本noteで利用しているAmazonリンクはアソシエイトリンクを利用しています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
