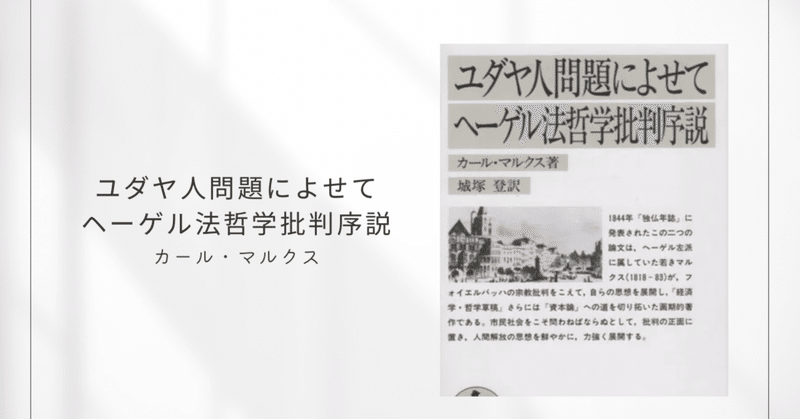
カール・マルクス『ユダヤ人問題によせて/ヘーゲル法哲学批判序説』
久しぶりに古典を読みましたが、やはり難しくて良いですね。古典は必ず価値があると前提を置いた上で、読むときには一回で分かるつもりで読まない、繰り返し読む前提で読むことが肝心だと思っています。
何を言ってるのか分からないけど、ところどころに理解ができる金言が眠っていて、「あー、そういうことを言っていたのか」と気づくことが出来るんです。2度目に読んだときには前回線を引いていた金言の論証部分が見つかったりして、どんどん理解が深まってくるものです。
本書は社会人になる前月に買って依頼、ずっと読みたかったのですが、ずっと積読になっていた本です。2週間くらいかけてゆっくりと味わうことが出来ました。
もちろん、何を言ってるのかよく分からなかったのですが読み通してみて「ユダヤ人問題によせて」は前半で理論の構築をして、後半でユダヤ人問題に当てはめた論証をしているのだという構成と理解しました。前半、抽象的な話が続くなぁと思っていたら後半で急にユダヤ人問題への適用がされて、あ、そういうことだったのねとなりました。
さて、おそらくマルクスの思想史に本書が位置付けられるとした時の、最も重要なコンポーネントは理解したので、そちらについて紹介します。
すごく雑に言うと、政教分離の話なのですが、ロックが『寛容についての手紙』で展開したような現代に引き継がれる政教分離の議論とは少し性質の異なるものです。
僕なりの言葉でまとめると、マルクスの言い分はこうです。
宗教的なドグマが市民生活の中に埋め込まれた時、仮に国家が宗教を揚棄することが出来ても、ドグマは市民社会の中にあり続けるゆえに、市民らは宗教的に解放され得ないであろう、と。
このことからマルクスは、ユダヤ教徒のドグマは貨幣であり、それは市民生活の中に埋め込まれつつあり、ゆえにユダヤ教徒がユダヤ教を揚棄したとしても、ユダヤ教徒がキリスト教国家において受けている不遇な処遇から解放されるための解放はなし得ないだろう、という旨を多分述べています。
ここでマルクスの資本主義批判とユダヤ教批判が繋がるんだなぁと思ったのですが、マルクスはユダヤ教を廃棄する必要があるという立場を取ります。その理由は、彼らが貨幣崇拝を宗教的なドグマとしており、その宗教的ドグマがよに広まることで、世界が私利私欲のうずまく利己的な世界へと変貌してしまうからである、と述べています。
今から考えるとユダヤ教徒のドグマが貨幣というのは、随分乱暴な物言いだなぁと思って読んでいたのですが、マルクスがこう考えるに至った背景を次は知りたいなぁと思いました。
映画『マルクス エンゲルス』もとても面白い名作です。
※本noteで利用しているAmazonURLはアソシエイトリンクを利用しています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
