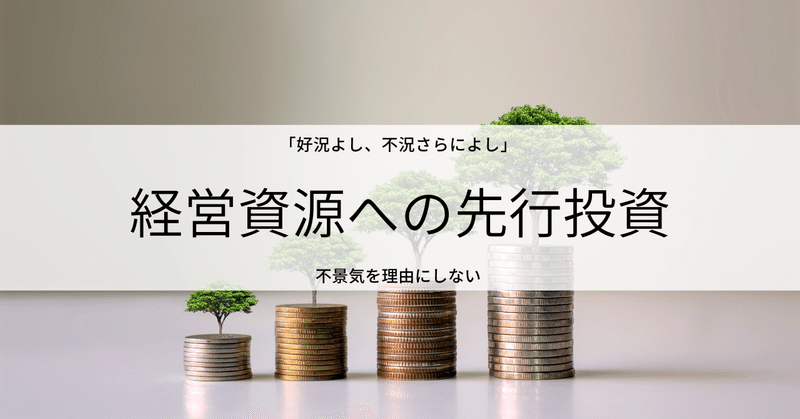
経営資源への先行投資ができているか?!
本日は、東洋経済オンラインの記事から話題提供します。
『東京女子医大で400人の看護師退職に続き医師100人超が退職!?』
東京女子医大が、大変なことになっていますね。コロナ患者の対応もあり、経営がひっ迫した状況に陥ったため、人件費削減に走った。
その結果、大量の看護師・医師が退職している、とのこと。
東京女子医大は、日本で唯一の女子医科大学であり、日本を代表する医師が揃い、外科分野で国内トップレベルの手術件数を誇る。名門医大としての存在感を放っている。
しかし、その病院経営の実態は…。
経営の問題点は色々ありますが、看護師400人の退職や医師100人の退職を決定付けたのは“給与”でした。
元々、東京女子医大の給与は、一般病院に勤務する医師よりもかなり低い、といいます。
それでも、多くの医師が望んで東京女子医大に働きに来るわけは、“名門”というネームバリュー。
安月給でも、国内トップレベルの医療を学びたい、という志を持った医師が集まります。
また、看護師も同様に、“名門”に惹かれて就職するが、結局、長く続けられずに、通常でも、毎年300人前後が入れ替わっているといわれています。
今回、コロナ禍の経営環境変化に加え、働き方改革の流れも影響し、看護師や医師の“給与”にしわ寄せが及び、最終的に大量の看護師・医師の退職に至った、と言います。
松下幸之助は云います。
「好景気のときは駆け足、不景気はゆっくり歩くようなもの」
不景気は、調子がいいときに目に入らなかった欠陥に気付くタイミングであると捉えました。
この発想から以下の教えを残します。
「好況よし、不況さらによし」
そして、この教えの裏には、大不況下でも社員を一人も減らさなかった松下幸之助の判断があります。
“給与”は、経営資源である「ヒト」に対する先行投資といえます。
この記事が本当ならば、「ヒト」に対する投資を怠ったり、大量の離職を引き起こした東京女子医大は、今後、時間をかけて衰退していく、そう感じています。
多くの会社は、東京女子医大を半面教師としてみているかと思います。でも、それをきちんと仕組みとして会社制度に落とし込めているか?と問われると如何でしょうか?
あなたも、そのような視点でこの事例を読み取って頂ければと思います。
今回取り上げた東洋経済オンライン記事は以下
『東京女子医大病院「400人退職」の裏にある混沌』(2020/7/16)
https://toyokeizai.net/articles/-/363372
『スクープ!東京女子医大で医師100人超が退職』(2021/4/20)
https://toyokeizai.net/articles/-/423926
※本noteは、過去のメルマガで配信した内容をリライトして執筆しています。この記事内容をメルマガで配信したのは、2021年4月21日でした。
当時から、ずいぶんと時間が経過し、更なる話題が取り上げられています。東京女子医大の今後の経過を見守りたいと思います。
もし、私のメルマガにご興味を持って頂けたなら、以下からご登録下さい!
https://55auto.biz/abco-biz/registp/abco-biz.htm
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
