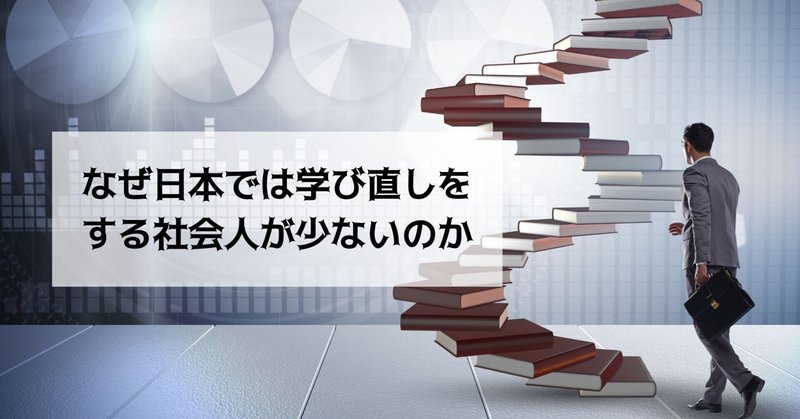
なぜ日本では学び直しをする社会人が少ないのかー1/2
自己紹介
ご覧頂きありがとうございます。新卒で食品会社に就職し、営業職を経験したのちにアメリカの子会社に赴任。約10年間海外駐在しています。
自分自身への備忘録も兼ねてアメリカでの体験や自身の考えをnoteに残していきたいと思います。同じ境遇やこれから海外に挑戦したいという方にとって少しでも参考になれば幸いです。
はじめに
最近、社会変化の加速や長寿化もあり、社会人の学び直し、リカレント教育、リスキリングのように言葉は違えど、再教育の重要性が叫ばれているように感じます。
しかしながら下記データにあるようにOECD加盟国の中で日本の再教育への参加率は下から3番目という状況です。

確かにアメリカの同僚は、就業後に仕事に役立つ単位を取りに大学に通ったりしています。それもいわゆる「意識高い系」という感じではなく、日本人が英会話教室やパソコン教室、フィットネスジムに通う感覚です。
日本の教育水準は高いと思いますし、日本人の基礎能力も世界的に見て高い水準だと感じます。しかしながら学び直しとなるとなぜ日本ではなかなか普及しないのか、その理由を自分なりに考えて見ました。
学び直しは投資効率が悪い?
日本で学び直しが進まない理由は色々あるとは思いますが、最大の理由はスキルアップと報酬(=昇給)の関係性の低さにあると感じます。
当然学びにはコストがかかリます。金銭的なコストもあれば時間的なコストもあると思います。それだけのコストを投下したにも関わらず得るものが少なければ投資しようとは思わないのは国籍関係なく合理的な判断だと思います。
企業や職種にもよりますがアメリカでは一般的に毎年給与更改があり、評価に基づいた次年度の報酬体系が社員一人一人との面談で通知されます。そのような機会もなく当たり前のように翌年の報酬額が決まる日本とは状況が大きく異なるなと、給与更改という仕組みを始めて知った時に驚いた記憶があります。
通知方法だけの違いということではなく、アメリカの給与更改は会社と従業員が対等な立場(少なくとも表面上は)であり、提示された報酬体系に納得がいかなければ署名を拒否することも可能です。そういう意味では給与更改は従業員の権利として認められた「交渉の場」であるとすら感じます。
報酬体系を拒否された会社側は、報酬体系を見直すか、交渉決裂(=離職)を覚悟するかということになります。つまり離職によるダメージと報酬増額を天秤にかけて最終判断を下さねばなりません。
もちろん会社側としては離職ダメージ最小化のために、従業員に依存した「余人をもって替えがたし」という状況を作らない仕組みや常日頃のマネジメントが極めて重要になってきます。
従業員側から見ると、その逆で「余人をもって替えがたし」という状況を作っていくことが、自身の雇用を守り、給与更改という交渉を優位に進めていくために重要になってきます。大まかに分けるとその状況を社内価値を高めることで実現するアプローチと、スキルアップを通じて自分自身の市場価値を高めるというアプローチが存在すると思っています。
適正な範囲での社内価値の向上は円滑な事業運営のために必要ですが、自身の業務をブラックボックス化することで、自分以外の人が代わりを務められない状況を作り出し、結果として社内価値を高めようとする人材も出てくるので危険です。最悪のケース、不正の温床にもなりますし、部門長の関与が限定的だと見ると従業員同士が徒党を組んで部門全体がブラックボックス状態という状況すらもあり得ます。
それらを防ぐことは言い換えるとコーポレートガバナンスでもあり、それが担保されていないとむしろ従業員に事業を実質的にコントロールされることに繋がります。彼らも悪意があってそうしているわけではなくて、解雇が一般的な雇用環境では自らの雇用を守るために必死なのです。
そこはある程度雇用が保証されている日本の従業員の思想とは根本的に異なるところだなと感じますので、その前提の大きな違いを認識して日々のマネジメントにあたることが特に日本人駐在員にとっては重要だと感じます。
次回に続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
