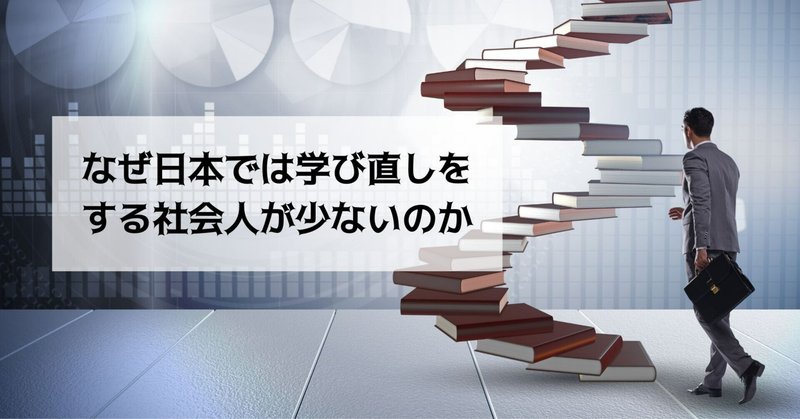
なぜ日本では学び直しをする社会人が少ないのかー2/2
本トピックの前編を見ていない方は以下リンクからご確認ください。
前回からの続き・・・
いずれにせよ一般的には従業員の社内価値がコントロール不能なまでに向上してしまうことに対する予防策を持っているとすると、自身の市場価値を上げることが、交渉力にとって重要になってきます。そしてその市場価値の証明が、他社からのオファーです。
実際、給与更改を待たずして「他社からこういうオファーをもらっていて、自分としてはこのまま働き続けたいがこれだけの待遇差があると…」というような突然の給与交渉も日常茶飯事です。
そもそもアメリカを始めジョブ型雇用が前提の欧米先進国では人材流動性は極めて高く、アメリカでは生涯に11の仕事に着く(=転職回数10回)ことが平均的だそうです。40年前後働くとすると3〜4年で転職している計算となります。むしろ社内での昇給だけではインフレ率+αで、大幅な報酬UPは転職でしか期待できないというのが一般的な認識です。
したがって毎年の給与更改や10回の転職タイミングに備え、学び直しにより専門性を深めたり、資格を取得したり、現在の専門性に掛け合わせる専門性を学んだりして自身の市場価値を継続的に上げて行くことが重要視されているのだと感じます。
一方、日本においてはそもそも給与更改というような仕組みがないために、報酬UPの交渉タイミングというのは基本的には転職に限られるのではないでしょうか。しかしながら日本の平均的な転職回数はなんと0.89回です。アメリカにおいては平均的に50回(給与更改+転職)ある交渉の機会が日本では1回にも満たない状況です。
そもそも交渉機会がないなら、交渉材料となる市場価値を上げていこうとはならないのではないでしょうか。むしろアメリカとは対照的に自社でしか通用しない特殊なスキルを習得したり社内人脈を広げて社内価値を上げて行くことの方に重きが置かれるのではないでしょうか。
つまりアメリカでは市場価値>社内価値、日本においては社内価値>市場価値という図式が成り立っていると思います。
これではわざわざコストをかけて学び直しをしようと思う人は少なくなるのは当然だと感じます。
しかしこの0.89回という交渉頻度はあくまで平均値で、転職活動(最終的に転職するかどうかは置いておいて)で能動的に交渉頻度を高めることは可能だと感じています。すでにそのことに気づいている人は増えつつあり、労働市場としてもジョブ型人材の需要増でその土壌が整いつつあるように感じます。
そうなってくると、市場価値を高めて交渉機会を能動的に増やしていく人・社内価値を高めて社内での登用や生き残りを図っていく人という二極化が進んでいくのではないかと考えています。
最後に
二極化が進むのだとしてもどちらが良いかということではなく、各々のキャリア戦略の違いだろうとは思います。しかしながら後者の決裁者は究極的には会社であり、自分ではありません。そしてこのVUCAと言われる時代にあっては会社が今までと同じ状況で存続するとも限りません。ある日突然、築いてきた社内価値が無力化されてしまうということも十分にあり得ます。そのリスクは覚悟しておいた方が良いでしょう。
学び直しと言っても、資格取得のように大袈裟に考えることはなく、日々の業務に役立つ本を読むだけでも十分だと思っています。むしろ何事においても継続のコツは心理的な負担を軽減し、日々のルーティンに取り込んでしまうことだと考えています。
またアウトプットを意識して学び直しのトピックを選定することも重要です。Excelの講習を受けてもほとんど何も習得できなかったのに、実務で実際に困っていることをググって数式を覚えたらなかなか忘れないどころか、それを多用するようになったという経験を誰しもお持ちではないでしょうか。
残念ながら時間やお金をかければ比例するように結果がついてくるというものではありません。むしろ投資した分だけ結果に対する期待値が上がって、それに満たない場合ガッカリしてしまうのが人の性というものではないでしょうか。
それを逆手にとって、まずは手軽な学びで期待値を下げて、その投資以上のリターンを得るという小さな成功体験を積み上げることで学び直しに対する心理的ハードルは下がってくるのではないでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
