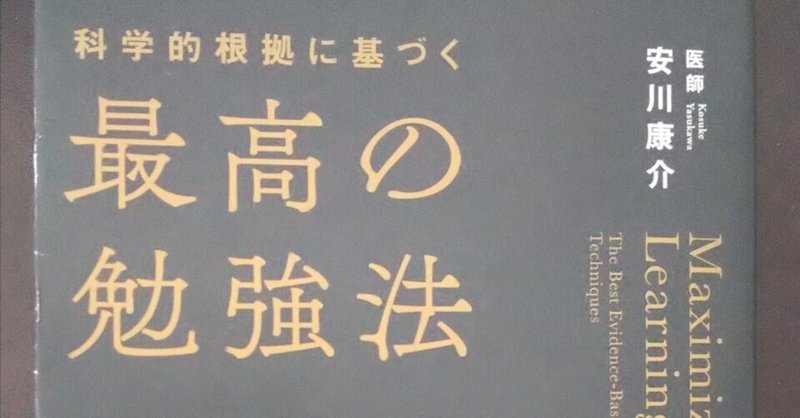
読書雑記 最高の勉強法
ふと自身のnote見返してみるとあることに気づく。
「コイツ食べ物のことしか書いてねえ!!」
元々noteを始めたのはプロフィールにある通り
雑多にアウトプットするスペースとして活用予定。読書、料理、外食、お菓子、お茶、映画、卓球、etc...
だったというのに…。これではまるで僕が食べること以外ほとんど何も考えてない人間のようなのでそうだよ直近で読んだ本について色々書いていくことにしました。なお注意点として書籍に書かれていないこと(僕自身の知識や体験から出てきた意見とか考えとか)も文中で書いています。そのため内容の正しさについては保証しません。だからこそタイトルも要約とか感想とかじゃなく雑記としてます。
今回読んだのは安川康介氏著の「科学的根拠に基づく 最高の勉強法」。
効果の高い勉強法を各種実験や論文といったエビデンスを元に解説していく本となりますね。本筋はタイトル通り効果の高い勉強法を紹介しており、また関連として効果の薄い勉強法、記憶術、心・体・環境についても書かれています。
そうそう、僕は読書後や映画鑑賞後などその内容や印象に残った箇所、感想などを用紙に殴り書きしてるのですが、せっかくなのでそれもアップしときます。あくまで自分用のメモなので汚いけど…。もっとも真面目に書いても根本的に汚いことに変わりはないけども。デジタルなら綺麗に書けるけど、面倒だし、何より思考が抽象的な段階だとアナログの方が便利なんだよなあ…。

構成としては
1.効果の薄い勉強法
2.効果の高い勉強法
3.記憶術
4.心・身体・環境
となっており、特に1章、2章については、「脳への負荷と勉強効果は正の相関がある」ということを頭に入れておくとより読みやすくなるんじゃないかな。
効果が薄い勉強法
まずは効果の薄い勉強法についてですね。まあこれは本筋じゃないんですけど。
繰り返し読む
初見時以外は効果が薄いという話ですね。初見時は理解するために色々考えたり、初めて知ることが多いため脳負荷は大きいが、2回目以降は初見時のことを覚えてるため脳負荷が小さくなってしまう。しかもこれ厄介なことに2回目以降スラスラ読めるもんだからしっかり理解できてしまうと過大評価を起こしてしまう。因みにこれを「流暢性の錯覚」というらしいです。言葉自体は初めて聞いたけど、感覚としてはメチャクチャ分かるなコレ…。
本書はあくまで勉強法の本なのでその部分にしか触れてないけど、エンタメなんかも初見が一番面白いのは理屈としては近そう(もちろん他にも理由はあるけど)。エンタメの場合は脳負荷というより情緒の動きみたいな表現の方が適切かな。
ハイライト
マーカー引いたりとかそういうのですね。パッと見は綺麗だけど、それ故やった感が出てしまう。
自分もマーカー引くの嫌いだったなー。単純に面倒だし、該当箇所の印象が強くなりすぎて、それ以外の部分の印象が薄くなるし…。って思いながら読んでたらまんま同じことが書かれていて笑ってしまった。
ノートに書き写す、まとめる
これ読んだ時はちょっと疑問だったんですよ。書き写すのが効果薄いのは分かる。脳に負荷を与える余地が少ないので。ただまとめるの方はそこそこ負荷かかるし効果あるんじゃない???って。
じゃあなんでかって言うと要約する能力が低い人がやっても効果が薄いってことだそうです。そして大体の人はその能力は高くないと言う身も蓋もない話。だから要約する前に要約の訓練が必要なんだとか。僕もおそらくその大体の人側の人間なので要約の訓練本でも買ってみよかな。
好みに合った勉強法
これについては若干毛色が違いますね。他の3つはエビデンスを元に否定されていますが、これについては好みに合った勉強法の有効性はちゃんとエビデンスを示せていない、と言うに留まってます。あくまで否定はしないけども肯定もしない、次項に効果が高いとわかってる勉強法を紹介するので、この勉強法を優先させる必要はない、くらいのニュアンスに感じました
むしろこの項で興味深いのは「実際に効果の高い勉強法は必ずしも本人が実感できるわけではない」という部分ですね。最もこちらについても次項で詳しく話すので軽く触れられる程度ですが。
効果が高い勉強法
こちらが本書の主題。そのため実験や論文など先の項と比較して詳し目に書かれています。
アクティブリコール
思い出そうとしたり、実際にアウトプットしてみたりですね。具体的には過去問を解いたり、それこそ先にアップしたように読書後用紙に殴り書きなんかもその例です。意外と自分ちゃんとやってんなと嬉しくなる。
また思い出すきっかけが少ないほど効果は高くなります。穴埋めなんかより何もないところから思い出す方が良いって話ですね。特に何もないところから思い出すというのは、頭の中だけで可能なため満員電車などでも誰にも迷惑がかからず、道が空いてることが前提ですが運転中などでも行えるのが良いですね。
分散学習
間隔を空けて勉強すること。例えばある範囲の学習を3時間続けて行うより、1時間を3回に間隔を空けて3回やる方が効果が高い。また試験などでこの方法を使う場合、試験までの間隔が長いほど、開ける間隔は長い方が効果は高いそうです。脳負荷と学習効果の相関の件から考えるに、ある程度間隔空いてうろ覚え状態になってしまった方が、2回目の学習において脳負荷が増える=効果が上がる、ということなのでしょう。
本書ではこの2つがとりわけ高い学習効果があると位置付けており、アクティブリコールを行う学習を分散して行うことが最強であるという結論を出しております。
他にも上記2つほどではないが、高い効果を期待できる勉強法も紹介しています。
プロダクション効果
ブツブツと声に出しながら勉強する。音読なんかもその1つ。インプット・アウトプット共に効果あり。
プロテジェ効果
人に教えるつもりになって学習する。よく勉強法は教わる側だけでなく、教える側にもメリットがある、と言われるのがそれですね。
実際自分が理解するだけならある程度抽象的理解のままでもイケるけど、人に教えるとなると具象的なところに落とし込まなきゃ無理だしな…。実際に教えなくても教えるつもりで勉強することによって、十分効果はあるそうです。
精緻質問
なぜ?どうして?という質問をしていく。例えば「〇〇なのは△△のため」という学習をするよりも、「〇〇なのはなぜか?」という問いに対して自身調べて「△△のため」と学習した方が効果が高い。ただしこの勉強法はその分野に対しての前提知識がないと効果が薄いため、アクティブリコール、分散学習に比べ評価が中程度となっている。
自己説明
学習内容や過程の理解について説明を行う。「もう少し詳しく」「この学習内容の中で未知のものと既知のものは?」「今回の学習で自身の知識と結びついたものは?」といった問を行うことで自己説明を促すことができる。
ここの部分をリアルタイムで読みながら「あー、なるほど。メタ認知の重要性の話に近いなー」って思ってたらメタ認知の話も出てきた。答え合わせ早くない?こうやって読みながらまさにその通りの体験をするとやはり印象に残りやすい。精緻質問の話とかより断然覚えてるし。逆にメタ認知が全く出来てない場合は「何処が分からないのかが分からない」的な状態になっちゃうのかな。
僕個人としては経験から自己説明はかなり効果高いと考えてるのですが、こちらは纏める力が必要ということでアクティブリコール、分散学習と比べ評価が中程度だそうです。
インターリービング
似ているが異なった複数のスキルやトピックを学習する方法。これの効果が高まる理由としては単一のスキルのアウトプットではそのスキルのアウトプットであるということが分かるのに対し、複数の場合はまずどのスキルを使うのか?という問が生じる=脳負荷が高くなるということでしょう。また結果として分散学習を行うことにもなるという点も大きい。
そういえば僕が以前資格試験の勉強で使っていたアプリも過去問をトピックごとに出すか、完全ランダムで出すか選べたな。最初の方はトピックごとの出題、途中から完全ランダムで解いてたけど、これ正着だったのか。
因みにこれに関しては勉強以外、即ち運動や芸術関連にも応用可能だそうです。
記憶術
ここに関しては本筋とあまり関係ない上に、僕自身あまり興味がないので簡潔に。
対象とイメージを結びつけるイメージ変換法やら、最初に特定の収納場所を思い浮かべて記憶したいものをそれぞれに収納する場所法、対象で1つのストーリーを構成していくストーリー法が紹介されてます。
ただいずれも対象と別の発想やら記憶やらが必要になるため、素直に記憶対象を背景要素と合わせて覚えちゃった方が楽な気がするんですけど、どうなんでしょ。
心・体・環境
こちらについても本筋とはあまり関係ないので簡潔に。とはいえ色々思うところがあるトピックもあったのでそこは深堀。
勉強のモチベーション
僕は勉強のモチベーションについては、大人になってからはそこそこですが、学生時代は低く結構嫌嫌やっていた記憶があります。勿論良い点取ったり、志望校受かったりした時はプラスの感情を覚えましたが、それらはあくまで勉強したことによる結果であって勉強自体にはずっとマイナスの感情を持っていました。
理由としては本書で取り上げられている自己関連づけ効果によるものでしょう。読んで字の如く関連いていることほど覚えやすい=モチベを保ちやすいという話。仕事の勉強については勉強中に「あー、あの場面これ使えたな…」とか、逆に仕事中に「これあの内容と繋がるな」などそのままではないにせよ、関連性を実感できるけど、学生の勉強はそれが全くないので、そらモチベも上がりません。学生の段階でどういうことをしたいのか、そしてそれと今の勉強の関連を見出せる人くらいしか学生時代の勉強のモチベなんて持てないように感じますね。
そういえば子持ちの親戚から「キッザニアすげー良かった(意訳)」という話を聞いて調べたけど、確かにあれはどういうことをしたいのか?のアンサーの補助として最適解と言っていい施設だったな…。キッザニアに限らずどういうことをしたいのか?のアンサーの補助になる施設ってどうしても都市部に集中するから、やはり子育てするなら都市部かな?と考えた瞬間でした。最もそういった施設側もコロナを機にリモート関連充実して、地方からでもアクセスしやすくなってますけど。
他にも「自分は〇〇出来る」という認知から学習効果を上げる自己効力感や、自己効力感の高め方、モチベを高めるにあたり参考になる自己決定論やモチベの種類、動機付けなどかなり有益なトピックが揃ってます。
我々が感覚的に理解出来ていること論理的に説明してくれており、それこそ本筋である効果の高い勉強法に勝らるとも劣らずの内容であると感じました。
他のトピックとしては、勉強のヒント、睡眠の大切さ、運動の大切さ、勉強で不安を感じた時などありますが、いずれも本筋ではなく、また自分としては「まあ、そうだよね」くらいの感想で終わってしまったり、既に実践してるようなことがほとんどだったため割愛。別段ディスってるわけではなく、新たな発見や気づきがなかったの意です(内容自体は今まで感覚的理解だったところを論理的理解に落とし込めたりもしたので、読んでて普通に楽しい)
以上、雑記でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
