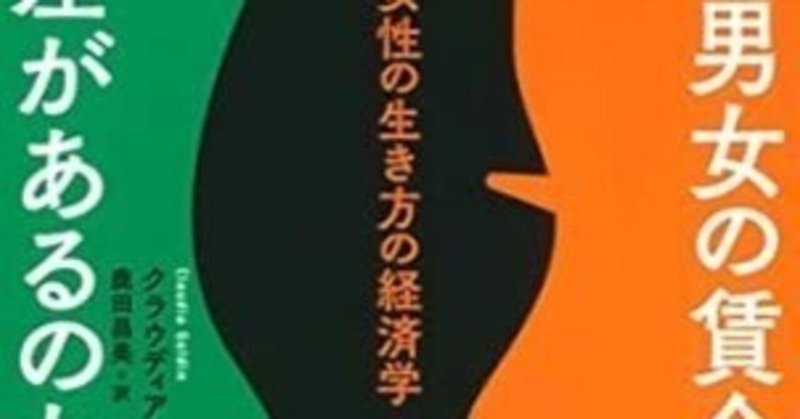
「なぜ男女に賃金の格差があるのか」を読んでみた。
「2023年のノーベル経済学賞受賞者が書いた本とあっては読むしかない。」「いつか読んでみようかな~」と思いながら早半年、ついに読んでみて感想と所見を書いていきたいと思います。
前半~女性進出の歴史~
この本の前半では、アメリカでの女性の社会進出の歴史を解説しています。
この中で、ゴールディン氏は、1900年代から2000年以降までを、女性の生涯未婚率、初産年齢、初婚年齢などによって5つのグループに分けています。
第一グループ 1900~1920
第二グループ 1920~1950
第三グループ 1950~1980
第四グループ 1980~2000
第五グループ 2000~
それ以降、それぞれのグループについて解説がされていきます。
第一グループ
この時期の女性は、ほとんどがキャリアか家庭の二者択一でした。そもそも、社会進出自体が難しかったからね仕方ないね。(一応、両方を達成した人もいなくはない)
第二グループ
この時代は仕事の後に家庭が中心だった。この時代に、産業革命の技術進歩により、力の弱い女性でも、働ける職場が増えていった。このことがより社会進出を後押しした。
ここまあ、個人的に面白くて、GDPに家事育児などの無償労働を入れるべきかどうかの論争を少し取り上げていた。発案者のクズネッツ自身も、相当に苦慮したそうで、入れるべきとした学者もいたが、彼は、信頼に足る指標がないとして加入を断念した。
確かに、GDPに家事労働は算入されていないが、全く無視しているわけではなく、計算が内閣府によってなされており、それによると、おおよそGDPの26%(2021年度)ほどで、決して無視できないものである。
ほかにも、マリッジバー導入から、撤廃の経緯も、示唆的で興味深かった。マリッジバーとは、結婚したときに、そのどちらかが(多くは女性)仕事をやめねばならないという法律だ。まあ、明らかな男女での職業差別だが、これが世界恐慌時に拡大した。そして、1950年代の好景気に縮小した。
これは、少なくとも職業差別の解消には、景気をよくすること、もっと言えば、その産業で人手不足にさせることが、よい解決策になるということである。中公新書の本で「女性の社会進出の遅れ」を日本の長期停滞に結び付ける(帯のある)本があったが、因果が逆である。長期停滞であったからこそ、女性の社会進出が進まなかったのではないか。
以下のグラフは1991年以降の女性の労働参加率の推移であるが、リーマンショック時や東日本大震災の時に停滞or減少していることがわかる。
なお、これは年齢別にみても同様で、年代別にみると、特に若い世代で顕著に減少していたり。停滞していることがわかる。

資料出所 総務省統計局「労働力調査(基本集計)」、総務省統計局「国勢調査」(1950年)(下端が48%なのに注意してね)
(因果関係は置いといて、安倍政権時代の功績だと思うんだけど、あまり言ってる人見たことないな….)
第三グループ
この時期は戦争から、兵士たちが帰還した影響もあってか、結婚&ベビーラッシュが続いた。この影響で、大卒女性の初婚、初産年齢が劇的に下がった。大学を辞める女性も増え、女性の社会進出は後退した。これをベティ・フリーダンなどが「新しい女性の誕生」で嘆いている。1920年代の女性は夢を追っていて素晴らしかった。だが今の女性はそんな気持ちが全くない。と。
まあ、(彼女が言っていることは) 嘘なんですけどね。
第四グループ
この時期、女性の社会進出の大きく進展させるできることが起こる
ピルの発明(&承認)である
ピルの発明により、女性は避妊の選択が可能になり、妊娠を遅らせ、いわゆるデキ婚でキャリアを諦めなくてもよくなったのだ。しかし、初産年齢の増加は、彼女らにとって思いがけない障害をもたらした。加齢による不妊である。
第五グループ
第四グループよりも、より家庭を求める傾向が強くなった。これは、第四グループが年齢による不妊に悩むさまを見ていることにも通じるものがある。
今後、もし第六グループと呼ばれるものができるとするなら、
私の個人的な意見になるが、それは、不妊治療技術の進歩による、平均初産年齢のさらなる増加が見込まれる。40代でも簡単に子供が産めるとなったとき、女性のキャリア向上、果ては出生率の改善も期待できる。
後半~なぜ未だに男女に賃金格差があるのか?~
上司の偏見や、女性の交渉力の弱さ、女性と男性の職業の偏りか?
確かに、それが格差の原因であることは事実であるが、それを解消したとしても、格差はなくならない。
では何が原因でこうなったのであろうか?
これが、ゴールディン氏の業績である。彼女は、これが不定期な長時間労働を求められる仕事(=「貪欲な仕事」と呼ばれる)であることを喝破したのだ。
これらの仕事は、金融業界や、医師、弁護士、大学教授、官僚などが該当する。
子供が風邪をひいたり、発表会があったりしたとき、不定期にどうしても休みを取らねばならない。これと、不定期な長時間労働の仕事が非常に相性が悪い。
休日出勤&サービス残業上等の人が出世or生き残る職業では、女性が子供が生まれたら、どうしても仕事量が他の人より劣り、出世レースから外れたり、挙句仕事をやめてしまうこともありうるのだ。これが、男女の賃金格差の主要因である。
なるほど、原因は分かった。では、どのようにすればいいのか。彼女はこれに対する解決案の一つとして、薬剤師の例を挙げている。
薬剤師は昔は、男女との賃金格差が大きかった。しかし、薬局の大規模化、システム化により、規則的な勤務や、従業員が休んでも、代わりに働く人が補充しやすくなったことにより、大幅に改善した。
もちろん、男女の賃金格差をなくすのは簡単ではない。一部のフェミニストに見られるような男性(や社会制度)をただ悪者ににして、排除や破壊することで達成できるものでは決してない。
家事育児とキャリアの両立には、男性の助けは必要不可欠であるし、男性にとっても利益のあることである。(子供の成長に第一線で関われることなど。)
最後に
男女関係の話って、SNSだとかなり荒れやすい。罵詈雑言の応酬で嫌になる。
もうほんと、うんざりする。
そんな中で、彼女の本は冷静にデータに沿った議論を展開している。
男女が障壁なく、健やかに過ごせる社会をみんなで一緒に作っていくための重要な道しるべになる本である。
この本の日本verを訳者のあとがきで見たかったけど、なかった。残念。
みんな読んでみてね~
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
