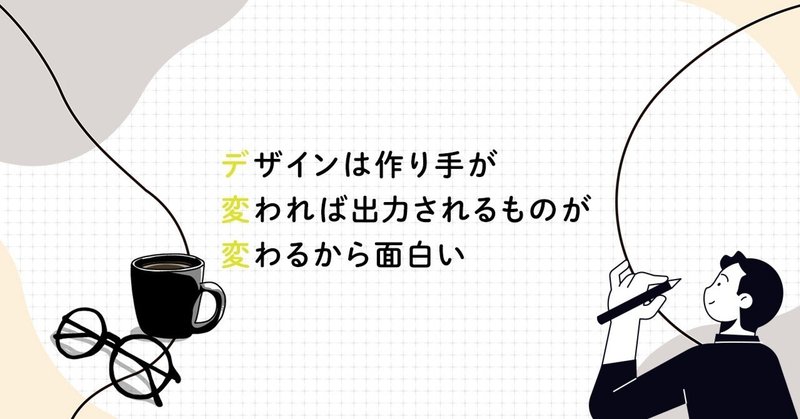
デザインは作り手が変われば出力されるものが変わるから面白い
デザインコンペで他のデザイナーの制作物を見て、同じ依頼内容でも作り手が変わると出力されるものが大きく違って面白いなと感じる今日この頃。同じ内容でもそれぞれのデザイナーの脳内でのプロセスの違いによって変化する。私は、参考サイトでサービスとターゲットやニーズが近いものを探してベンチマークとなるサイトをリストアップしてWEBサイト全体のイメージを紙に箇条書きで書いて言語化しています。書き出す際にどんなイメージを与えたいかを考え、なるべく形容詞になる言葉を書き出します。WEBサイトの課題を洗い出し、役割や目的を書いて、そこからツリーのように紐づけて関連するワードを書き出していってコンセプトを決めています。それぞれコンペに応募したデザイナーの方がどんなプロセスで制作物を完成させたのか興味が湧きます。
また、デザイナー自身の練度や経験値によってもクライアントの要望に対する理解度やコンセプト設計の差で制作物としての解像度の差が生まれるので勉強になるところがあります。そのデザイナーの見る視点の違いによって切り口も変わるのでその切り口があったのかと感心することが多々あります。デザインを通していろんな人のいろんな視点に触れることができるのは、デザイナーとして貴重な機会だと思うのでコンペにチャレンジする意味は大きいと思います。デザインを制作する上で空から眺める鳥のような広い視点が多様なニーズが増えている世の中で求められるだろう。だからこそ世の中に出回っているデザインを日頃からどんな視点でどんな切り口で作られているのかいろんな角度で考察する洞察力を持たないといけないなと日々、感じています。
私は、WEB制作で大切なのは、目的や役割を果たすものになっているかどうかだと考えています。どんだけいいデザインでも求められる役割を果たさないと意味がないですし、クライアントも何か目的があって何かしらの役割を持たせたくてWEBサイトを作ってる訳なので。それぞれクライアントごとにいろんな目的があると思います。採用力を強化したくてとか自社のサービスの認知度を上げたいとか自社の技術力をアピールして受注に繋げたいとか。
コンペにおいてそのWEBサイトとしての役割としての最適解とWEBサイトとしての目的を果たすまでの最短距離を目指せるかが評価のポイントになるのだと思います。だからこそ、世の中にあるWEBサイトやWEBのサービスの役割の意味を考えてどうしてこの形に行きついたのだろうか日頃から疑問を持つ視点を持つことも必要だと考えています。
終わりに
ノリと勢いで書き進めましたが、コンペは学ぶことが多くて楽しいということをなんとなく伝えたくて書いてみました。つたない文章ですが、読んで頂けると嬉しいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
