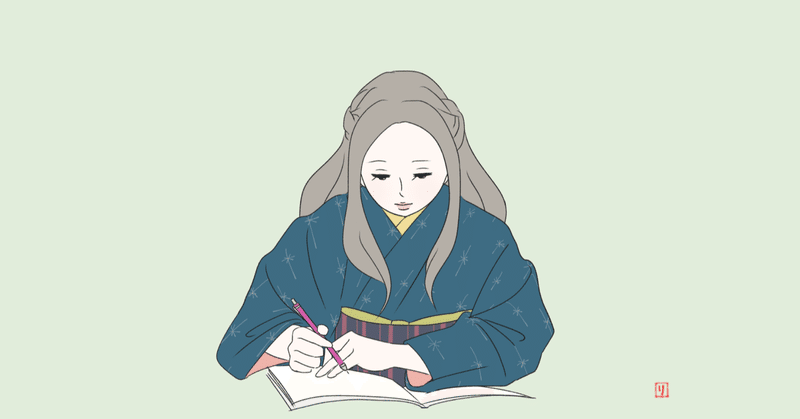
やさしい日本語
【がいこくじん の みなさんへ】
— NHKニュース (@nhk_news) October 10, 2019
たいふうが つぎの どようび から にちようび、とうかいちほう や かんとうちほう の ちかくに きそうです。
とても つよい かぜが ふいて、あめが たくさん ふるかもしれません。きをつけて ください。 https://t.co/47Pb7NhZu6https://t.co/kHlFxQUAnG pic.twitter.com/FSULDk4qqU
この全部ひらがなで書かれたツイートには賛否両論がありました。
・翻訳機能でいいじゃん
・外国人馬鹿にしてるの?
・ひらがなにしても意味ないでしょ
・各言語で書いた方がいいよ
このような批判がありました。
ただNHKニュースのツイートはただひらがなにしているだけではありません。
やさしい日本語なのです。
「やさしい日本語」とは?
・阪神淡路大震災で日本語以外の緊急情報対応が英語・中国語などの主要外国語だけでは不十分
・数十カ国語での対応は不可能
・外国人が理解しやすい「やさしい日本語」を導入することで減災となるのでは?と研究され始めた日本語領域
「地震の時に言語の壁によって大切な情報が伝わらなかった」という反省を生かし、「やさしい日本語」というものが研究されています。
地震の時に電波が繋がらない、電子機器が使えない状態で翻訳機能は使えないかもしれません。
各言語、つまり100近くの言語を使いこなせる人はいるのでしょうか。
それらを考慮するとやさしい日本語の理由、目的は明確なのではないでしょうか。
「やさしい日本語」はなぜ大事か
「外国人には英語を使えばいいじゃん」というのは間違っているわけではないと思います。今日英語は多くの国で勉強される言語ですし、論文やネット記事なども英語のものがとても多いです。飛行機のパイロットたちも航空管制官とのやり取りは英語だったりします。
ただ、英語が苦手な外国人も日本にいます。日本文化が好きで日本語は少し勉強して留学してきました...など。
その人たちにとっては英語でずらずら書かれるよりは簡単な日本語で書かれた方がわかりやすいこともあるのです。おそらく気持ちとしては『英語ちんぷんかんぷんだから、ドイツ語少し勉強してドイツに行ってみたところ、ネイティブのドイツ語は難しく、英語はもちろんよくわからなかった』という感じだと勝手に想像しています。ネイティブの難しさを例えるならば、中学校の教科書レベルの英語は完璧で日常会話もできるものの、急に英字新聞を渡されてしまった...という感じではないでしょうか。
確かにみんな英語を話せれば、やさしい日本語は必要なくなるかもしれません。みんな意思疎通ができて素晴らしい世界かもしれません。ただ、ネイティブの日本語は難しいけどせっかく日本に来て日本語に触れたい外国人だっているはず。文化として保ちたいという気持ちもあるし、そこで英語ばっかり使われてもいい気はしないような気がします。
「やさしい日本語」の仕組み
「やさしい日本語」の作り方というところに詳しく載っていますが、ここにもいくつか引用してみましょう。
・一文を短く、簡単な構造に
・難しい語彙を簡単な言葉に
・曖昧な表現を使わない
・文末をなるべく統一
・ひらがなベース
・一文を短く、簡単な構造に
関係代名詞たくさんの複雑な文とかは大変ですよね、うん、短い文が正義。
・難しい語彙を簡単な言葉に
そうそう、evacuateって言われてもよくわからないけど、runとかdangerousって言われたら逃げられますよね(本当にはevacuateなんて言わないはずですが)。
まぁ「語彙」と言うか「言葉」「単語」と言うかの違いですかね。
・曖昧な表現を使わない
日本語に多い「おそらく」「多分」「〜と思う」はわかりにくいとのこと。
英訳する時に「〜と思います」というのを "I think..." と訳さないと習った方も多いのでは?...そういうことです。
・文末をなるべく統一
文末を何に揃えるのか、それは「です」「ます」「してください」です。なぜこのように文末を丁寧な形にしないといけないんだ、そう思う方も多いと思います。それは外国人の日本語を学ぶ方法を知るとわかると思います。
(『外国人に知って欲しいこと』の中で少し書いています)
・ひらがなベース
あとひらがなベース。中国の方であれば、漢字の方が意味がわかる場面もありますが、漢字が苦手な外国人にとってはひらがなの方がわかりやすい時もあります。ただ、ひらがなにした時には単語と単語の間にスペースを入れると良いでしょう。日本人でもすべてひらがなだと単語の切れ目がわからず、とても読みにくいものとなります。
「やさしい日本語」の良いところ
・情報を的確に伝えられる
・翻訳時間短縮と均一化
『「やさしい日本語」の仕組み』で書いた通り、曖昧な表現を使わずに、簡単な言葉を使って作ります。つまり通常の日本語の文章よりもわかりやすく、
ストレートな表現となっています。
また、"I think..." と翻訳しそうになる「〜と思います」などの必要ない部分がカットされるので、やさしい日本語から英語などに翻訳するのが簡単で、シンプルな文なので表現の仕方が統一され、意味の食い違いが起こりにくくなります。
「やさしい日本語」の悪いところ
・やさしいのルールが決まっていない
・日本語能力試験が基準としてふさわしくない
・やさしくするとニュアンスなどの情報が抜け落ちる
良いところがあれば悪いところもあるのです!笑
実は『「やさしい」とはこのくらい!』という明確なルールはありません。日本語能力試験(N1からN5まであり、N1は日本人でも間違えそうになるレベル)というものもありますが、「N3を持っている人ならわかるレベル」のようなレベル設定ではありません。
また「土足厳禁!」と書いてあるものを「くつを ぬいでください」と書かれると、ニュアンスが変わるような気がしませんか?このように意味は伝わるかもしれないけどニュアンスが少し変わってくることがあります。
日本人に知ってほしいこと
私が日本語チューターをして、学んだことです。
・こどもに話すのとは違う
・正解はない
・英語の方が理解しやすいと思ったらそれでいい
・こどもに話すのとは違う
これは私がある時ハッと気づいたのですが、簡単な日本語、というと多くの日本人は子供に伝わるような日本語を思い浮かべるのではないでしょうか。
例としては「おうちにかえりましょう」と外国人に言っても通じないことがあります。なぜかというと「おうち」という単語がわからない時があるからです。「いえ」と言えば通じたかもしれません。英語でニュースを読める方も、英語の赤ちゃん言葉はわからないのではないでしょうか。
じゃあどんな単語を使ったら良いのか、というと私たちが中学英語で学んだような英単語の和訳だと思っています。シンプルでかつ一番オーソドックスな感じの単語ではないでしょうか。
例文はこちらにも載っているので、是非参考にしてみてください。
・正解はない
・英語の方が理解しやすいと思ったらそれでいい
もともとは震災の時に情報を伝えたい、ということが根底にあるので、伝わればOKだと思っています。だからお互いに英語が少しできるのであれば、英語を混ぜながら話すのも良いし、英語ができる人同士が、わざわざ緊急事態に日本語で話す必要もないと思っています。
お互いに意思疎通ができる方法を取ってみるのがいいと思います。
外国人に知ってほしいこと
・やさしい日本語を知らない日本人もいるということ
・日本人は外国人がどのように日本語を学んでいるのか知らない
・やさしい日本語は少し不自然
外国人に伝えたい、日本人との考え方などの違いです。
(日本人も知って損はないと思います)
・やさしい日本語を知らない日本人もいるということ
・日本人は外国人がどのように日本語を学んでいるのか知らない
中学校などで五段活用の終止形が〜、仮定形が〜、のようなことを学んだと思います。日本人は日本語を話せるようになっている中学生などで仕組みを学びますが、外国人はその活用形を暗記しています。また私たちは「走る」「食べる」などの言い切りが基本形だと考えることが多い思いますが、外国人は「走ります」「食べます」などの丁寧な形を基準に覚えています(全員というわけではないとは思いますが)。なぜかというと会話する際に失礼に当たらないように、「〜です」「〜ます」から習うとのことです。なので子供に話すように「〜だよ」と言われると「???」となる可能性があるということです。
・やさしい日本語は少し不自然
しょうがない面もありますが、明日からやさしい日本語に全部移行します!と言われたら、不自然でむずむずしちゃうんじゃないかなと思います。伝わるのとネイティブが慣れているのは違うということだと私は思っています。
「やさしい日本語」を現実でどのように使っていくか
これをどのように使うか。英語ができる人はそれでもいいのです。
法務省や文化庁でも「やさしい日本語」ガイドラインというものを出しています。
福岡市では市のホームページに「やさしい日本語」についてのページを設けています。岡山県などのホームページでも「やさしい日本語」についてのページを見つけました。
外国人労働者を雇う会社も、従業員が「やさしい日本語」を学ぶ機会を設けたりしています。
英語が苦手だから話すのやめよう、ではなく、簡単な日本語なら話せますというスタンスが大事になる時もあるのではないでしょうか。みんな英語を話せたら便利という面もありますが、世界すべてを英語に染める必要もないし、するべきでもないと思っています。言語も一種の多様性だと思っています。
留学生に本音を聞いてみた
この「やさしい日本語」について日本人と留学生に対して話す機会があったので、そこで出た意見を共有したいと思います。
・(Twitterのつぶやきのような)くだけた文はわからないから、わかりやすい
・中国語ができる人からすると、漢字で意味がわかることが多い。ただ普通の文は難しすぎるから、シンプルな文章で漢字を入れてくれると一番良い。
・中国語がわからなくても日本語を学ぶ中で漢字もそれなりに学んでるから、漢字があったほうがわかりやすい時もある
・単語と単語の間のスペースでわかりやすくなる
最後にひとこと
最近の記事では、こういうのもありました。
知らない人は多いけど、導入していくのが良いのではないか...という記事。今はネットがつながり翻訳も簡単にできると思うので、あまり重要性は感じないかもしれないですが、震災の多い日本ですし、これを機に少し勉強してみるのも良いのではないでしょうか。
やさしい日本語の良いところ、悪いところなどは参考にしたページもありますが、教えてきた中で私が思うこと、なども含まれています。
私は本職として日本語を教えているわけではありません。ちょうど日本語チューターとして留学生に日本語を教える機会があり、その時に「日本語の教え方」などを日本語の先生に教えてもらいました。それがなかったら私はこんなに日本語について考えることはなかったと思います。
なので間違っていることもあるかもしれません。アニメなどが好きで、そこから日本語を覚える外国人はくだけた日本語の方が得意だったりするので、一概に「〜です」「〜ます」調が良いとは言えません。「そういう人もいるんだ」という気持ちで読んでいただけたら嬉しいな、と思います。
良いところ悪いところいろいろありますが、覚えることもそこまでないですし、外国の方と日本語で話す時には少し気にしてみてはどうでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
