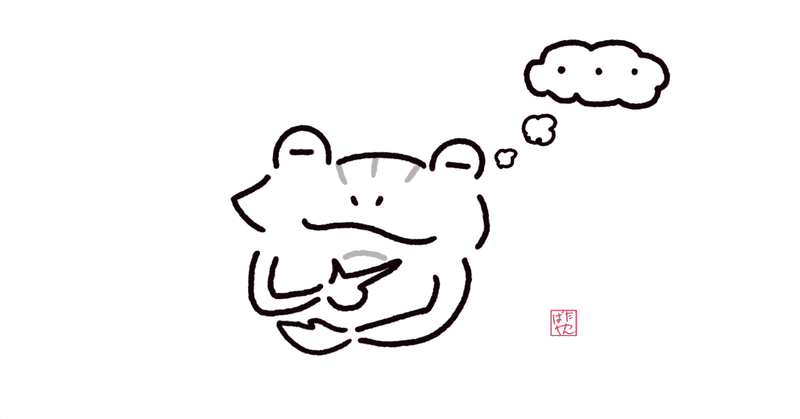
【アート】美術品の価値って何で決まるの?独断と偏見で解説。7つの重要な登場人物。
価値が決まるための登場人物は7つ!
まず先に紹介させていただきますと下記7名の登場人物によってアートの価値が形成されている、と考えております。
アーティスト
ギャラリー(プライマリー)
コレクター
批評家
ミュージアム
オークションハウス
ギャラリー(セカンダリー)
異論はあるかと思いますが、アートの世界に身を置かせていただいている立場からすると上記7名によって市場価値が決まり、新人作家がデビューしてから出会う(関係してくる)順で記載しております。
詳しく紹介させていただきます。
①アーティスト
名も無き古美術やアンティーク品を除くと、すべての始まりです。
個人的には最も尊敬しています。この人たちがいなければ私がアートに関わる機会がなかったでしょう。
多くのアーティストが命を燃やしながら作品を生み出しています。
ただ、そのような作品も人の目に留まらなくては価値は見出されません。現在はSNSなどで個人で発信できるプラットフォームなど充実してきましたが、制作活動で手いっぱいの作家さんにとっては情報を発信する事に時間を取れない方も多く、そもそも情報発信の専門家ではありません。
【良い作品を多くの人に知ってもらう】という役割を担っているのが、次に業界する【ギャラリー(プライマリー)】です。
②ギャラリー(プライマリー)
ギャラリー以外の呼び名ですと画廊と言われたりします。
画廊やギャラリーという名称はどのような仕事かイメージ付きやすい人が多いと思います。しかしながら、【プライマリー】とは何ぞや?という方も多いと思いますので簡単に解説させていただきます。
画商には大きく分けて【プライマリー】と【セカンダリー】とで大別されております。
前者は作家から直接作品を預かる若しくは買取して販売します。いわゆる新品です。
一方、セカンダリーは一度市場に出回った作品を取り扱う画廊です。なので仕入先が作家本人ではなくコレクターやオークションなどとなります。
基本的に亡くなった作家を扱う場合はセカンダリーになりますが、生きている作家も扱っている画廊も多いです。
今回は作家と直接取引をするプライマリーギャラリーの解説です。
アーティストが世に出るための第一歩がギャラリーとの契約と言っても過言ではありません。
アーティストの数よりもギャラリーは圧倒的に数が少ないため、アーティストは目を引く実績(○○賞受賞、大学での実績、SNSでの評価、トレンドに合う画風かなど・・)が無いと取り扱ってもらうことが難しいです。
厳密に言うとスポットで展覧会に呼ばれたりすることはありますが、ギャラリーの所属アーティストになるためには大きな山をいくつも超える必要があります。
ただ、ギャラリーに所属しても一定の市場価値が付くには多くの関門があります・・
つまり、作品に値札が付く以上は買ってくれる人が必要となります。
そう、【コレクター】です。
③コレクター
ギャラリーに所属できる時点で既に複数のコレクターが付いているケースもありますが、多くのアーテイストはギャラリーに所属してからがスタートでしょう。いかにコレクターを増やしていくかが肝です。
ZOZOの前〇さんみたいなメガコレクターが一人ついてしまえば、ある程度市場価値の上昇は見込めますが、最初からそのようなコレクターは付きません。
まずは多くの人に手が届きやすい価格からスタートして、コレクターの反応を見て徐々に金額を上げていくのが一般的です。
号2~3万円程度からスタートして、コレクターが増えたタイミングで金額を上げていきます。この辺りの手腕がギャラリーの力の見せ所ではないでしょうか。
コレクターにもいろんな種類がいて、若手作家ばかり買う方、ある程度市場価値が固まった作家ばかり買う方、オークションでしか買わない方、いろいろいます。
日本独特の文化ですがデパートもギャラリーのひとつと言っても良いかもしれません。バブル期に比べると勢いは弱くなっているように見えますが、まだまだ影響力はあります。デパートで作品を発表できると作家の格もあがるでしょう。
コレクターの悩みとして、作家とギャラリーの話だけだですと客観的に価値を判断しにくく、その結果第三者の意見が気になってきます。
値段が上がる過程で【この作品を買っても良い根拠は?】という問いが出てきます。
この問題を解決するのが【批評家】となります。
④批評家
批評家とは、簡単に言うと雑誌やウェブメディアなどで作家や作品に対しての感想を書く方です。いわゆる利害関係が無い第三者の専門的な意見なので非常に参考になります。
批評家にも様々で影響力がある方からそうではない方までいます。
私の様なnoteは影響力はないので参考程度に見てください。。
影響力とは、有名な雑誌に寄稿している、○○大学で研究している、本を出版している、美術館とのつながりがある等様々あります。
つまり、実績の有無が重要となります。
影響力がある批評家から評価される事によってマーケットからの反応も良くなり、市場価値はどんどん上がっていくでしょう。しかしながら、アートの価値を固めるためにはまだ弱い部分があります。
次は価値を永続的に守られる権威の象徴、【美術館】です。
➄美術館
美術館に収蔵されるとその作家に対して見る目が変わりませんか?
美術館は国や市町村が運営している所も多く、権威性があります。いわゆる美術版の社会的インフラのような役割を果たしています。
ただ、美術館は非常に多いです。下記参照すると全国で452施設もあります。
文部科学省が3年おきに実施している『社会教育調査』(平成23年度)によると、美術館(美術博物館)は452施設となっています。
そのため、どこの美術館に収蔵されているかによって権威性は変わってきます。私設美術館より国立美術館の方が収蔵されるハードルは格段に高いです。
ここでハードルを越えれるかどうかはマーケットだけではなく批評家からの反応もポイントになります。
美術館にも収蔵され、市場価値も権威性もついてきました。ただ、プライマリーで購入した作品をコレクターが手放した後も同様の評価になるでしょうか?
次は【オークションハウス】の出番です。
⑥オークションハウス
基本的には作家から直接出品される事はなく、個人のコレクターなどが手放す際に使われます。ダミアン・ハーストみたいな例外もありますが・・
2008年にはサザビーズがロンドンで開催したオークションにて、223点の作品を出品したところ、落札総額が1億1100万ポンド(約211億円)に達し、1人の芸術家の作品落札総額として当時の最高記録を樹立した。このオークションで、ギャラリーやディーラーなどを通さず直接オークションに出品するという美術界では前例のない行動をとり話題となった。
オークションは二次流通での市場価値がリアルに見えてきます。
例えばプライマリーで100万円の価格が付いていたとしてもオークションでは数万円で落札される事も珍しくありません。
一般的にはプライマリーで購入できなような人気作家はオークションで高くなる傾向で、いくら販売価格が高かったとしてもお金を出せば購入できてしまう作家は厳しい金額になるでしょう。
良くも悪くもオークションでの落札価格が作家のリアルな市場評価になります。
ちなみにオークションでは生きている作家や亡くなっている作家という区別は関係なく、ある程度【市場価値】があるかどうかがポイントになります。
オークションハウスと言えば【クリスティーズ】や【サザビーズ】の様な名前を思い出すかもしれません。このような世界トップクラスのオークションに出品できるようになれば市場価値が確立されたといっても過言ではありません。
しかしながら、日本人作家の多くは上記オークションでは出品できません。文化勲章や人間国宝レベルの作家でも難しく、世界的にコレクターがいるかどうかが重要となります。
そのため、目指すべきは国内のオークションでしょう。国内のオークションですとある程度実績があれば出品可能です。まだ市場価値が低い作家は落札予想価格(個人コレクターでも買いやすいような目安の数字)も安価です。プライマリーと同じ考え方ですが、最初は安くても需要があれば落札金額も高くなります。落札金額が当初の落札予想価格よりも高い状態が続くとオークション側も落札予想価格を上げていきます。
冒頭で述べたようにオークションでしか作品を購入しないコレクターもいますので、コレクターの裾野を広げる点でも非常に有効な場所となります。
ただ、作品を手放す際はオークションしか選択肢はないのでしょうか?
既に亡くなった作家を購入するためにはオークションだけでしょうか?
作品を後世に残す役割を担っている存在として【ギャラリー(セカンダリー)】の出番となります。
⑦ギャラリー(セカンダリー)
オークションで出品できるほどの市場価値がある作家に関してはギャラリー(セカンダリー)で再販されます。冒頭でもお伝えしましたが既に亡くなった作家は基本的にセカンダリーギャラリーがマーケットに送り出す役割を担っています。
基本的にプライマリーよりもセカンダリーの方が高価格帯の作品が多く、数十万~数千万円、中には1億を超える事もあります。市場評価が定まっている作家がメインなのがプライマリーよりも高い価格帯になる理由です。
セカンダリーの役割としては【作品の再流通】と【市場価値の担保】となります。オークションも同じような構造に見えるかもしれませんが、ギャラリーはオークションほど市場評価がダイレクトに価格に反映されません。
オークションは市場原理がダイレクトに反映されていると思いきや、タイミング(コレクターの不参加、景気、自然災害、トレンドなど)により相場よりも下回る状況もあります。主要なコレクターが一人体調不良で参加しないだけでも落札金額が大きく変わります。
直近に自然災害が起こってしまうとオークションどころではなかったりします。
また、オークション参加者同士がヒートアップして過剰な金額で落札されてしまう側面もあります。
オークションは良くも悪くも様々な要因によって左右されるデリケートな場所で予期せぬことに弱いです。
そのような不安定な場所から守る存在としてセカンダリーが必要です。
ギャラリーによって自由に値付けができ、価値ある作品の場合は安く売る事も無く、結果的に作家の価値が守られます。ギャラリーが経営破綻してしまったらもともこうも無いですが・・
作品の価値は上がり続けるだけではなく、いつか下がるタイミングも来ます。その際に下がるスピードを弱めたり、再度価値を上げる事ができる存在となります。
アートや美術品は螺旋階段みたいに段階的に上がる
現実は上記の流れみたいにキレイに市場価値が上がっていくことは少ないかもしれません。美術館に収蔵されるタイミングは前後する事もあります。ギャラリーと契約する前から賞を受賞してコレクションの一部に収蔵される事もあります。一方、ゴッホのように亡くなった後に再評価されて収蔵される事もあるでしょう。
プライマリーギャラリーからセカンダリーギャラリーに至るためには1~2年で達成する方もいますし、達成せずに引退してしまう方もいます。
時代背景やトレンドによって日の目を見ることができない作家も多く存在します。
アートコレクターが増えたら嬉しい
作家がアートを作成するにはお金も重要です。お金の問題で作家活動を辞めてしまう方も多いです。一部の人しかアートを生み出せない世の中は面白くないため、評価されている作家は安定して対価を受け取れるような未来が理想です。
ただ、コレクターにアートは嗜好品で資産価値があるのはごく僅かと伝えて買ってくれる人は少ないでしょう。
コレクターが増えるためには美術品全般の資産価値を安定させる事が求められております。みなさんどう思われるでしょうか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
