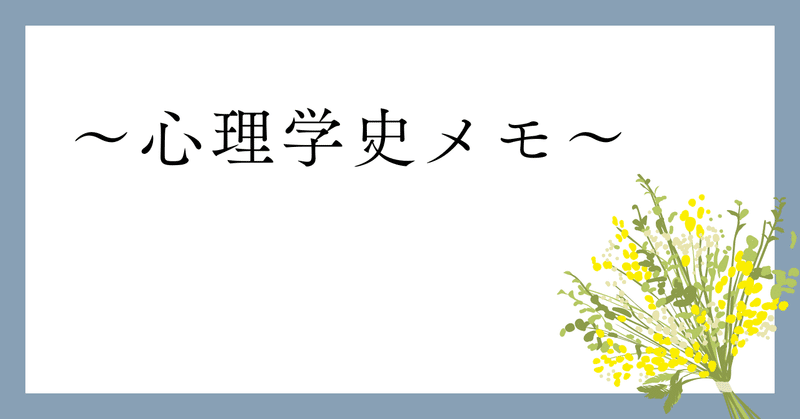
~心理学史メモ~
心理学史についてまとめたいので、どんどん追記していきたいと思います。心理学生にしか需要のないnoteです。
なお、今のところは神経・生理心理学の教科書を参考にしています。なので、現在では神経・生理心理学の歴史範囲+自分が知っている範囲での補足しか記載していません。
後々、いろいろと追記していく予定です。(心理学史の本を手配中)
ごちゃごちゃしてきたら、分野ごとに分けていくかもしれません!気が向けば、図を入れることも考えています。
完全にメモ帳替わりですが、需要があれば参考にしてください。
基本的に教科書に倣ってはいますが、自分で調べたりもしているので、もし間違っているところがあれば教えていただけると非常にうれし~です。
よろしくお願いします!
心理学=psychology
psychologyの語源=ギリシア語の魂(psyche)と理学(logos)が由来。
紀元前5~4世紀のギリシャ時代にヒポクラテス(Hippocrates)が登場。
⇒脳が善悪の判断や感情をつかさどる「知能の座」であると述べた。
※著書に「ヒポクラテスの誓い」があり、医学倫理について言及している。医学の父と呼ばれている。
プラトン(Platon)の弟子であるアリストテレス(Aristoteles)は、「心の座」が心臓にあると述べた。
脳は血液を冷やすための装置であり、心ではないと主張した。
ローマ時代に入り1世紀前半に活躍したギリシャ人の医師ガレノス(Glaudius,G.)は、脳は運動と感覚の中枢であると考察した。
17世紀~19世紀は「理性主義」VS「経験主義」の時代
理性主義の方たち:
スピノザ(1632年 - 1677年)
オランダの哲学者
神と自然を同一視する汎神論を唱えた
代表作:『エチカ』
ライプニッツ(1646年 - 1716年)
ドイツの哲学者・数学者・科学者
モナド論を唱えた
代表作:『新しき方法論』
ウォルフ(1679年 - 1754年)
ドイツの哲学者
ライプニッツ哲学を体系的にまとめた
代表作:『自然神学』
パスカル(1623年 - 1662年)
フランスの数学者・哲学者
確率論の研究で知られる
代表作:『パンセ』
経験主義の方たち:
フランシス・ベーコン(1561年 - 1626年)
イギリスの哲学者・政治家・科学者
科学的方法の重要性を主張し、経験に基づいた知識の獲得を提唱した。
代表作:『新論』、『オルガンム・ノヴム』
トマス・ホッブズ(1588年 - 1679年)
イギリスの哲学者
人間は生まれつき何も持っておらず、すべてを経験を通して学ぶとした。
代表作:『リヴァイアサン』、『要素論』
ジョン・ロック(1632年 - 1704年)
イギリスの哲学者・政治思想家
経験論の父と呼ばれる
人間は生まれた時は白紙の状態 (タブラ・ラサ) であり、経験によって知識が書き込まれるとした。
代表作:『人間悟性論』
ジョージ・バークリー(1685年 - 1753年)
アイルランドの哲学者・神学者
存在は知覚されることであるとした観念論を唱えた。
代表作:『認識新論』
デイヴィッド・ヒューム(1711年 - 1776年)
イギリスの哲学者・歴史家
因果関係の存在を否定し、経験に基づく懐疑論を唱えた。
代表作:『人間本性に関する研究』
近世17世紀に入り、フランスの哲学者デカルト(Descartes,R.)が心身二元論を提唱した。※心身二元論とは、脳は物質であり、精神と肉体は別個であるという考え。「心の座」は松果体であると述べた。
18世紀(後半)になるとガル(Gall,F.J)が頭蓋の形と人の特徴の関係を言及した。これが脳の局在説の先駆けとなった。
19世紀中盤のドイツでは、J,ミュラーを中心として実験的な感覚生理学が進むようになる。ミュラーは生理学的実験を行いながらも、生命現象は物理化学的過程に還元するものではないとする生気論の立場を取る。⇒弟子が異を唱えた。
その中の4人の生理学者(デュ・ボワ=レイモン、ルツ、ルートヴィッヒ、ブリュッケ)は唯物論の立場を取った。
19世紀後半、ブローカ(Broca,P)が脳の局在説を強く支持。言葉を理解できるが発語できない患者を診断し、発語中枢を発見した。発語に関わる領域として、ブローカ野と名付けられている。
※補足:言語理解をつかさどるのはウェルニッケ野
同じころに、米国の鉄道建築技術者であるフィニアス・ゲージ(Phineas P Gage)が工事中に受けた事故により、前頭葉の大部分を欠損した。人柄がよく好かれる人物だったが、前頭葉の欠損により感情の制御ができなくなった。医学に大きな影響を与えた症例である。
1879年に、ヴントの心理学実験室でゼミナールが開講された。
19世紀から20世紀にかけて、ゴルジ(Golgi,C)とカハール(Cajal,R.Y)が脳の神経細胞について論争を繰り広げた。
ゴルジは独自で考察したゴルジ染色法を用いて、脳組織を観察。神経細胞が互いに隙間を持たず、つながった状態でネットワークを形成していると主張。
※細胞の中にある器官(ゴルジ装置)を発見した人物でもある。
一方カハールは、個々の神経細胞は接触しているもののわずかな隙間があると主張した。
⇒今では、神経細胞が互いに隙間を持ったシナプスとして結合し、ネットワークを形成していることが明らかになっている。
記事は気に入っていただけましたか?メッセージ付きでサポートいただけたら、とってもうれしいです(*^^*)
