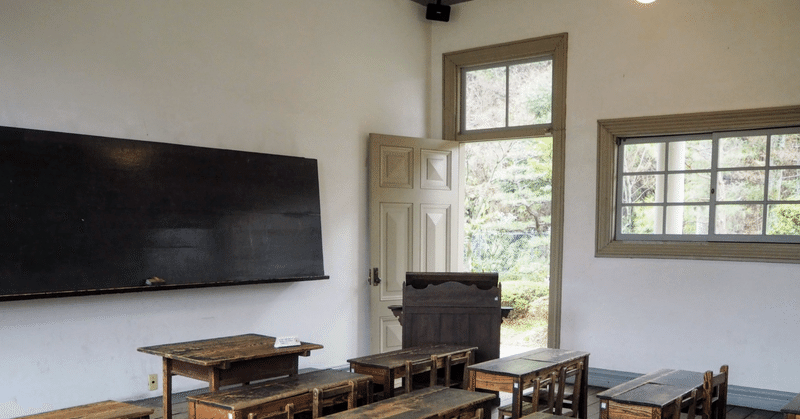
【読書感想文】だれでもデザイン 未来を作る教室
Twitter でフォローしている山中俊治(やまなか・しゅんじ)さんが執筆されたデザインに関する本を読んでみた。
構成としては、2017年に高校生に行った4日間の特別授業を書籍化したもので(こんな講義を受講できる高校生羨ましい!!)、デザインの定義からスケッチ手法、アイディアの発案方法から育て方まで幅広い講義内容である。
目次は以下の通りで、印象に残った章について感想を書いておく。
はじめに
1章 デザインって、なに?
2章 言葉としてのスケッチ
3章 「っぽい」リアルさを描く
4章 分解と観察スケッチで「作り方」をたどる
5章 アイデアのヒントは観察の中に、他人の頭の中に
6章 使いやすいものを作る
7章 なにを、どうして作るのか
8章 形にして、共感を集めて、アイデアを育てる
おわりに
1章 デザインって、なに?
"デザイン"という言葉の定義は、美術的な側面を扱う作業全般と思っていたのだが、語源である英語のデザイン(Design)では、美術的な側面と技術的な側面を併せ持った考え方であること。日本語として輸入した時の経緯によって、日本では技術的な側面を担当する『設計』と、美術的な側面を担当する『デザイン』が明確に分けられているが、その中間(設計もデザインも学ぶ)もあってもいいんじゃないかという話が非常にしっくりきた。
この話はシステム設計(特にフロントエンド)でも同じような話があるんじゃないかと思った。画面構成・フォント・色などを担当するデザイナーと、関数・データ構造などを担当する設計者(プログラマー)を担当者レベルで明確に分離して設計・実装するより、同じ担当者がそれぞれ実施する方が上手くいくことが多い。学習する際もどちらかの領域に限定するより、両方に足を突っ込んで学ぶ方がより多くの学びがあると思う。
それ以外にもアートとサイエンスの探求方法の違いと、その両方を学ぶことの重要性についても述べられており、この1章を読むだけで、この本を買った価値はあり。
4章 分解と観察スケッチで「作り方」をたどる
日用品を形を決定する3つの要素のち、3つ目の作り方(製造技術概論)が色々と勉強になる。
1. 機能 (工学的機能/心理的機能/社会的機能)
2.構造
3.作り方(製造方法)
たかがネジ、されどネジというか、普段全く意識しないネジの傾き・入り方にもこだわりがあるんだよという話が面白い。この章を読んだ後に、身の回りの家電の構造や、ネジの入り方をちょっと観察するとなお良し。
あと美術が苦手な私は2章と3章(スケッチの基礎講座的な章)を読み飛ばしてしまったのだが、4章と関連しているので2章・3章を読むともっと深い知見を得られるかもしれない。。
6章 使いやすいものを作る
Suica 改札機や内部被曝検査用機器の開発秘話、どのような経緯で設計・開発・改善・実装されていったのか実際の事例が紹介されている。
それぞれの事例を読んで、何かの課題に対する解決策を検討する際には、課題→アイデアの着想・発散→前提や制約事項による収束→実装と観察→改善という基本的なプロセスが重要ということを改めて認識した。
一般的にデザインという言葉は、アイデア勝負でふと頭に降りてきた瞬間が勝負なイメージがあるのだが、実際にはそのアイデアが実装されて社会に出る前には、様々な制約(資金・製造・技術など)があり、折り合いをつけながら、試行錯誤しながら良いものを生み出すことが重要だよと言っている章。
8章 形にして、共感を集めて、アイデアを育てる
この章で説明されているプロトタイプを作ってアイデアを育てていく作業は、そのまんまソフトウェアのサービス設計に適用できる作業だと思う。
(1~3は少し順序は異なると思うが)
作る(身近な素材で) → Mock で作成してみる
作り方・売り方を考える(加工方法、ネーミング)→ ビジネスモデルを考える
小芝居する(使用状況を演じてみる)→ 想定顧客の利用方法を考える。
知らない人に使ってもらう(その様子を観察する)→ プロダクトデモを行う
1.に戻る
デザイン思考(デザインシンキング)が事業企画やプロダクト設計に用いられることもあるし、このあたりの考え方はすんなりと頭に入ってきた。
最後に8章から至言を抜粋して終わりたい。
僕もデザイナーとして、様々なアイデアを生み出してきました。この授業ではこんな面白いものを作ったとか、8千万人が使っているとドヤ顔で話しましたけど、受けなかったアイデアの方がはるかに多くて、死屍累々です。どれも最高にヒットすると思って提案しているから、いちいちショックを受ける。もうそれは仕方がない。
〜中略〜
自分のアイデアが人前に晒されること。その評価を、まずはきちんと受け入れましょう。嬉しくても辛くても、なにが評価され、なにが共感されなかったのかを理解することが、次につながります。
P.344
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
