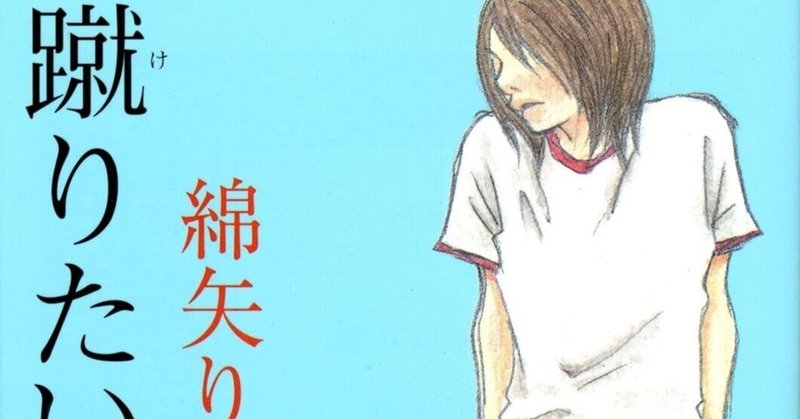
【読書メモ】今週読んだ6冊
『86-エイティシックス-』2巻 3巻 安里 アサト

共和国の指揮官(ハンドラー)・レーナとの非業の別れの後、隣国ギアーデ連邦へとたどり着いたシンたち〈エイティシックス〉の面々は、ギアーデ連邦軍に保護され、一時の平穏を得る。だが――彼らは戦場に戻ることを選んだ。連邦軍に志願し、再び地獄の最前線へと立った彼らは、『隣国からやってきた戦闘狂』と陰で囁かれながらも、シンの“能力”によって予見された〈レギオン〉の大攻勢に向けて戦い続ける。そしてその傍らには、彼らよりさらに若い、年端もいかぬ少女であり、新たな仲間である「フレデリカ・ローゼンフォルト」の姿もあった。少年たちは、そして幼き少女はなぜ戦うのか。そして迫りくる〈レギオン〉の脅威を退ける術とは、果たして――? シンとレーナの別れから、奇跡の邂逅へと至るまでの物語を描く、〈ギアーデ連邦編〉前編! “――死神は、居るべき場所へと呼ばれる”
・少年少女が多脚戦車に乗って戦う男女物ラノベ。2巻と3巻で上・下となっていたのでまとめて読んだ。
・1巻では捨て駒として母国に使いつぶされてきた主人公たち少年兵。2巻では母国よりマシな国に保護されて、ひとときの平和な日常を得る。だけど戦場で生まれ育った主人公たちは、戦うことでしか生きられない。だから一度は与えられた平和を捨てて再び戦場に戻る。という展開となる2冊。フィクションに対してノンフィクションの話を持ち出すのもナンだけど、先週読んだ『戦争は女の顔をしていない』でも一度戦争の日常を経験した元兵士が平和な日常に戻ることの大変さを語るシーンがあった気がする。また、ベトナム戦争帰りの元アメリカ兵が、近所の子供が水たまりで跳ねる水音を湿地帯での敵襲の音と思い、反射的に子供を殺してしまった話も以前読んだことがある。「一度戦場を知った人間が日常に戻ることは難しい」というのはフィクションでも現実でもよく聞く。
・戦闘シーンが2割、会話シーンなどの人間ドラマが8割ぐらいの構成。実際、戦争物といってもずっと戦闘しているだけではダレるし、これくらいの割合が丁度いいのかも。ドンパチだけが戦争じゃないし、そもそも戦闘シーンって難しいし、それが多脚戦車というなんともイメージしにくいシロモノならなおさら。
・主人公が生に執着が無さすぎるので、好みは読者によって分かれそう。ラノベって「主人公に感情移入できるか」が大事なんでしょう? 私は感情移入とか考えないタイプなのでよく分からんけど。
『闇の守り人』上橋 菜穂子

女用心棒バルサは、25年ぶりに生まれ故郷に戻ってきた。おのれの人生のすべてを捨てて自分を守り育ててくれた、養父ジグロの汚名を晴らすために。短槍に刻まれた模様を頼りに、雪の峰々の底に広がる洞窟を抜けていく彼女を出迎えたのは――。バルサの帰郷は、山国の底に潜んでいた闇を目覚めさせる。壮大なスケールで語られる魂の物語。読む者の心を深く揺さぶるシリーズ第2弾。
・アニメにもなった『精霊の守り人』シリーズ。
・達観した強キャラ中年女性が主人公なのが嬉しい。でもなんかヘテロフラグが立っているのよね。
・「氏族長の血を引いた男しか倒せない」とされていた怪物を主人公の女性が撃退したことで、血統主義とジェンダーを同時にブッ飛ばす展開が読んでいて気持ちよかった。
・蒼い鉱石が闇に溶けていくようなラストシーンの描写が幻想的で美しく感じた。ファンタジーってやっぱり夢のある情景描写が大事よな。
・短槍というちょっと特殊な武器を主人公たちが扱うのが独特な設定に感じた。シンプルに剣やナイフのほうが読者はイメージしやすいんじゃないかと思ったけど、本作の端的かつ分かりやすい描写のおかげで「短めの槍」がすぐに頭に浮かんだ。作者の描写力の勝利。主人公に特殊な武器を持たせる場合は作者の筆力が試される。
『蹴りたい背中』綿矢 りさ

第130回芥川賞受賞作品。高校に入ったばかりの“にな川”と“ハツ”はクラスの余り者同士。やがてハツは、あるアイドルに夢中の蜷川の存在が気になってゆく……いびつな友情? それとも臆病な恋!? 不器用さゆえに孤独な二人の関係を描く、待望の文藝賞受賞第一作。
・いまでいう「ぼっち」同士の男女の不思議な関係を描く男女物小説。
・芥川賞には堅苦しいイメージを勝手に抱いていたが、語り口は高校生主人公らしくいたって軽い。
・「他人の家」の解像度が高い。色褪せたふすま、古雑誌の詰まれた庭、椅子の背もたれに干されたバスタオル、鰹節みたいな生々しい冷気が出るエアコン。
・社会性の無い女性とダメ男の組み合わせ。いままで芥川賞受賞作は『コンビニ人間』『ハンチバック』と読んできたけど、みんなこの組み合わせだった(『ハンチバック』は社会性を持つことができなかったと言えるが)。芥川賞の傾向が分かるような分からんような。
・目が印象的に描かれる。主人公の鋭い目と、にな川の昏い停電した目。対照的な目を持つ二人は、そのままキャラ造形の差異を表しているのかも。
・思春期の子供の複雑な感情を描いた作品・・・、と思ったが、いくら思春期でもクラスメイトの背中をいきなり蹴る真似はしないだろう。おそらく。
・女性モデルの追っかけをしているにな川。彼女が出ているファッション雑誌は全て購入し、着けている香水も入手して部屋に仕舞い込んでいる。挙句の果てにはアイコラ(有名人の顔をヌード画像と合成する迷惑系エロ画像)を自作する気持ち悪さを見せるが、主人公はそんなにな川に対して「蹴りたい、愛おしい」と思うようになる。なぜ。どんな感情。
・Twitterの相互さんからいただいた知見だけど、「現実では普通に嫌悪感を覚えるようなシチュエーションなのに、二次元だとなぜだか興奮を覚える。男性向けでNTR、女性向けで乱暴な性行為描写のエロ漫画が好まれるのもそのためかもしれない」という考え方がある。主人公のにな川に対する感情もそれに近いのかもしれない。
『古本食堂』原田 ひ香

美希喜(みきき)は、国文科の学生。本が好きだという想いだけは強いものの、進路に悩んでいた。そんな時、神保町で小さな古書店を営んでいた大叔父の滋郎さんが、独身のまま急逝した。大叔父の妹・珊瑚(さんご)さんが上京して、そのお店を継ぐことに。滋郎さんの元に通っていた美希喜は、いつのまにか珊瑚さんのお手伝いをするようになり……。カレーや中華やお鮨など、神保町の美味しい食と心温まる人情と本の魅力が一杯つまった幸せな物語。
・グルメ系だけどウザいオノマトペとかは無いのでストレスフリーに読める。擬音を用いず文章力だけで美味しそうな食事シーンを描いているのに好感を持った。
・実在の本が物語のキーアイテムとして登場する。だけど作者の読書量をひけらかすような嫌味な感じはない。
・大きな事件は起きず、古書店を継ぐことになった女性の日常を描く。けれども展開の波はしっかりあるので読んでいてダレることはない。
・「展開を引っ張る」ことの大切さを学んだ。大きな事件は一切起こらないけれど、ちょっと気になる「引き」で〆たあと別キャラの別視点の描写のシーンを挟むことで、先を読みたくなる欲求を読者に与える。バラエティ番組のCM前の「このあと衝撃の展開が!」みたいなやつ。ドラマチックな展開が少ない日常系なら特に使えそう。後から読み返すとしょうもない出来事でも、ちゃんとストーリーのメリハリになる。
・登場する料理は実在の飲食店のもの。神保町に行きたくなる一冊。
・ヘテロ(異性愛)要素は薄いながらもある。
☆おすすめ!『安達としまむら』2巻 入間 人間

今まで興味なんかなかった。ないフリをしていた。だれにも、なにもほしがらなかった。だけど今年は違う。私が初めて願うクリスマスプレゼントは、しまむらとのクリスマスだった。 今までなんとなく毎年過ごしていた。強い関心があるわけでもなかった。だけど今年は違う。少し気を遣って、安達へのクリスマスプレゼントを選ばないといけない気がしていた。
・Audibleで再読。朗読の「間」や空気感の作り方が相変わらず上手い。作品の旨みを引き出している。
・安達の愛がもう重い。2巻にして既に。しまむらをクリスマスに一緒に外出するかどうかで延々と悩んだり、メール一つ送るのにもいつまでも躊躇したりと想いが吊り合わない。だけど一方通行ではなく、しまむらからもちゃんと返してくれるのが嬉しい。
・同性愛への禁忌観が強いのは2010年代前半の作品って感じがする。
・ストーリー構成よりもキャラクター同士の掛け合いで魅せるタイプの作品。ファンタジーでも特殊な設定も無い作品の場合はキャラクターの感情や会話や関係性で作品としての面白さを見せつけなければならないので、むしろ作者の手腕が問われる。その結果、上質な百合ラノベが生まれた。
・恋人はおろか友達もいないので、いざ大切な人が出来たら距離感が分からなくてバグる感じの安達が実にリアル。
・ブーメランを投げる描写がいやに臨場感ある。ブーメラン描写の教科書にできるよこれ。
・「女だけで盛り上がれるイベントが無い」は本当に”それな・・・”ってなった。クリスマスもバレンタインデーも基本は男女のものとされている。女と女のための日は無い。いっそのこと、たとえばひな祭りを何とかして「女の子同士で遊んだりイチャイチャする日」に出来ないだろうか。ハロウィンが若者たちがバカ騒ぎする日になったんだし、不可能ではないと思う。うん。
・「しまむら ジムへ行く」で登場するロリコン男は同作者の『花咲太郎シリーズ』の主人公・花咲太郎のカメオ出演であり、この後は二度と登場しません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
