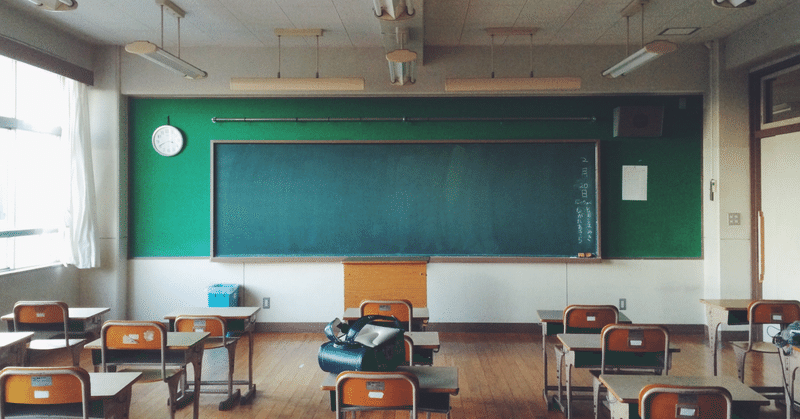
学級崩壊の90%はこれが原因です。
学級崩壊が起こる大きな原因は一つだけです。私は20年ほど前からそう思い続けています。
巷では、社会の変化、発達障がいのある子が増えたこと、家庭のしつけ力の低下など、いろいろな原因が述べられがちです。
しかしそれらは学級崩壊の本質的な理由ではないです。
学級崩壊の原因は、学級崩壊が起こるクラスの担任教員の力量不足です。
これは、特に子どもの年齢が低い学校で当てはまります。例えば高校生くらいになると、一部の高校では、反社会的な団体と繋がりをもっている生徒がいます。そのような生徒が複数いる学級は、教員が頑張ってもなかなか難しいところがあります。
でも小学校はそうではありません。小学生は人格や性格の形成の途上です。そして外の世界をいろいろ知っている高校生とは違い、学校が小学生の生活の中心です。だから教員の関わり方や、学級運営によって子どもの様子は大きく変わります。
教員のどのような関わり方が学級崩壊を招くのか。それは小言が多い教員の関わり方です。例えば子どもがちょっと騒がしい時に「あーもう、うるさい、少しは静かにできないの」などとすぐに思ったことを口に出してしまう教員がいます。
この小言で子どもたちが静かになれば問題はありません。でも、小言程度のことでは子どもたちは素直に言うことを聞かない方が普通です。そして小言が多い教員は、思ったことがつい口に出ただけで、すぐに子どもたちが静かにならなくてもそんなに気にしません。
そして、この教員の言うことを聞かないで済んだという経験が学級崩壊に繋がっていくのです。
小言が多い教員はその時々で気になったことをつい口にしてしまいます。
こうした小言が多いタイプの教員は「早くしなさい」「片付けなさい」「ちゃんと並びなさい」など常に小言を繰り返しています。
しかし言うだけで満足してしまうので、その発言の後に子どもが、早くできたのか、片付けたのか、ちゃんと並び直したのか、という結果まで確認しないのです。これが子どもたちにとって教員の言うことを聞かないで済んだという経験を積み重ねることになります。
そしてそうなれば当然、その教員の言葉は軽くなります。本気で静かにさせなければいけない場面でも、普段からその教員の言うことを聞かなくても済んでいる環境で過ごしている子どもたちは、「静かにして!」という言葉は軽いものなので、素直に従うことはないです。
教員の言葉に従わない雰囲気が醸造されると学級崩壊が起こります。教員の言葉が子どもに伝わらなければ、学級の統制が取れるはずありません。
こうならないためにどうすればいいのかと言うと、教員が言葉を発する時は責任をもたなければいけないということです。
自分の中でしっかりとルールを決めて、例えば休み時間は多少はめを外しても何も言わない。ただし授業中は少しでも騒がしくなったら「静かにしましょう」と言う。そして言ったからには静かになるまで、授業を進めない。
他の例をだすなら、教員が「姿勢を正して座りましょう」と言ったら全員ができるまで帰りの会を始めないなどということです。
教員は自分が発した言葉に責任をもたなければいけません。教員の言葉を重たいものにすることが学級崩壊を防ぎます。
教員が普段からごちゃごちゃ言わなくても、大事な場面でしっかりと教員の言葉に従ってみんなで動いた、という経験が積み重なれば学級崩壊は起きません。
そして教員の言葉を重たくするために子どもとの約束は必ず覚えていて、絶対に守る、というようなことも必要です。
例えば、「学期末にお楽しみ会をしよう」と一度言ってしまったら、他の学級よりどんなに授業の進み具合が遅れていてもお楽しみ会を中止にしてはいけません。約束を守らなければ、教員の言葉が一気に軽くなります。
教員が発した言葉は絶対に実現する、ということが普通になれば絶対に学級崩壊は起きません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
