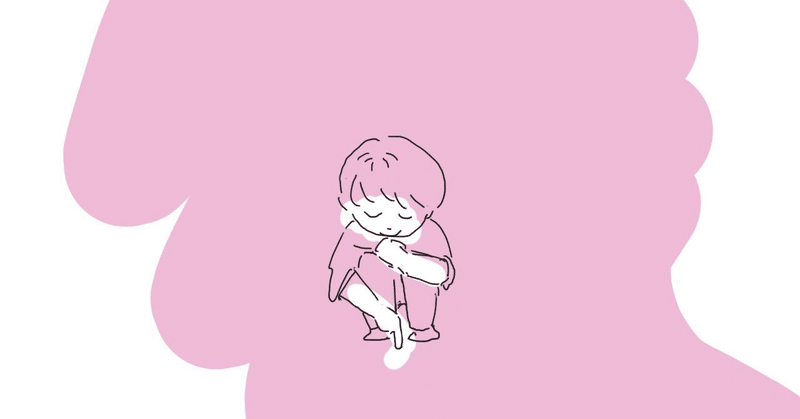
息子は保育園から帰りたくない。
頭では分かっていてもなかなか気持ちが追いつかないことが世の中にはある。太ると分かっていてもおやつがやめられない、早起きすれば得が三文あることは分かっているが、布団から出られないなど人それぞれいろいろあると思う。
また、自分がそうでないことについて、頭では分かっていても理解できないこともある。
私は超絶お子ちゃま舌なので、いまだにコーヒーが飲めない。スタバに足を踏み入れたことすらないほどである。私は世の中にコーヒーを愛飲する人が数多く存在することは知っているが、正直毎日何で飲むんだろう?という気持ちである。
逆に私はお子ちゃま舌と言っておきながら、お酒は毎日飲む。すごく飲む。
私の母はコーヒーをかなり飲むがお酒は飲まず、居酒屋に行ったことが人生で一度もないらしい。
だから飲み物関係については親子とはいえお互いに相いれず全く話が合わない。
このように立場の違う相手がいることは理解していながらも、自分はそうではないので心情が理解できないということが世の中にはよくあるように思う。
そしてそのようなことがまさに昨日起こったのでここに書き記して記憶に留めたいと思った次第である。
それは昨日の夕方、埼玉県のとある保育園で起こった出来事である。私はいつも通り、5歳娘と3歳息子を迎えに行こうと保育園まで馳せ参じた。
そして保育園の玄関口で我が子の名前を呼びかけた。5歳娘はその声を聞くや否や駆けてきて私に飛びつく。毎日繰り返される心が温まる光景である。
しかしここで私は異変に気が付いた。息子が出てこないのだ。
何度か名前を呼びかけて待っていると、しばらくして息子が渋々といった様子でお部屋から出てきた。
ドラえもんの塗り絵を手にして不機嫌顔だ。そして私にこう言った。
「もっとやりたかった…」「もっと塗り絵するの…」
私はこれを聞いた時に言葉を失った。
これが俗に言う園から帰りたくない子だ。
私もその存在は風の噂には聞いていた。
園から帰りたがらず、まだ遊んでいたいと保護者を困らせる子どもがいるということを。
しかしまさか我が子がそうなるとは。
これは私にとっては天を仰ぎ見るほどの出来事である。
そもそも私は幼稚園児のころ、幼稚園にいる時間において何を考えていたか。
それはただ一つのみで、「一刻も早く帰宅したい」ということであった。朝からひたすら帰宅できる時間がくるのをいまや遅しと待っていた。
幼稚園児の私は幼稚園にいる間中ずっと、帰宅という唯一にして最大の目標に向かって邁進していたのだ。
幼稚園で営まれるお遊戯や体操や製作などの活動はすべて苦痛であったが、これも帰宅するための通過儀礼だと思えばなんとか耐えることができた。
そしてどうにかこうにか園での活動をやり過ごし帰宅の時間である。
家に帰る幼稚園バスに乗っている時は、世の中にある幸福をすべてかき集めて、身に纏っているような感覚すらあった。
私は幼稚園で困難を耐え忍べば、その後に必ず福音があるということを学んだ。
そんな帰宅原理主義の私の息子が、まさか園から帰りたがらない子になるとは。
娘は保育園は楽しいが、帰れるには越したことはないと考えているようで、これまでの保育園人生において帰宅を渋ったことはない。
だから私にとって帰宅を渋るという状況を目にするのは、はじめてである。驚き、困惑、不安、動揺、どの言葉を当て嵌めても正しくないような不思議な感覚に陥った。
息子には塗り絵は家でも遂行可能という旨を伝えて、なんとか帰宅することについて了承を取り付けた。ただ、自転車に乗せて帰宅している最中も「もっとやりたかったのに」と不平不満の気持ちを隠し果せない様子であった。
子どもは親の相似形のように育つわけではないことを私は実感した。
また、それと同時にとても重大なことにも気付かされた。
それは自分と信念や信条が違う人と相対し、まさにその信念や信条の違いに直面した時の心の持ちようだ。
私は子どもの頃、園から一刻も早く帰りたかった、息子は園から帰りたくないという。
私と息子は園からの帰宅という点についての信念や信条を全く異にしてしいる。それは相反する信念や信条である。
昨日の夕方、私と息子の信念や信条がぶつかりあい、そこに葛藤がうまれた。
その葛藤から私はいわく言い難い複雑な感情を抱いてしまった。しかしこの葛藤を克服すること、またはこれを葛藤と思わないことが必要なのだと沈思黙考して冷静になってから気が付いた。
世の中には信念や信条が違う人は数多いる。そのたびに動揺するのは愚かなことだ。動揺するだけならまだいいが、信念や信条が違うことをネガティブに捉えすぎると、排斥や差別が起こる。
他者が自分と違う信念や信条をもっていても、それを受け止めて認めていく姿勢が大切である。これが多様性を認める社会の基本的なありようであると私は考えている。
息子の帰宅渋りから私は学び、多様性について考えることができた。
息子と私は園から帰りたいか帰りたくないかということについては袂をわかった。
だからといって親子の絆が弱くなる訳ではない。お互いの信念や信条が違うことを知り、それを認め合うことで以前より深い人間関係を築く契機となったのだ。
私には私の信念や信条があるし、息子には息子の信念や信条がある。お互いが個人として尊重しあいながら共に成長していきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
