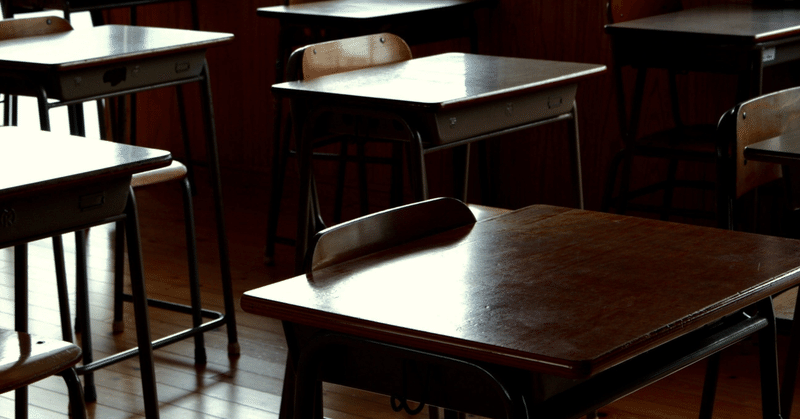
新時代の学校で行われる危ない教育
現在の学校教育では、主体的・対話的で深い学びの実現が求められています。一見するととてもいいことのように感じますが、これは相当な危険性をはらんでいるように、私は感じています。その危険性について、書いていきたいと思います。
数年前に文部科学省が学習指導要領を改訂して、いよいよ学校現場には主体的・対話的で深い学びができるような授業を本格的にしなければいけない、という空気が漂っています。
主体的・対話的で深い学びが実現できれば、素晴らしい学習効果が上がると思います。しかし、私はそれが実現しない場合が多いと思っています。
それはなぜかというと主体的・対話的で深い学びを実現できる教員がほとんどいないからだと思っているからです。だいたいの教員は主体的・対話的で深い学びと言われて戸惑うでしょう。
教員は今までそのような教育をしてきていないし、教員自身もそんな教育は受けてきていません。どうしていいのか分からないのが実情であると思います。
そんな中で主体的・対話的で深い学びと言われて教員が発想するのはどんなことかというと、対話を重視した学びになります。
それも子ども達が主導の「話し合い学習」です。
なぜかというと主体的、深い学びは漠然としていて具体的にどのような学習活動をすればよいか分かりにくいですが、対話的という言葉からは「話し合い学習」という具体的なイメージが起こりやすいからです。
そして私は教員がたどり着く、子ども達主導の「話し合い学習」に危険性を感じています。「話し合い学習」の何が危険かというと、子どもに任せて話し合い学習をすると、クラスで立場の強い子の意見が常に通ってしまうということです。
教員からすれば子ども達主導の「話し合い学習」は、主体的でもあるしいいものじゃないかと思ってしまいます。
でも「話し合い学習」は先生がお気に入りの、先生の意図を汲むのが上手い子どもが自分の意見を正当化してみんなに認めさせる場になりがちです。
子どもが主導の「話し合い学習」について、あまり自分から進んで意見を言わない子どもを巻き込みつつ、深い学びのある方向へ導くのは、実はものすごく教員にとって大変なことです。
教員にとっては悪気はないですが、話が上手な子達がいい意見を出してくれればそれで主体的で対話的な授業になったと思ってしまいがちです。
そしてここで大きな被害者になるのが、話し言葉で表現することが苦手な子ども達です。
私が小学校の頃にいたクラスメートで、全然喋らないし、目立たない女の子がいたのですが、作文をみんなの前で発表すると、驚くほど内容が濃くユーモアにとんだ文章を書いていました。
また、大人しい男の子で勉強や運動が苦手で話も下手でしたが、恐ろしく絵が上手い子もいました。
明るく朗らかではないので、先生からは好かれていませんでしたが、テストは必ず100点という子もいました。
「話し合い学習」が増えるとこのような子たちは必ず埋もれていきます。その才能に気付くことも減っていきます。なぜなら話し合いの時間がどうしても増えるので、作文を書いたり、絵を描いたり、黙々と勉強をする時間が減るからです。
そしてもし作文や絵が素晴らしかったり、テストの点がよくても、「話し合い学習」が重視されているクラスでは評価されにくいので、自分の才能に自信がもてなくなります。
文部科学省もきっと子ども主導の「話し合い学習」が危険性をはらんでいるのは気づいていると思います。平成28年度の中央教育審議会で対話的ということについて「対話の相手は子どもだけでなく、教職員、地域の人、先哲など幅広いものである」と子ども主導である必要がないことを、わざわざ示しています。
現場の教員は主体的・対話的で深い学びを実現せよと言われて戸惑いや困惑があると思います。でも、いつも意見を言う子の意見が通り、話し言葉で表現できない子がおいていかれるような、安易な「話し合い学習」はしないでくださるよう願っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
