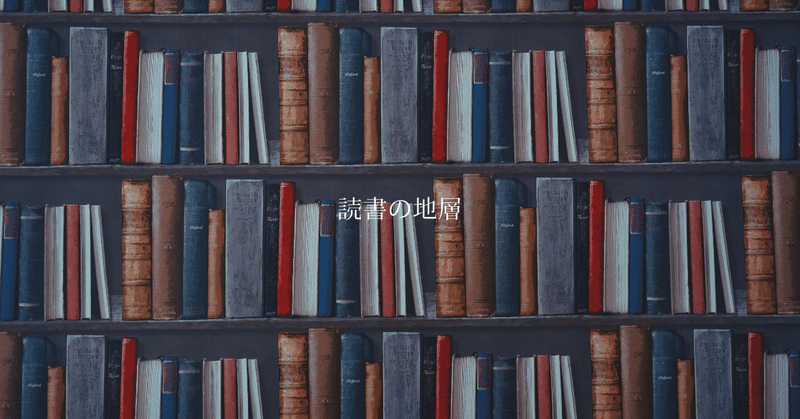
読書の地層
私はよく本を読むほうであると思う。
「趣味は何ですか」と尋ねられた際には「読書ですかねえ」と答えているが、正直、あまり読書を趣味だと思ったことはない。なので、内心ふんわりと嘘をついているようなごまかしているような不思議な気持ちになりつつ、「読書ですかねえ」とお茶を濁しているのだ。
どうして読書を趣味だと思えないのか。それはおそらく、あまりにも幼い頃から「本を読む」という行為をしてきたためにその行為がもうほとんど生活の一部となっているからであると思われる。私の読書体験を遡っていけば、最も古いものは夜寝る前に親にしてもらった絵本の読み聞かせである。主に昔話やお伽噺と呼ばれるものを日本モノ・西洋モノを問わず毎日読んでもらっていた。聞かせてもらっている私だけではなく、読み手である母や父にもそれぞれお気に入りのお話があり、そういうものは「好きこそものの上手なれ」とでも言おうか、特に読み聞かせに熱が入って面白いので頻りに読んでもらったものだ。
小学校には「朝読」という文化があった。朝のホームルームが始まる前の10分間、みんな黙ってただただ本を読む時間が設けられていたのだ。教室には「学級文庫」という教室の誰もが利用できる本が数冊置かれており、やんちゃな男子たちによって争奪戦が繰り広げられていた『かいけつゾロリシリーズ』は表紙がボロボロになっていた。私はほとんど学級文庫を利用せず、自前の本ばかり読んでいたように思う。青い鳥文庫をよく読んでいた記憶はあるのだが、その他には何を読んでいたのだろう。もうあまり覚えていない。名木田恵子さんの本が好きで、図書館で借りたり、新作を買ってもらったりしてよく読んでいた。この頃、初めて「好きな作家」というものができて、母には「もっと他の人のも読んだら」と言われたことを記憶している。
中学生の頃は、たくさん本を読んだ。この頃から「私は本を読むことが人より好きなのだ」と自覚し始め、できるだけたくさん本を読みたいと思い始めた。アニメもたくさん見たし、本もたくさん読んだ時期だ。この頃にインプットしたものは今でも私の好みの根源的な部分に鎮座していると思う。宮沢賢治や湯本香樹実、ヘッセやジッド、ギャリコ、サン=テグジュペリに出会ったのも中学生のときだ。母が本屋で働いていたので色々な本を選んでくれた。この頃の私は自他共に認める「文学少女」であったことは間違いない。部活の顧問にもこう呼ばれていたし。科学部だったけれど。
田舎の中学生だった私にとって、本を読むことが紛れもなく日々の支えになっていた。少し背伸びして読んだ本たち。後にして読み返すと、やはりこのときに読んでいてよかったと感じるものも少なくない。
高校に入ってからは部活部活部活の日々であったが、通学電車や10分休みに文庫本を開いていた。この時点ですでにもう「本を読むのは当たり前」の私になっていたと思う。古い本を多く読み始めた。というのも「まずは基本から押さえておこう」と思い、名作と呼ばれる近現代文学をたくさん読んだわけだ。梶井が好きになったのはこの頃だったかもしれない。
ある日、演劇部顧問の先生と何かの作業をしていた際、A6サイズを図り取らねばならない状況になって「吉野(=私)が文庫本を持っていないはずがない。出して」と言われたことをよく覚えている。なんだか、とても嬉しかったのだ。「こいつならいつでも本を持っているはずでしょ」と認識されていることが。そのことがあって、私はより意識的に文庫本を持ち歩くようになった。だって私が本を持っていないはずがないもんね。
最近「得意科目は何でしたか」と尋ねられたとき、少し悩んでから「生物」と答えた私だが、大学では迷うことなく文学部に進学した。そして、またもや迷うことなく近現代文学専攻。考えるまでもなくそれが当たり前だったからだ。課題のためにもたくさん読んだし、研究対象としてテクストを読み解く術も学んだし、「読書」への歩み寄り方が増えたように思う。この頃はもうしっかり嗜好が定まっていて、自分が未知の本を選ぶのが下手だということも自覚していた(自分で選んだ本がとにかく嗜好に合わないのだ)。なので、ますます古い本ばかり読んだ。母が早い段階から危惧し「もっと他の人のも読んだら」と忠告していたというのに、この体たらくである。であるが、母が選んでくる本は何故か面白いので、それだけは読んだ。そのようにして少しずつ触手を伸ばし、美味しく読める作家の名前をストックする日々は今もなお続いている。
美味しく読む、と言ったが私の中で「読書」という行為はかなり食事に近い感覚で捉えられていると思う。食べることが当たり前のように、読むこともまた当たり前なのだ。近現代文学ばかり読んだあと、突然にエッセイを読んだりミステリを読んだりしたくなるのは、甘いものと塩辛いものを交互に食べたくなる感覚と同じである。あるとき、突然もうしばらく本は読みたくないと思う瞬間が来るときもあるが、それは一時的に満腹なのである。
それに私は、本を読むと体力が回復するような気さえしている。くたびれたときでも、本を読めばシャキッと目が覚めてくる。「もしかしたら、活字を食ってエネルギーを得ているのかもしれない」と友人に話したら「そっちのほうがしっくりくる」と返された。字喰いのバケモノの誕生である。私は実際に旨いものを食べるよりも、旨い本を摂取するほうに強い関心を持っている、そういうタイプなのだ。
月並みな表現ではあるが「本は鏡」であると私も体感している。高校生のときに初めて読んだ感覚、大人になってから読み返したときの感覚、それらはやはり同じではない。読みにくいと感じていても数年後にはするすると読めたり、もとから大好きな本でも心臓に焼き付く場面が変わっていったりする。それは私に様々な時間が蓄積したからで、一概によいことでもなければ悪いことでもない。ただ、変わったのだという事実を明確に感じることができる。それは、読書という行為の持つとても大きな能力であると思う。
だから私は「今」できるだけ本を読みたい。「今」読んだことを大切にしたい。「今」は「今」しかないのだ。何度同じ本を読み返したとて「今」読んだ感覚は「今」しか記録できない。そう考えている。これはもちろん、読書だけに限ったことではないが、読書は特にこの現象が観測しやすいので強くそう感じるのかもしれない。だから読書は面白いし、やめられないし、若い人にはたくさんたくさん本を読んでほしいと願ってしまう。数年後の自分のために、たくさん仕掛けを用意しておくのだ。私が年下の友人たちによく本を贈ってしまうのはこういう訳だ。
もちろん、幾つだって関係ない。誰だって当然今日が一番若い。いつだってはじめ時である。それに、たくさんの種類を読まなくたって構わない。たった一冊だって、気に入った本があればそれを繰り返し読み返してみてほしい。自分の「今」を観測する面白さを味わってみてほしい。そんな風に思う。好きや嫌いといった根源的な感覚すら、まったく無自覚のうちに音もなく変化していることがある面白さ、また恐ろしさよ。
色々語ってきたが、とどのつまり私は本を読むことを愉快な生活習慣だと思っている、ということだ。これは趣味なのだろうか。うん、ピンと来ない。私が「趣味」という言葉と相性が悪いのかもしれない。これもまた、嗜好である。「今」のところこんな感じであるという記録にするとして、今日はここまで。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
