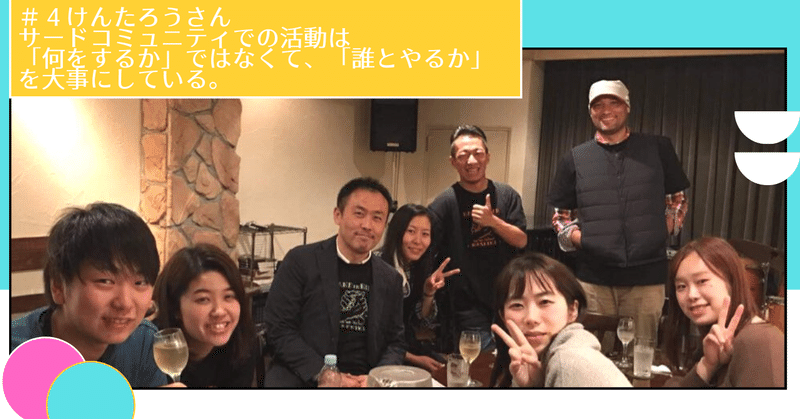
【インタビュー第2弾 Part 2 (After Talk)】 大沼健太郎さん
地方自治体勤務
海外ボランティア系、地方イベント系等4つのサードコミュニティで活動中
■大沼さん。インタビューありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。他の人がどんな話をしているのか気になりますね。
■みなさん面白い話を聞かせてくれていますよ!
ぜひ記事読んでみてくださいね。では、もうちょっと大沼さんの昔の話を聞かせてください。
もちろん何でも聞いてください。
■最初のシンクタンクに入社する一つの理由として、「社会と政策をつなげる仕事がしたい」とのことでしたが、学生の時そう思ったきっかけはなんですか。
野田知佑さんっていう方がいて、その方は世界中の川を下って、それをエッセイに書いている方でして、小学生か中学生の時にその人の本にたまたま出会ったんですね。当時はバブル経済真っ盛りで、片っ端から日本中の川にダムを作るという公共工事をやっていた時代で、野田さんは自然が壊されることを問題視して、本の中で投げかけてたんです。その人の本を読んで、「こんなの作らないで」って言っている人たちがいる一方で、「工事をしたい」って言っている人たちがいて、「なんでここ上手く繋がらないんだろうなあ」って思ったのがきっかけですね。
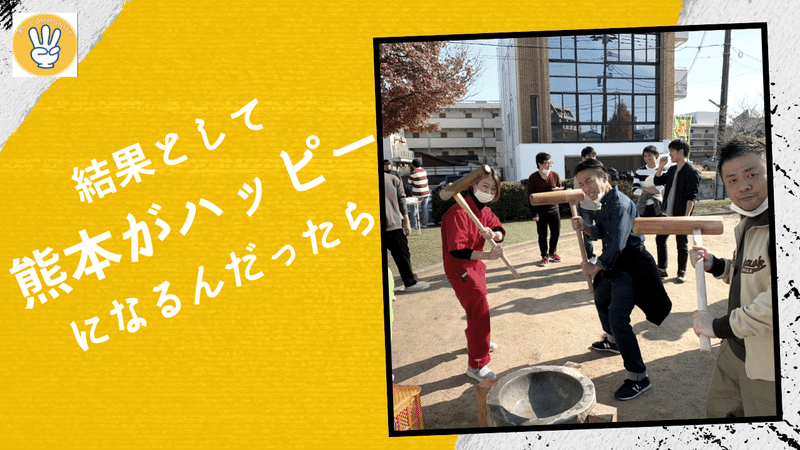
■小学生の時から思っていたんですね。すごい。。。そして政治学を専攻されてシンクタンクに入ったんですね。
東京で働いているときはオン・オフをばっちり分けていたとのことでしたが、何か理由があるのですか。
東京で働いていた会社は情報セキュリティがすごく厳しかったんです。
例えばですけど、会社の合併情報とかを知っている会社だったので、仕事の話をプライベートで絶対しないって決めていました。うかつなこと言えないっていうのがあったので、オン・オフきれいにはっきり分けていたっていうのがありました。
一方で熊本での仕事は、いろんなことをぐちゃぐちゃにしないと進んでいかない世界でもあったので、意図的にぐちゃぐちゃにしていたのかもしれないです。熊本に通い始めた当初は、例えば飲み屋で知らない人に「復興で来てるんです」ってことを言うのはすっごく嫌で、自分の身の内を絶対に明かさなかったんですけど、途中からプライベートと仕事を分けないほうが可能性がいろいろ広がって、結果として熊本がハッピーになるんだったら、分けるのをやめよう、って思って、行動するようになりました。今ももちろん言えないことは言わないですけど、一気に自分の中でハードルを下げたっていうのはありましたかね。
■明かすのがいやだった理由は?
情報セキュリティが厳しい会社で、新卒のときからそういう風に社内教育を受けて育ってきたので。飲み屋で隣に座った知らない人と名刺交換なんて絶対しなかったですし。
東京だったら飲み屋で隣のテーブルに関係者がいたりとか、合併の話をそれに関連する人が聞いていたりとか、普通にあり得る環境じゃないですか。だから僕から言わせると、「半沢直樹」はあり得ないんですけどね、あんな飲み屋で仕事の話をするなんて(笑)。
熊本では、そこまで情報セキュリティが高い仕事をしているわけじゃないっていうのと、誰かと誰かをつなぐことで熊本がハッピーになればいいなっていうのは思いましたかね。
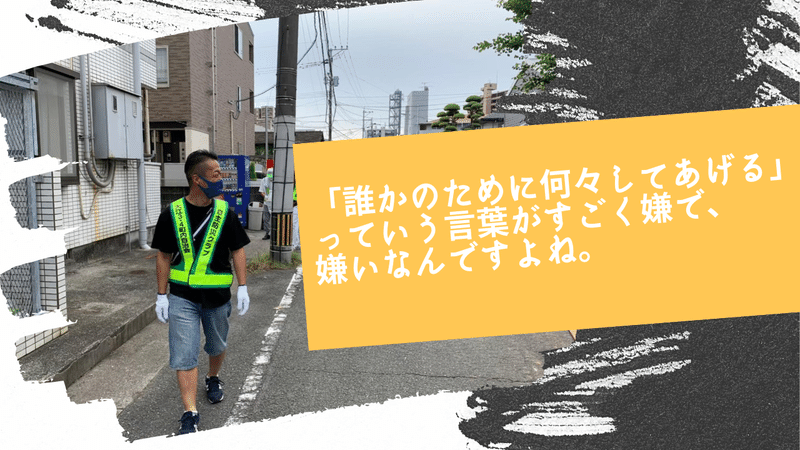
■すごい世界ですね。では、熊本に行ってからいろいろなサードコミュニティに入られたと思いますが、そのサードコミュニティに入る前のイメージと入った後のイメージの変化はありましたか。
入る前に持っていたイメージとしては、サードコミュニティって、「誰かのために何々してあげる」っていう意識高い系の人たちの集まりで、自分とは合わないだろうなあって思っていました(笑)。僕は「誰かのために何々してあげる」っていう言葉がすごく嫌で、嫌いなんですよね。押しつけがましいというか、恩着せがましいというか(笑)。いろんなコミュニティで僕が活動するのは、「僕にとってそれがハッピーかどうか」がすべてなんですね。モチベーションの軸を自分の外に持ってきちゃうと、その相手のせいにしちゃう気がするんですね。
たとえばフィリピンの児童養護施設を支援している団体に関していうと、もちろん「フィリピンの子どもたちのために」っていうのはあるんでしょうけど、それよりも、僕自身が楽しいかどうか。たとえば「ほんとはやりたくないんだけど、子どもたちが困っているからしなきゃいけない」っていうモチベーションになっちゃってたとしたら、それは子どもたちのせいにしちゃってる気がする。そういうのは僕は好きではないし、得意でもないですね。
僕が今いろんなサードコミュニティで活動を続けているのは、僕が楽しいからです。たぶんですけど、仮に夏祭りを一緒にやっている人たちと喧嘩したら僕は夏祭りの実行メンバーを抜けるでしょうし、その他のコミュニティも心地よくないなって思ったら、やめちゃうと思います。だって楽しくないですからね。
で、実際にサードコミュニティにいくつか入ってみて思うのは、必ずしも意識高い系の人たちの集まりじゃなかったです。それはいい意味で裏切られた。サードコミュニティというものが、楽しめる場所なんだなっていう風に僕が気づいたのが最近なんでしょうね。だから続けられているんだと思います。
■ボランティアって自己犠牲だと言われることもありますが、活動されている方って確かに楽しんでやられている方が多いですよね。そして、サードコミュニティで活動している人は時間とエネルギーを持て余しているって言葉がありましたけど、その時間とエネルギーを趣味に費やしている人もいる中で、それを人とのつながりのほうに持っていったのはなぜですか。
人といるのが好きなんでしょうね。繰り返しになっちゃいますけど、「何をするか」よりも「誰とするか」のほうが僕にとって大事なので。ずっと家で一人でこもって趣味に没頭しますっていうのはあまり得意じゃないんですよね。まあそういう時間もたまにはいいけど、それだけだとつまらない。人といるのが好きっていうのが大前提にあるんでしょうね、人っていうものが面白いなっていつも思っているので。
いろんな人とお酒飲むのが楽しいですよね。飲むとすぐ忘れちゃうのが問題なんですけど、昨日飲んでいて楽しかったなって感情だけは残っているから、それでいいかって思っています。
■お酒が趣味って言っていましたもんね。でも記憶なくしちゃうんですか(笑)
記憶はほとんど常に飛ばしていますけど、それで何かをやらかしたってことはないはずです、そんなには。覚えてないだけかもしれないですけどね(笑)。
でも、東京にいるときは常にイライラしていたので、飲み会の場でもずっと仕事の愚痴ばっかり言っていた気がします。それに比べたら、いいんじゃないかな(笑)。

■熊本移住して穏和になりましたか?
サードコミュニティの話とはちょっと違っちゃうかもしれませんけど、熊本にいるときの自分のほうが、人として優しくなれたんだろうなって思うときはあります。たとえば東京のバス停で知らないおばちゃんが隣にいても話さないですけど、熊本でバス待っていて隣に知らないおばちゃんいたら話し掛けますもんね。
2年くらい前ですかね、まだ僕が熊本に移住する前ですけど、中学・高校の同級生が熊本に遊びに来てくれて飲んだことがありまして、そのときに、「お前は東京にいたときはAIだったけど、熊本に来て人間になれてよかったな」って言われました。それは本当にそのとおりなんだろうなって思いましたね。
東京にいたころ、一個一個の仕事は楽しいものが多かったし、やりがいもありました。東京にいたときは、超大手シンクタンクでコンサルタントとして働くとか、都内の一等地に住むとか、そういったステータスみたいなものが、僕の人生の満足度というか幸福度につながってるんだと思ってやっていましたし、そう思い込ませようとしていたのもありました。一方で「キャッキャしたい」っていうのは自分の中ではたぶんずっとあって、でもそれを具現化できるような環境はありませんでしたし、その余裕もなかったので、ほんと腐っていたと思います。
コンサル時代しか僕のことを知らない人からすると今は結構違いますもんね。中学・高校からの友達とかはキャッキャしていた時代の僕を知っているので、その友達たちからすると「ようやく戻ってきたな」って感じなのかもしれません。
■熊本に出会ったことが大きな転機になったんですね。
熊本に移った当初、新しいコミュニティを築くのは大変でしたか?
最初の年は基本月曜の朝熊本に羽田から飛んできて、4泊5日で仕事をして金曜、週末に東京に戻るって生活をしていました。でも2年目くらいから仕事が徐々に落ち着いてきて、仕事後にいろんな所に飲みに行くようになって、そこで多くの友達に出会いました。だから、いきなり環境がガラッと変わったわけではなくて、移住するまでの4年間で徐々に徐々に慣らしていったというか、耕していったという感じでしょうか。
■それでも、移住しようと思うほどの人間関係を築けたことはすごいですね。
僕は無愛想でとっつきにくいように見えるらしいんですけど(笑)、そこを破っちゃえば腹割っていろんな話をするんですよね。だから「腹を割って話す」っていうのは僕の人生における大事なテーマかもしれないです。
■大沼さんありがとうございました。これからも活動頑張ってください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
