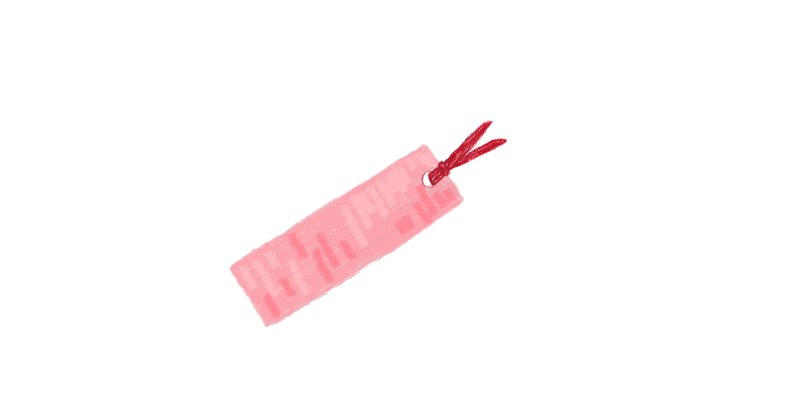
サラリーマンだった私が、「文春」や「Number」で記事を書くようになるまで。♯5 マラソンのゴールがスタートだった。
ずいぶん久しぶりのnoteになってしまった……。
つくづく自分というやつは、〆切りがないと原稿が書けないんだなと思う。書くことが嫌いではないが、書くことに執着がないのだ。困ったことに。
まあ、とにもかくにも続きを書きたい。
(この間、目に留めていただき、読んでいただいた皆さまへ。どうもありがとう!)
(現在発売中の週刊文春10月6日号に、シニアYouTuberのグラビア記事を書いています。機会があればご拝読ください)
さて、ひょんな理由から挑むことになった、人生初のフルマラソン。選んだ舞台はホノルル。天気はすこぶる良かったと記憶している。
思い出は薄れがちだが、それもまあ仕方がない。なにせ25年以上も前の話である。たしか有給休暇が1日しか取れず、HISの弾丸ツアーに申し込み、現地に着いたのは1996年12月のことだった。
レース当日、まだ夜も明けきらぬなか安ホテルをでて、30分ほど歩いてスタート地点に向かった。前回書いたように、これは自分との戦いであり、イベントを楽しもうという気持ちはほとんどなかったように思う。
号砲と同時に走り出す。
わりと体力に自信があった僕は、後先を考えずにランナーを抜くことばかりを考えていた。後方からスタートしたこともあって、序盤は驚くほど多くのランナーを抜いた。気がつけば大集団の中から抜け出し、朝もやが晴れる頃には細長くなった隊列の中ほどにいた。当時はこれこそがマラソンの「罠」だということに、まったく気づいていなかったのだ。
序盤はできるだけゆっくり入り、ペースを決して上げないこと。ずいぶん後に、高橋尚子さんらを指導した故・小出義雄さんから教わるマラソンの極意(https://number.bunshun.jp/articles/-/839163)を、この時はまったく知らなかった。
15㎞くらいまではなんとか周りの景色も楽しめた。タイムも1時間20分くらいだったと思う。だが、そこからがいけない。次第に足が重くなり、何にもまして古傷である左膝の痛みに悩まされた。20㎞を過ぎてからの長いハイウェイ。景色が単調になってからの道中はまさしく地獄だった。
なんでこんなに痛いんだろう。苦しいんだろう。疑問を振り払うように走り出すが、またすぐに痛みから足が止まってしまう。とうとう痛みを我慢することができなくなり、ハーフ以降はずーっと歩きっぱなしだった。
終盤には自分より遥かに年上と思われるおばあちゃんたちにも抜かれ、完走こそしたものの、要したタイムは5時間台……。思っても見ない結果に打ちのめされた。
苦しんだという意味ではむしろ願っていたことでもあったが、実際にやり遂げた感はまったくと言っていいほどなかった。肉体の痛みに耐えることは、自身の限界を知ることにはつながらない。そもそもほとんど練習をせずに臨んだ時点で、得られるものがさほど多くないことに気づくべきだった。
だから、筋肉痛と悔しさで眠れなかったその夜、二人でもう一度話し合い、1年後のリベンジを誓ったのは当然のことだったように思う。
次こそはちゃんと走る練習をする。と同時に、来るべき退社の日に向けて、できる限りの準備をしようと心に誓い合った。
もうこの時点で、会社を辞めることへの迷いはなかったように思う。
次(2度目)のマラソンを走り終えた後、自分たちは辞表を書き、きっと新たな一歩を踏み出すのだろう。適性を見極めるために挑んだ初めてのフルマラソンだったが、後から振り返ってみると、勢いをつけるという意味合いの方がはるかに大きかったように思う。
ライターになるためにフルマラソンを走る経験はまったく必要ないが、意味のないことに全力で取り組み、それを笑い飛ばすことでようやく次へ進めるということは「ある」のかもしれない。
そこからの展開は、早かった。
翻訳家を目指してた伊達君は、東京外大に入り直すことを計画していて、次の夏だったか、TOEICで990点を叩き出した。「あと10点かー」と羨望のまなざしで話しかけると、「TOEICの満点は990点なんだよ」と事もなげに言っていた。
資格や学校がある翻訳と違って、ライターにはこれといった資格がない。この敷居の低さをどうとらえるか。それが重要だった。
今の自分にできることは仕事とマラソンの練習と割りきって、翌年の春から冬までを過ごした。会期末には人事考課があったが、そこで僕はS級の評価を受ける。前年度だったかに制度が少し変更されていて、トップのS級は社内で数%しかいないはずだった。
飛ぶ鳥跡を濁さずと頑張ったのは、マラソンの練習も然りだ。毎夜、残業を終えて社宅へ帰り、そのまま眠りにつきたい誘惑を振り切って河川敷まで走りに出かける。あの頃、僕は大阪で働いていて、社宅のある大和川沿いをよく走っていた。(なぜかこの頃のことを思い出すと、川面から漂ってきた洗剤の匂いを思い出す)
練習をすればそれは必ず成果となって現れる。秋風が吹く頃にはもう走ること自体が楽しくなっていて、走らない日はむしろ物足りなさを覚えるほどだった。
もはやホノルルは目標でもなければゴールでもなかったが、それでも律儀に2度目のスタートラインに立ったのは、やはり次なる人生に向けて弾みをつけたかったのだと思う。
ここで結果が出ていれば言うことなしなのだが、現実はそう甘くなく、またも結果は奮わなかった。中盤以降が勝負と思い、なるべく抑えて走り出したものの、やはり20㎞過ぎ以降は古傷の膝が痛み出し、その傷みに耐えることはどうしてもできなかった。
タイムは1年前とほとんど変わらない、5時間台前半。もちろん悔しさはあったが、どこかサバサバした気持ちにもなっていた。
その夜、南半球の真夏の凍星に誓ったのは、いつか必ず、マラソンではない人生の本当の目標を叶えようという決意だった。
記憶が確かなら、翌年の秋に伊達君はひとあし早く会社を辞めた。東京外大の転入試験に見事合格し、学校に通いながらさらに翻訳を学ぶための翻訳教室も探し出してきていた。
僕もこの頃には、退社の決意はほぼ固まっていた。年齢的に新たなキャリアを始めるにはギリギリという認識で、12月末日での退社にこだわったのは、99年の1月になれば誕生日を迎え28歳になってしまうからだった。
少しでも早く会社を辞め、そこから5年のうちにライターとして何らかの結果を出す。漠然としたものだが、それが次の目標になった。
その年の12月、あれはどこだったのだろう、大きなホールのような場所だったと記憶しているのだけれど、たくさんの同期が送別会を開いてくれた。
この時のことを思い出すと、僕はにわかに不安な気持ちになる……。
年の瀬にこれだけ盛大な会を開いてくれた友人に、僕はちゃんと心からの感謝の気持ちを伝えられていただろうかと。
それほど、当時は気持ちに余裕がなかったのだ。これから飛びこむ世界はコネなし、経験なし、さらに言えば決まった道筋すらなかった。
ライターになろうと思う、とは周囲に語っていたものの、どうやったらなれるかも正直なところわかっていなかったのだ。
かくして、僕はサラリーマンの肩書きを捨て、文字通りフリー(自由)の身となった。
肩書きを失うことで、これほど不自由な境遇になるとは思ってもいなかった。(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
