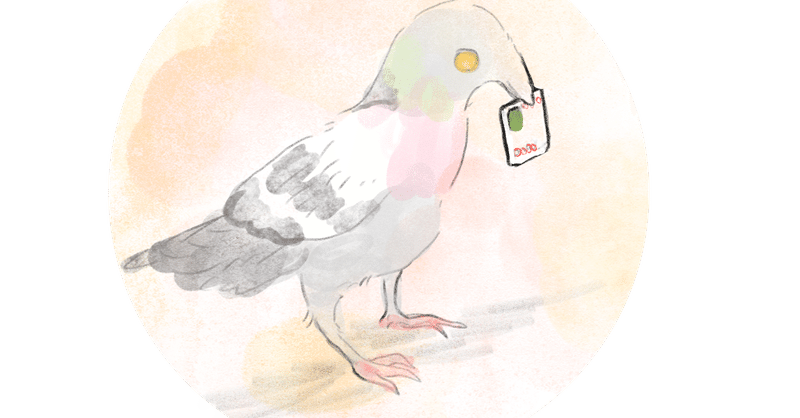
サラリーマンだった私が、「文春」や「Number」で記事を書くようになるまで。♯4 勢い転じてフルマラソン。
転職をする人と、一つの会社で添い遂げる人、今はどちらの方が主流なのだろう。昔と今とでは、転職に対する心の持ちようも微妙に変わってきているのだろうか。
僕が会社を辞めたのは平成10年の年末だった。
年齢で言えば28歳のとき。すでにセカンドキャリアを歩むにはギリギリという認識だった。
就職時は買い手市場だったこともあり、せっかく入れた会社を手放して良いのかという不安も抱いていたはずだ。しかも自分の場合は転職ではなく、とりあえずの退社である。親に相談したとき、絶句し、猛烈に反対されたのを憶えている。
もしあの時、一人で悩みを抱え込んでいたら、僕は最終的にどちらの道を選んでいたのだろう……。
会社員時代を振り返ると、それなりに楽しい思い出がよみがえる。スーツを着て出勤するのも初めのうちは新鮮で、知らないことを覚えるのも楽しかった。
そもそもなぜ損保企業を志したのかと言えば、恥ずかしながらマンガである。浦沢直樹さんの人気作『MASTER キートン』を読んで、保険の調査員をしながら考古学を究めようとする主人公の姿に憧れを抱いたのだ。(もっといえば、あんな風にいつも優しく正直な人間になりたかった)
さすがに現実は甘くなく、仕事は想像以上に忙しかった。
有給など思い通りに消化できるはずもなく、残業は当たり前。一、二年目はいけ好かない上司や先輩にも悩まされた。
それでも週末は社内のサッカー部と、同期で作った野球部を掛け持ちし、サラリーマンライフをまあまあ謳歌していたように思う。
だが前回書いたように、僕にはサラリーマン以外にやりたいことが見えてきていた。キートンのように並外れた才能があれば、ライターと会社員生活を掛け持ちもできたかもしれないが、実際は悲しいほどに凡人である……。
もんもんとした気持ちを引きずりながら、あれはいったいどういったタイミングだったのだろう。いつものように週末の草野球を楽しんだ後、ファミレスに寄ってべちゃくちゃと話をしていたときだったと思う。
とりわけ仲の良かった伊達君と、こんな会話をした。
「オレ、会社を辞めてやりたいことがあるんだけど……」
まさか!もう一人からも同じように「オレも」という答えが返ってくるとは(どちらも)思いもしなかった。
聞けば、彼は翻訳家になりたいのだという。外国語学部出身ではなかったが、小さいころから洋楽が好きで、翻訳小説をことのほか愛していた。
毎日毎日、決まったルーティンをこなす中で、本当に自分のやりたいことが見えてくるというのは、じつはそうめずらしいことではないのかもしれない。
僕たちはそれ以降、互いの悩みを包み隠さず話し合うようになった。
自分たちが共に本好きであることはわかった。会社を辞めることがどれほどリスキーなことであるかもわかっていた。辞めた後の生活が相当苦しくなるのもわかっていたと思う。
ただ唯一わからなかったのが、自分たちが何者であるかということだった。
はたして、自分たちにライターや翻訳家になるための資質はあるのだろうか? 困難に直面したとき、それに耐えるだけの胆力は持ち得ているのか。なにより、夢を途中で諦めてしまわないかどうかが心配だった。
そこで思いついたのが、マラソンを走ることだったのだ--。
んっ、マラソン!?。
どういうこと、と書きながら自分でも疑問に思う。
あの当時、なぜあんなことを思いついたのかよくわからない。ただ二人で話し合う中で、自分たちが何者であるかを知るために、難しいことにチャレンジしようと決めたのだ。きっとそうだ。
その困難なことの象徴として思いついたのが、マラソンだったのだろう。
1990年代後半と言えばまだランニングブームなど来ていなかった。高橋尚子さんがシドニーオリンピックで金メダルを獲得し、「とっても楽しい42.195㎞でした」と笑顔で振り返るのは2000年のこと。当時はガイドブックもなければ、マラソン専用のシューズもなかったように思う。
僕たちはそれを秋に決意し、エントリーが間に合う12月のホノルルマラソンに照準を絞った。多少の練習はしたかと思うが、ほぼぶっつけ本番で人生初のフルマラソンに挑むことになる。
目標は「完走」。いや、それ以上に「苦しむ」ことだった。本当に苦しくなったときににじみ出てくる、己の本性を見極めようとしたのだ。
それがまさか、あんな姿になるとは……。
この時はまだ知る由もなかった。 (つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
