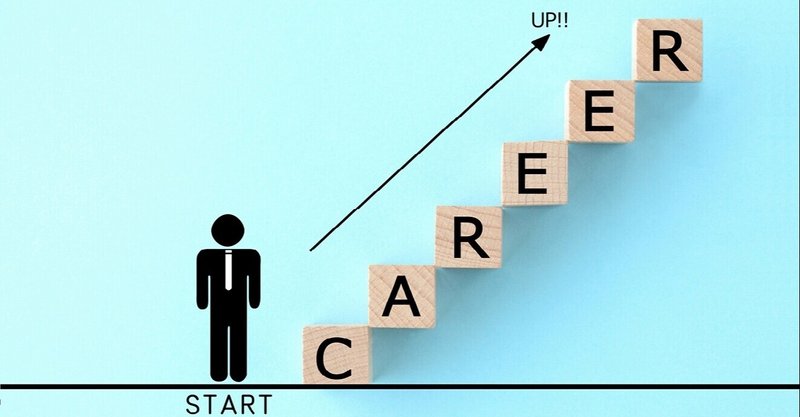
今後10年で市場価値が高まる「働き方」~仕組みづくり人材~
今回は、市場価値・これからの時代で求められる人についてのお話です。
「市場価値」の話をする際に、前提として「市場価値」と「個人で食っていける人になる」という話が混在しているケースがよくあります。
前者は、「どの企業にいっても活躍できるスキルを身に着ける」等の組織で働くことを前提にした話、後者は個人事業主になっても稼げる等の個人で稼ぐスキルという話。今回は前者を前提の元、「市場価値」の話をします。
仕組みづくり:新たなビジネスをつくり上げる人
今までは仕組みに乗っかり、忠実な運用者が求められる時代。これからは、時代の変化に合わせ絶えずPDCAを回し、新たなビジネスモデルをつくり上げる人、「仕組みづくりができる人」が求められる時代。
テクニカルスキル(専門知識・スキル)だけに走っても、そのスキルはいつまで求められるか先行き不透明なことも多く、スキルを派生させたり、ポータブルスキル(どこでも通用するスキル)を上げていくことも重要。詳しくは過去に以下記事に記載しています。
シフトチェンジの時代
今までのやってきたことを深める「深堀」と、新しいことを模索する「探索」の両軸を進めることは、企業でも個人でも求められること。
いくら調子が良い主力事業であっても「必要に応じてシフトチェンジしていく」というのは業界を牽引していた大手でも求められていること。こんな大企業も過去、業種が変わっています。

では、どんな人材が仕組みをつくっていけるのか?
■仕組みをつくれる人4選
①個人での成果より、組織での成果
属人的で再現性の薄い個人成果の集積ではなく、柔軟なチームプレーによる組織成果の最大化に貢献できるかを求める企業が増えています。より組織的な動きに貢献できるかどうかは重要な視点。自分に部下がいるかどうかにかかわらず、チームや組織に何かできることがないか。
②指示待ち型人材より、テーマ設定型人材
会社の経営者や上司から降ろされてくる指示を待っている人材ではなく、各自が自分のミッションからテーマを発見し、合意を得て、それに向かっていく「自走度」の高い人材が求められています。(合意なく走ると、ただの暴走になることも…)
③自前型人材より、ネットワーク型人材
自分の力だけで乗り切ろうとするのではなく、社内外のリソースやテクノロジーを活用して会社の枠を超えたプロジェクト方式で事業を展開していく必要性も高まっています。そのため、ネットワークを持つ人材は活躍機会が増えています。
④固定ミッション型人材より、遊軍型人材
経営を取り巻く外部環境の変化が激しくなると、営業や企画や製造など、決められたポジションに固定されているよりは、状況に合わせて必要なところにフォローに入る多能的な人材が高く評価される場面が増えます。
いまの市況ではまさにそんな感じですよね。
また、フラットな文鎮型組織が増えていく中では、マネージャーも指揮管理するだけではなく、自ら手を動かして、現場を走れるかどうかということが
当たり前のように求められるようになっています。
■市場価値が高める志向・価値観
この前提の中で、今後10年に市場価値が高まる「働き方」の志向・価値観は以下です。
【ミッション志向】
見かけの役職・年収にこだわらず、現実のミッションの重さや裁量の自由度にこだわる
【挑戦志向】
自分の経験分野やスキルにこだわらず、新しい価値創造へのチャレンジを好む
【貢献志向】
企業から安定や保護をもらうことを期待するのではなく、自分が貢献できることを重視する
【ネットワーク志向】
業界や年齢など固定階層をまたいで幅広いネットワークを持っている
【ポジティブ志向】
業務の精度や慎重さはあるが、基本的に楽観的・前向きな傾向が強い
【水平志向】
コトやヒトの価値判断がフラットで、過去の成功・失敗体験に縛られない。決めつけ、思い込みがない
【包容力・柔軟性】
理想と現実のギャップへの柔軟性や、理想通りに進まないことを飲み込んで前進させていく力がある
【矢面志向】
悲観的な状況や、絶望的なトラブルでも簡単に折れず、高い当事者意識で壁を乗り越える態度を失わない
まとめ
既存の事業を深めながらも、広げて新たなビジネスをつくらねば衰退してしまう時代。この時代に必要な人材が「仕組みができる人材」
前提として必要なのは、自立したビジネスパーソンとして自ら考え、当事者意識を持って、会社ではなく、市場や顧客に貢献しようとすること。
今後の時代を牽引できる人材になるために、早くから全体最適のために柔軟に動き、フォローできるスキルを身に着け、挑戦できる人材へ。
Twitterやっています!よろしければフォローお願いします!
https://twitter.com/33king_co
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
