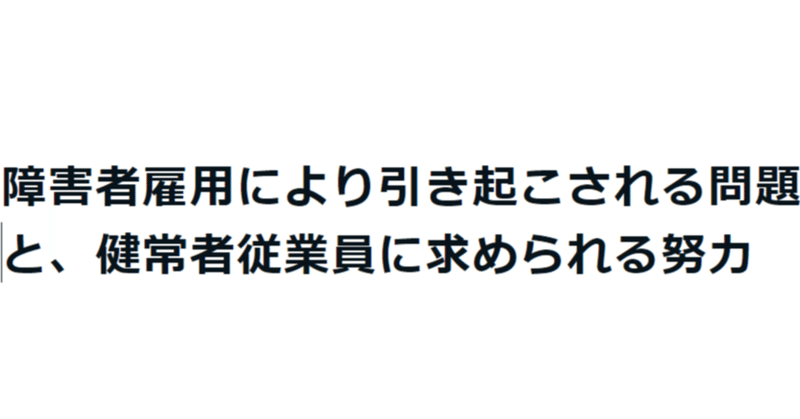
障害者雇用により引き起こされる問題と、健常者従業員に求められる努力
次年度(2024)より、障がい者の法定雇用率が2.3%から2.5%へと引き上げられ、さらに次の年(2025)には2.7%に引き上げられる。

参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001039344.pdf
障がい者を何人雇うかは、その企業の従業員の数や、
障がい者の障害の程度により異なる。
障害の程度とは、知的、身体、精神、発達の障害の重さで扱いが異なるということである。
例えば、重度知的障がい者を雇うと2ポイント(正確には2人分という扱い)がもらえる。
逆に、雇った障がい者が短時間勤務だと0.5ポイントしかもらえない、というようなカウントをする
企業は、それらのポイントを合計した数が「4」とか「3」とかになるように、障がい者らを雇う必要がある。
この「4」とか「3」とかいう最低ラインは、企業の従業員数で変わる。
ちなみに、この基準を満たさないと行政指導を受けたり、不足人数分1人あたり月5万円徴収(/1人)される。
そして、次年度以降、この雇用率(上記法定雇用率)が引き上げられるため、今まで「障がい者0人」だった企業が「障がい者1人」になるかもしれない、ということが起こる。
元から障がい者を雇っている企業にとっては、社内制度が確立している可能性が高いため、大きな問題ないかもしれないが、
特に「0人」だったところが「1人」になるところは、大変だろうなあと思う。
理想論を言えば、
障がいがあっても働ける社会(ノーマライゼーション)というのは、
今後、自分自身何があるかわからないので、とっても安心な社会で良いなあと思う
しかし、自分が障がい者になることなんて絶対にない、と他人事に考えている人にとっては、職場に障がい者がやってくることは驚きだと思うし、接し方から何から、難しいよなあと思う。
余談だが、自分の父親が勤めている会社は障がい者雇用をしている。
そして父親は、その障がい者の指導役というか上司のようなポジションをやっている。
父と障がい者従業員とのエピソードを聞いていると結構面白い。
例えば、仕事中に姿が見えないと思ったら、給湯室でこっそりアイス食べてたとか、
当該従業員がバス停から会社までゲームしながら歩いてるのを見つけた父親がその従業員を叱ったとか。。。
我が家は弟が障害持ちなので、おやじとしても、ハンディのある人にあまり抵抗がないのかもしれない。
ただ、健常の家で育った健常者は、職場に障がい者(特に知的と精神)が来ることを、どう受け止めるのだろうと考えてしまう。
せっかく、障がい者が働ける社会を作ろうとしても、障がい者が社会進出したことが原因で、今までよりも障がい者への風当たりが増してしまうかもしれないという不安もある。
厚労省がどこまで引き上げる気なのかはわからないが、すごいチャレンジある制度だなと思った。
個人的な意見としては、やはり健常者側は努力すべきだし、皆が働ける環境整備しなければならないと思う。
知能があるなら、障がい者に合わせた行動、言動、思考をすべきであると思う。
「べき論」ですが・・・
私個人としては、これは健常者が試される制度だな・・・と思う
あと、個人的にもう一つ、私は将来事務所や会社を立ち上げようと思っており、そのときは絶対に障がい者雇用をしようと思っている
そのため、この制度をきっかけに、先輩企業たちによって培われた障がい者雇用ノウハウがもっと世の中に増えればありがたいなーとも思っている。
さらに理想論をいうと、この制度をきっかけに、
「障害を持ってても大丈夫だね」
と言えるような社会になっていけばいいなと思っている。
