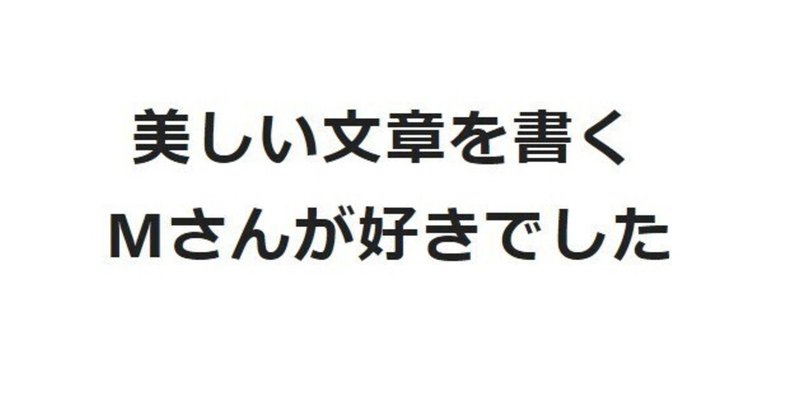
美しい文章を書くMさんが好きでした
美しい文章を書く人が好きです。
私は学生時代、理工系の大学で化学を学ぶ学生でした。
化学科では、学年が進むと実習が増え、ほぼ毎日実験室にこもることになります。
実験をする度に結果を考察し、それをレポートにまとめる生活を送っていました。
私は化学科の劣等生だったので、「理工系学生のあたりまえ」を淡々とこなすことはできず、猛然とがむしゃらに、日々の実験とレポートに追われる生活をしていました。
そんな時、インターネットの掲示板でMさんに出会いました。
Mさんとは共通の趣味があって、偶然掲示板で出会いました。
Mさんとオタクのオフ会で実際に会うこともありましたが、特別仲の良い友人になることは出来ませんでした。
ただ、Mさんは当時ブログをやっていて、私はそのブログをこっそり読んでいました。
そのブログには、Mさんが読んだ漫画や映画のことが綴られていました。
私は学生時代、ほとんど本を読まない学生でした。
読むのは理工書だけでした。
高校生の時は大学受験のために、学校や塾で薦められた「受験のために読んでおけ」と指定された有名作品だけ流し読みしてました。
当時の私にとって、活字の本(特に小説)は「受験のために読まなければいけないもの」でした。
「小説を楽しく読む」なんて、考えたこともありませんでした。
しかし、Mさんは違いました。
Mさんは文学部の学生で、様々な本を読んでいました。
例えば、ヘルマン ヘッセ『車輪の下』
私は受験のためにタイトルと著者名だけ覚えていました。
しかしMさんは、その本の内容をなぞらえて、読んだ本や観た映画の感想をブログに書いていました。
たまにMさんは、私も読んだことのある漫画の感想を書いていました。
私は漫画を読んでも「面白い」とか「すごい」とか、その程度の感想しか言えませんでした。
でもMさんは、同じ漫画を読んでいるはずなのに、表現が豊かで、私が表したかった気持ちを、見事に文字として、豊かな表現で、読んだ人を唸らせるような記事を書いていました。
私は、このMさんのブログに、とてつもない衝撃を受けました。
当時の私は、ひたすら数式を使ってデータを算出し、それらを端的にレポートにまとめる、そんなことで頭がいっぱいの学生でした。
実験レポートに無駄は許されず、個性も存在しません。
しかし、いわゆる文芸と呼ばれるものには、一見すると何が言いたいのかよくわからない場面がたくさん出てきます。
でも、それらはきっと、作者が表現したかったもので、作者にとって必要なものなんだと思います。
文芸は、そんな表現がたくさん溢れています。
作者が好きなように味付けをすることで、作品に彩り生まれます。
その味付けや彩りは、読み手にとって
「そう! 私が言いたかったのは それなんだ!」
に変わります。
つまり読み手は、作者の表現から、自分が言いたかったことを見つけ、
自分の内部に隠れていた気持ちがどのようなものだったのか、知ることができます。
私は、Mさんの記事から、文芸の凄さ・素晴らしさを学びました。
私は自分の気持ちを文字や言葉に起こすのが遅いタイプです。
「何と言ったらよいのだろう・・・」
とモヤモヤした時間が続くことが非常に多いです。
だから、作品の感想を文字で起こせる人は本当にすごいと思うし、もっともっと、その人の表現を読みたいと思うのです。
現在の私の仕事は、要らないものをとことん削って、理屈をこねくりまわすお仕事です。
このように、カットできるものをとことんカットした日常を送っていると、段々と、理屈じゃないもの、まわり道をしてゆっくり進む時間や表現が恋しくなります。
それが文芸作品なんだと思います。
例えば、映画のなかで流れる景色の場面とか、セリフがない場面がそれに当たるのではないでしょうか。
一時期流行ったファスト映画ではきっと飛ばされてしまうような場面というのは、無駄なようで無駄ではない、必須な場面だと思います。
映画や小説から無駄を削ぎ落とし、序論と結論だけ述べてたら、何も面白くないです。
その表現が抜群に美しく、初めて文芸の面白さを私に教えてくれたのは、間違いなくMさんでした。
Mさんとは、今はもう縁が切れてしまいました。
今どこかで、Mさんが文章を書く仕事をしているなら、ぜひその作品を読みたいです。
Mさんへ
今も本を読んでいますか? 何か、書いたりしていますか。
もし、文章を書かない人生を送っていたら、本当にもったいないと思います。
勝手な意見だけど、私はMさんが見たもの、感じたことを、Mさんの切り口や表現で語ってほしいです。またMさんの文章を読みたいです。
ずっとずっと、待っています。
おしまい
