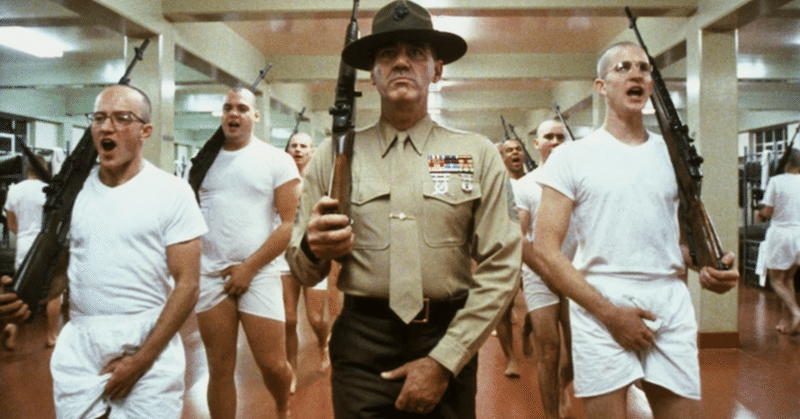
教授の異常な愛情 - または私は如何にして心配するのを止めて彼の学説を批判するようになったか
アルベルト・アインシュタインを心の師匠(&反面教師)として育った私は、良くも悪くも粘着気質です。日常生活ではともかく、何か気になりだすと、そのことを何年も何十年も独りで考え続けるのです。
ところで私にはもうひとり、心の師匠と呼ぶのは少々大げさなのでしないでおきますが子どもの頃から親近感を寄せてきた男性がいます。まんが家さんです。「週刊朝日」(現在廃刊)で長くうんちくまんがを連載されてきた方です。名前は夏目房之介さんといいます。あああの方ねとピンとくる方も多いと思います。その後学習院大の大学院教授として十年奉職し、おととし退官された方です。
私が一度(正しくは二度ですが)彼のゼミに呼ばれて、彼の院生、学生、留学生たちを前に、それなりに濃密度な内容のことを講演したことがあります。ドラえもんをマグカップやリュック等にあしらって商売する、いわゆる「商品化」をめぐる法理論についてです。これがわかると、日本のアニメ史における手塚治虫の位置づけが、旧来の説を覆すものとなると、そういうお話をしました。
私としては、精一杯かみ砕いて語ったつもりです。理屈より直観での理解をしてもらえるよう、面白おかしい画像をいろいろ用意して、それで笑いを取りながら、前編後編を語りました。その後質疑応答が続いたのですが、どうも話がかみ合わないのです。
そのひとつが、日本のテレビアニメ黎明期の、ある事件についての質疑応答でした。
白土三平…といっても今の若い方はご存じないと思います。実は私もなじみのあまりない名前です。1960年代、忍者劇画で子どもから大学生それもインテリ学生運動家たちまでも熱狂させた、そういう劇画を描いていた方です。この白土さんに、今でいう東映アニメが目を付けて、テレビアニメの原作を提供してもらったのです。それをテレビアニメ化したのがこれでした。

これ、そこそこ人気番組になりました。今でいう商品化が東映によってなされ、商品化印税が流れ込んできました。これに気を良くした東映(というか東映アニメ)が、その後白土の原作まんがから離れて脚本家チームによる完全オリジナル路線に転じた際に「今の新シリーズではうちの脚本家チームがすべてのストーリーを作っているわけだから白土原作とは呼べない、それで『原作 白土三平』の表示を番組から外させてほしい」と白土先生に伝え、了承してもらい、以後の商品化印税は東映アニメの独占となった…そういう話を私は講演でしました。
すると院生さんのひとりが質疑応答で噛みついてきました。「白土には『絵の権利』があるはずなのに、どうして途中からこのアニメの原作者でないとされたのか?」
なんですねん絵の権利って? 私は戸惑いました。それで彼にはそう訊きかえしました。
どうも質問者は、主人公・フジ丸やその仲間たちには、それぞれに『絵の権利』が発生していて、それは原作者・白土に帰属するものと思い込んでいるようでした。
そんな権利聞いたこともないと言い返そうとしたら、夏目教授があのでっかい声でいきなり割り込んできて「これは白土の絵じゃないよ!」と言い出しました。「絵柄がぜんぜん違う」と。

これには呆れて私はこう言い返しました。「描いているのは東映のアニメーターたちなのだから、白土先生の絵でないと言われても…」
夏目さんはまんがの読解についてはずば抜けた眼力をお持ちなのですが、アニメーションについてはど素人なのだと、このとき気が付きました。
私はこう説明しました。「アニメーションは、複数の絵描き、つまりアニメーターたちが、同じ人物の絵を描くのですよ。ミッキーマウスのアニメを作る時も、複数の絵描きがミッキーを一枚一枚描いています。絵描きにはそれぞれ絵柄に癖や特徴があるので、全員が同じ絵柄のミッキーを描くのはほんらい無茶なのですが、幸いミッキーマウスは、誰でも同じ風に描けるようシンプルなものにあらかじめデザインされているので、誰が描いても同じ絵柄でアニメートできるのです。『風のフジ丸』のときもそうで、制作にあたっては事前に主人公らのデザインが、白土のものよりすっきりしたものが用意されて、各アニメーターはそれに準拠でフジ丸たちの絵を一枚一枚描いているのです。ゆえに『これは白土の絵じゃないよ』とあなたが言われても、そんなのは最初からわかりきった話です」
どうも彼は、テレビアニメ「風のフジ丸」における各登場人物は白土の絵とまるで似ていないゆえに、くだんの院生が食い下がるところの「絵の権利」が発生しなかったのだろうと理屈をこじつけてきたのです。
これには絶句してしまいました。今の私なら「もう今日限りで辞表をお出しになってはいかがでしょうプロフェッサー?」とキレてしまうかもしれませんが、当時の私は今より多少忍耐力があったか、それとも単に度胸が不足していたからか、そういう荒業には頼らず、もう少し腰の低い語りで、彼と、その院生さんには、アニメーション制作におけるキャラクターデザインの存在理由について、説明した気がします。気がしますというのは、もうあまり覚えていないからです。思い出すたびにだんだんと不快の念が高まっていくので、冷静に振り返る自信がなくなっているのです。
昨日、この行き違いについて、ふっとある閃きがありました。
夏目さんのまんが論、まんが研究は、ある非常に素朴な公理から組み立てられています。彼の公理を、絵で説明するとですね…

皆さんの目にはどう映っていますか? 小さな〇と、小さな線としか映っていないと思います。
ところが…

どうかな? 「顔に見える」と言っていただけると思います。
次にこうしてみましょう。

どうでしょう? 両手を広げている様に思えると思います。
さらに、〇の上に加筆すると…

表情になってきましたね。これが夏目理論です。極めて素朴な線や点が、重なっていくにつれて、そこにひとの姿が見えてきて、やがて人格や感情がそこに感じられだす… これが「まんが」の原初的な姿である—―
さてここから先は私の想像なのですが、この実に素朴な夏目理論を「公理」とするならば、こういう絵に「人格」とか「自律性」とかがあると見なして…

この、仮に「トラえもん」と名付けておきますがこのよくわからない絵を、仮想的な著名人と見立てて、そこからいろいろな権利が生ずる…そんな風に、夏目理論は拡張できるように、思われるかもしれませんが…

これ不可能です。もしトラえもんが、実在の、それも著名な方でしたら、そういうことはありえます。トラえもんさんは「人権」を有するということで、人権をコアにして、いろいろな権利が認められます。しかしトラえもんは、架空の存在ですので「人権」は認められず、ゆえに人権から派生する諸権利もありえないのです。
実在の著名人なら、先ほどの院生さんがねばるところの「絵の権利」にあたるものが認められます。

キムタクです。昨年(2022年)秋、新作映画の宣伝も兼ねて、岐阜県の県庁所在地でパレードを敢行したときの画像です。織田信長のコスプレで練り歩いています。岐阜市では毎年秋、信長コスプレパレードを行っていますが、このときは天下のキムタクが信長役ということで、市の人口がこの日だけ倍になりました。つまりキムタクのお姿には、そのくらいの集客力があるわけです。
すなわち彼のお姿は、知的財産です。他者が無断で使うと権利侵害となります。どういう権利の侵害かというと「パブリシティ権」の侵害とされます。桁違いの集客力を有する方ゆえに認められた権利です。
この権利は「人権」が最重要の根拠になっています。キムタクさまのお姿を、彼に(というか所属元であるジャニーズ事務所に)無断で二次利用したりしたら、キムタクの人権侵害にあたると、そういう考え方です。
しかし、これについてはどうかな?

ただの絵です。
もしこれがアニメやゲームや子ども向け商品などを介して大衆人気を得たとしても、やはりただの絵です。
大衆にとっては実在の人物(に限りなく近い存在感がある)と同じだったとしても、実在でないことに変わりはないので、ここには「人権」は認められません。ゆえにキムタクでいうところのパブリシティ権などのいろいろな派生的権利は、ここからは生じないことになります。

以上が法学における考え方です。大雑把ですがこういう風です。けれどもプロフ夏目さまはこういうことには疎いのです。しょせんまんが家上がりですからね。それでいてまんがの理論化を大学(ええと青山学院でしたっけ)の漫研時代から目論んでらして、そして先ほどご紹介した、こういう素朴な理論をこしらえたのです ⇩




素朴ゆえにわかりやすい、わかりやすいゆえに大衆受けはいいわけです。
その代わりに、空想的理論に終わります。ジャン・ジャック・ルソーが人権論を繰り広げたとき、原始社会がどうやって現代(彼の時代における現代)社会になっていったのかを論じましたが、その際の「原始社会」は考古学や人類学の知見とは無縁な、あくまでルソーの夢想のなかにしかない「原始」でした。そもそも考古学や人類学や進化論等が形になるのは、彼よりもっと後の時代のことでしたしね。
夏目まんが理論(&まんが史)は、ルソーの原始社会論と同じか、それにすら至らない代物だと今の私は考えます。彼のもとで講演して以後、私は現代コミックスの始原について、少しずつ研究を続けてきました。多言語翻訳者ゆえの強みです。そして、彼の理論と実際の歴史があまりにかけ離れていることが、はっきり形になって浮かび上がってきたのでした。
話が先走ってしまったので戻します。かの院生さんが粘ってきた「絵の権利」とやらは、夏目理論に染まった学生さんならばごく自然な発想だったのでしょうが、人権を有さないものにそういう権利はそもそも生じないのです。
法律の考え方では、そういうのは「不正競争」かどうかの判断となります。不正競争防止法というのがあります。実は講演のとき、この法について私はちゃんと触れていたのですが、どなたもよくわからなかったようですね。「風のフジ丸」でいけば、そして1965~6年当時ではなくもっともっと後の時代にもし白土と東映アニメのあいだでこの衝突が起きたとしたら、そしてもし裁判になったら「東映アニメ側の理屈は不正競争にあたるから否」と判断されると思われます。「原作とはもはや無関係にストーリーを東映アニメ側が作っているから白土はこのアニメとは無関係であり、利潤の分け前はないなどという理屈は、白土の得るべき利潤を不正に横取りするのと同じであるばかりか、もしこれを合法と認めたら以後いろいろな方面でいろいろな人間の手で応用的に悪用されるのは必至である、ゆえに認められない」と。
めんどくさいですよね。しかし法理論とはこういうものです。
私を含めて大衆は、こういうめんどくさい理屈は苦手です。もっと直観的にわかる説明を欲します。それで(誤って)広まったと思われるのが、こういうのでした。

とはいうものの、架空の存在それもただの絵でしかないものに「人権」を(疑似的とはいえ)与えるのはやはり無茶なので、こんな風にこじつけるのです。

「このネズミっ子はぼく・ウォルトの分身だよーん」と笑顔。こういう広報写真を介して、アメリカの大衆はずっと昔より、「架空の存在に人権を認める」というけったいな、はっきりいえば無茶苦茶な考え方を、受け入れていったのでした。
ただ、こういう広報写真の裏で、アメリカのアニメスタジオや出版社や新聞社など、利害関係者はもっと遥かに複雑怪奇な法理論を開発していったのです。ちなみに20世紀の前半のことです。先ほどご説明した「不正競争」の論法とか、いろいろ。
そのあたりのことをじっくり説明しだすと大著になってしまうので今はしません。要点をいうならば、大衆向けには「ミッキーくんは人気スターだからいろんな権利で守られているんだよー」と納得させて、しかしその理屈を成り立たせるための高度な法理論&慣習が何十年(それどころか一世紀以上)もかけて出来上がっていったということです。
私たちがパソコンを使う時、OSの仕組みについていちいち気にしませんよね。何か不具合が生じたときだけ「なにもしてないのにおかしくなった、なんとかしてー!!!」と騒ぎ出すぐらいで、普段はOSについて意識すらしない。それと同じです。
やっかいなのは、OSのことをろくに知らないし学んでいない方が、パソコン操作の権威として君臨している場合です。別に夏目さんがそうだったとはいいません。しかし限りなくそれに近いポジションにある(あった)ことは、否定できないと思います。
OS(ウィンドウズやアンドロイドなど)は自然発生ではありません。何十年のときとともに工夫され、バージョンアップされ、ときには世を混乱させながら今の姿に磨き上げられていったものです。それを子どものラクガキの延長であるかのように説いていった、彼の罪は非常に大きいものだと、今の自分は考えます。
こんな話を目にしたことはありませんか? 古代ギリシャのユークリッドが提唱した幾何学は、いくつかの公理をもとに幾何宇宙を生み出す優れものであったが、後のその公理のひとつが否定(というか除去)されると、それまで想定外の幾何空間が生まれてきた、その成果が、アインシュタインの相対性理論であった――

より踏み込んだ論は、後の機会に譲ります。その日まで、その日まで、今は笑顔でいましょうね~ ♪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
