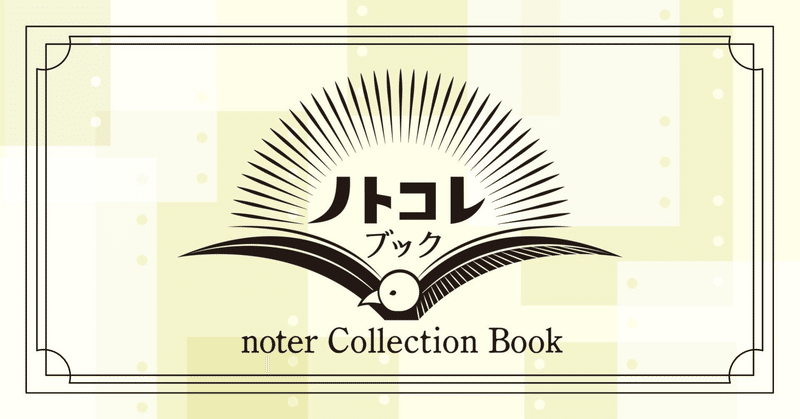
最初で最後のポートレート【ノトコレ応募】
『遺影の写真を、撮ってほしいの。』
突如入った母からの連絡に、しばらく連絡を取っていなかったバツの悪さと共に、淡々と書かれた一文に心が冷え切るような感覚がした。
母が遺影の撮影を依頼したのは、きっと私がフォトグラファーだからだろう。全国どこでも、依頼があれば駆けつけるライフスタイルから、実家に顔を出すのはおろか、連絡すらおざなりになっていた矢先のことだ。
3年前、父が亡くなった。その葬式以来、実家に足が向かなくなっていたのは事実だった。
父の容態が良くないと聞いていながら、全国を飛び回っていたのをいいことに実家に戻らなくなってから数年。父の最期を見守った母が暮らしていた家は、私が住んでいた時の面影がないほどに荒れ狂っていたのを覚えている。
これまで以上にないほど重要な依頼に、腰がさらに重たくなるのを感じた。でも、私が、娘が会いに行かないでどうする。
父を失った母は、ずっと1人で寂しかっただろう。唯一血のつながった私に送った、精いっぱいのSOSかもしれない。そう思うと、メールの返信を打つ手はスムーズに動いてくれた。
『週末、そっちに帰るね』
そっけない一文が、トークルームに浮かぶ。かわいいうさぎのスタンプがすぐさま送られてくるのを確認して、スマートフォンをスリープモードにした。
地元に帰る電車は、意外にも空いていてすんなり帰省することができた。
ビルが行き交っていた窓からの景色は、だんだんと緑が多くなり、いつの間にか山々に囲まれる。終点の小規模な駅に停車した電車から降りると、懐かしい景色が私を包んでくれた。
春のうららかさと初夏の兆しが垣間見える空の下で、一歩一歩を踏みしめながら歩みを進める。機材の重さもあり、身体が少し汗ばんでくるのを感じたころ、ちょうど実家の前に到着した。
玄関の前の枯れ果てていた植木鉢の行列は、跡形もなく片付けられており、いささか驚きを覚える。小綺麗になった玄関周りに逡巡しながらも、玄関の扉に手をかけた。
家の中には、どこか疲れ切った様子でほほ笑む母の姿があった。
「そろそろじゃないかと思って」と話しながら出迎えてくれた母は、父の葬式の時よりも小さくなったように感じる。
機材を持ってくれようとしたが、細い腕に重たい機材を持たせるのは酷だと思い、遠慮しておいた。
荷物を運びがてら家の中に足を踏み入れると、3年前とはうってかわって、殺風景な部屋に変わり果てていることに驚く。
3年間、母は1人で片づけ続けたのであろう。父と私の痕跡が残る家を、ずっと1人で。
殺風景な家の中でも、母は変わらず台所に立ち、私のためにお茶を入れて呉れようとしている。そのアンバランスさに、頭は混乱を深めていくばかりだった。
あんなに取っ散らかっていた家を片付けるのには、相当の努力が必要だったと思う。母の心境に、何か変化があったのだろうか。
もう家に帰らない二人の痕跡を片付けながら、母が抱えていただろう感情を想うと、過去の自分を叱責したい気持ちがこみあげてきた。
「それで、どんな感じで撮ろうか」
なるべく、暗いニュアンスにならないように努めながら、母に問いかける。母の前で、遺影だなんて言葉を使いたくなかったからだ。
少し考える素振りを見せた後、母はにこりと笑って答えた。
「笑っとるところを撮ってほしいねぇ。あの人は仏頂面しかなかったもんで」
そう言いながら父の眠る仏壇に目を向ける母。同じく仏壇に目を向けると、むっとした表情で私たちを見つめる父の姿が目に入り、思わず笑いがこみあげてきてしまった。
ひとしきり笑ったあと、とりあえず撮ってみるということで、バック紙の準備に取り掛かった。
白はシンプルだけど、どの場面にも相応しい色。母はお気に入りの服を着て、私が準備する様子を眺めていた。
そういえば、母の写真を撮るのははじめてだっけ。バック紙の前の椅子に母を座らせ、ポージングを指示しながらふと思い返す。
そう思うと、どこかむずかゆい気持ちになりながらも、夢中でシャッターを切った。
遺影の撮影を終えた私たちは、久しぶりに近所を散歩しようと外に出た。
こうして、母と一緒に歩くのはいつぶりだろうか。母の手を握って歩いていた私は、いつの間にかこんなにも大きくなり、母との距離ができてしまったように感じる。
「海に行こう」
そう言うと、母はニコリを笑って私の手を握った。小さなころ、母が私にしてくれた時と同じように。
海に到着してからは、持ってきたカメラで海を撮影していた。時折、話しかけてくる母の話に耳を傾けながら、沈みゆく夕日と海のはざまをたくさんカメラに収める。
すると、母がカメラの前に立ち、映りこんでくるようになったので、母のポートレート撮影会が始まった。
何度もシャッターを切るさなか、母がぽつりとつぶやいた。
「この瞬間を、永遠に切り取れたらいいのにねぇ」
零れ落ちた言葉の重みが、どすんと腹の中に落ちる心地がした。その言葉にどう答えてあげたらいいのかわからなくて、無力は私はただただ、シャッターを切り続ける。
その時は、この瞬間を少しでもあがいていたかったのだった。
それからほどなくして、母が亡くなった。母は末期がんだったのだ。
家が片付いていたのも、遺影の撮影を依頼したのも、すべて自分の終活のためだったのだと、この時に初めて思い知った。
母は、最期まで私に病気を黙っていた。それは、愛する家族に死が一歩一歩迫ってくるのを、隣で見守らなければいけないという恐怖を味わってほしくないという、母からのメッセージだったのかもしれない。
そのことに気が付き、母が息を引き取ったベッドの前で、声を枯らして泣き叫んだ。
母の葬式に使用した遺影は、無機質な白色のバック紙ではなく、夕日ときらめく海を背景に、無邪気にほほ笑む母の笑顔の写真を選んだ。
写真は、素晴らしくも愛おしい瞬間を切り取るもの。あの日の母は、永遠に輝き続けるのだ。
こちらはミムコさん主催の「ノトコレブック」、文学フリマ用の作品に応募させていただく作品です。
文字調整がうまくいかなかったので、とりあえず横書きに記載したWordをお送りします。
作品になるのが楽しみです!!ミムコさん、よろしくお願いいたします🌙
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
