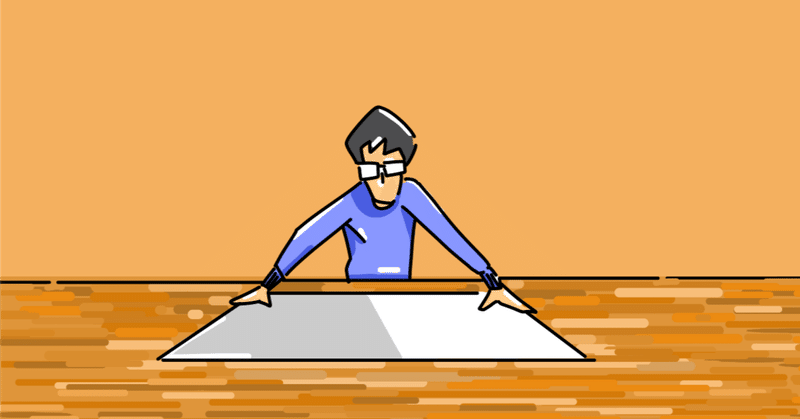
中小企業者の計画書は自分との約束事
中小企業にとって、計画書は本当に必要?
「取引先次第で変わるのに、先の計画を立てても意味がない」
「日々の仕事は繰り返しなんだから、計画書なんて必要ない」
「計画書がなくても経営はできる」
などなど。
「計画書は不要」とする声もよく聞くところ。
(ここでは、経営計画も事業計画も、ひとくくりに計画書として話を進めます)
もちろん、経営者の考え方次第ですが、中小企業支援のフィールドで働き続けて思うのは、やはり『必要』という結論です。
(『必要ない』と断言できたら、それはそれでカッコいいのですが)
診断士になりたての頃は「計画書は必要か」と聞かれたら、つい教科書的な理由を並べて「必要ですよ」と鼻息荒く説明していた気がします。
ですが、さまざまな経営者の方々と接して、経営者の価値観やこだわりもそれぞれ。相手に応じた理由を考えながら「案外、経営者自身のためになりますよ」と、肩の力を抜きながら話している気がします。
計画書は作っているか
実は、事業計画書は思うほど作成されていない。
2020年の小規模企業白書では、小規模事業者が計画書を「策定したことがある」者は52.5%、と半分ちょっと。残りの半数は策定していない。

作成しない理由の一つとして、経営者本人が「必要性を感じていない」ことも大きいかもしれません。
経営者自身が「作成する意義」に腹落ちがないと『実行に使える計画書』にはならない。労力が多いわりに「つくって終わり!」のカタチだけの計画書になる可能性が高くなります。
つくる意義
・これからの成長戦略とその実行計画を描くため
・従業員など社内に方向性や行動を伝えるため
・金融機関から資金調達する(条件変更する)ため
・補助金や助成金を獲得するため
といったことが考えられますが、結局は「経営者自身のため」なんだと思います。
計画書づくりは、経営者本人が、自分の会社をどうしたいか、を考えるプロセス。その成果物には、自分の思いや覚悟が詰まるはずです。
計画書はある意味、経営者である自分との約束事であり、契約書のようなものかもしれません。(もちろん、状況によって変更できるものですが)
経営者が本気で考えて、結果にコミットする計画書だからこそ、働く従業員や、銀行や出資者など外部の機関も動かすことにつながるんでしょうね。
特に家族経営のような中小企業の場合は、株主も同じであり、すべてが経営者の判断次第。GOサインやSTOPのサインは、本人以外、口を出せないことも多い。
だからこそ、自分がつくった計画書は、自らの判断がどうなのか、行動を振り返り、気づきを与えてくれる存在になれるものだと思います。
「思う」が計画書をつくる
経営の神様と言われた松下幸之助氏の「まず強く願うこと」という言葉は深い。その言葉は、京セラ創業者の稲盛和夫氏にも感動を与えています。
”“オレはこういう経営をしたい”と、ものすごく強い願望をもって毎日毎日一歩一歩あるくと、何年かの後には必ずそうなる。“やろうと思ったってできやせんのや。なにか簡単な方法を教えてくれ”というふうな、そういうなまはんかな考えでは、事業経営はできない。
“できる、できない”ではなしに、まず、“そうでありたい。オレは経営をこうしよう”という強い願望を胸に持つことが大切だ、そのことを松下さんは、言っておられるんだ。そう感じた時、非常に感動しましてね」
そんな強い思いが、言葉や数字となり、カタチになったものは、パワフルな計画書になるんでしょうね。
響くタイミング
といいながらも、計画書づくりは、必要性を感じない経営者には、響かないのも現実。
そういう方々にはタイミングが大事。
日々の経営とは違う局面、自身の経営を立ち止まって考えるようなときは、良い機会と言えます。
例えば、次のような変化のタイミングは、経営者に「強い思い」が生まれる機会。
・親から子への事業承継のとき
・M&Aで企業を買収するとき
・新規事業の立上げのとき
・金融機関に経営改善計画を提出するとき
他にもコロナ禍後の環境変化やAI・デジタル化対応など、外部環境に変化が起きているとき。などなど。
変化のタイミングをチャンスとしてとらえて「その波に乗れるよう計画書をつくろう」というマインドになれたらいいですね。
最後に
計画書づくりの技術的な本は多くありますが、経営者が計画書をつくることへの腹落ち(納得)させるような本は、なかなか出合えない気がします(笑)
計画書をつくったことのない経営者の方々に「計画書はいいもんですよ」と、うまく促せるようになりたいところです。
最初から立派な計画書をつくらなくとも、先ずは、自分の思いを言語化してみる、そこからお手伝いできたらと思います。
おわり。
