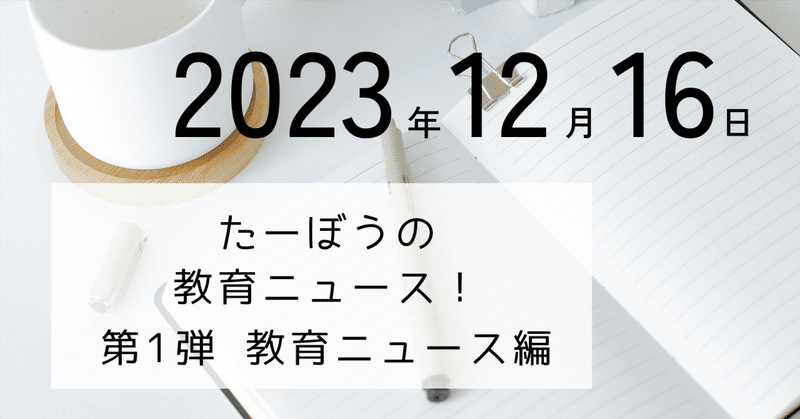
【たーぼうの教育ニュース①】 2023年12月16日(土)
こんにちは!たーぼうです!
今回は、かなり思うところもあって、ただでさえいつも長いのに、さらに長めです。誰か必要な人に届いたらいいな〜と思います。今日も思考の整理の一環で、実験的にゆるっとしたり、ガチっとしたりしながら、やっています。1日遅れですが、もし良ければご覧ください〜!
このニュースは、以下の3本立てで進めています。自身の勉強の一環で実験的にやっています。もし良ければテキトーにご覧ください!
・第1弾(土曜日):教育関連のニュース
・第2弾(日曜日):インタビュー・イベントの紹介
・※第3弾(不定期):SVPの活動紹介
ということで、本日は第1弾:教育関連ニュースです!よろしくお願いします!
■1:教育ニュース
12/7 dmenuニュース(琉球新報)
大学生の非常勤講師任用、6人採用 沖縄県議会で教育長が説明 大学生講師6人採用 教育
ーーーーー
沖縄県は特に教員不足が深刻化しているので、心配です。大学生も投入されることがニュースにもなっていましたが、採用も決まったようです。大学生が非常勤になっている例は他県でもありますが。
この一連のニュースを見て、特に思うのは、「大学生たち(新卒も含む)が現場で大切にされると良いな。」ということです。学生たちは優秀な人も多いですが、経験はほぼありません。
教員不足が進む中で、若手が即戦力になるケースが今後多発すると思います。現場にいる私も含めた先輩教員たちは、生徒を育てることももちろんですが、若手教員を丁寧に育てられるかどうかが今後の学校の在り方に大きく作用します。とにかく今回採用された沖縄の大学生たちものびのびと育ってほしいなと思います。きっと優秀な人たちなので、素敵な現場の先輩に巡り合って、頑張ってほしいなと思っています。
若手たちはそれぞれの時代に沿った価値観を持っていることが多いので、先輩たちの学び直し(アンラーン)が必須です。自己流の育て方も限界がありますし、相性もあります。また指導教員だけが育てるのも噛み合わない場合など、負担も大きいです。
職場全体で若手を育てる意識が大事です(色々と自戒も込めて)。学校が生徒だけでなく、先生ものびのびと育つ場になったら良いなと思います。
■2:生徒指導ニュース
12/14 教育新聞
生徒指導提要改訂で学校は変わったか(室橋祐貴さん)
ーーーーー
生徒指導提要(国が定期的に改訂している生徒指導のめっちゃ大事なガイドライン)が昨年の12月に出されてから、1年になりました。生徒指導提要はとてもよくできているので、読める人は1度読んでみるのが良いと思います。そしてこの室橋さんの記事はとても素晴らしいです。
大前提は上記の通りです。
ですが、ちょっと別の角度から書かせてもらいます。
生徒指導提要の認知は現場ではとても弱いと思います。改定されたことの周知は弱いし、全員に冊子が配られる訳でもないし、講習があればいいけど、そうでもないし。誰かが研修を受けて、それがサクッとだけ資料として、共有されるだけだしとも思います。 記事自体は良いものだし、読んだ方が良いのは確かなんですが。多くの先生に読む時間があるかというと、そうでもないような感じがします。(まぁサボっている人もいるとは思いますが) 職員会議で共有される自治体からの通知も多過ぎて、正直見ないものが多いなと感じます。
教員に限った話ではないかもしれませんが、どの職業にもおそらく「〇〇なら知っていて当然だろ!?」というものが、世の中には多いなと思います。
ちなみに私は、最近流行りの生成AI関係は正直弱いです。あんまりわかっていません。いずれは本くらいは読もうとは思っていますが、まだちょこっとだけです。だから「この時代に教員のくせに生成AIについての本も読んでないなんて、終わっている」とか言われると悲しくなります。
さらに言うと、歴史の教員ですが大河ドラマも全部見ている訳ではありません。見る年もあれば、見ない年もあります。大河ドラマ見ると、教材研究モードに入ってしまうので、リラックスできない時も結構あり、見ない時もありました。だから「歴史教員なのに、大河ドラマを見ていないなんて終わっている」とか言われると、さらに悲しくなります。
教員はもうすでに現場で必死に頑張っているので、これ以上いろんなものを求められるのも、正直ちょっとしんどいな〜とも思います。
「〇〇なんだから、知っていて当然だろ!?」という投げかけで苦しんでいる人たちがとてもいるだろうなと思います。当然の感覚なんて人それぞれです。ここで話題になっている子ども権利についても、これからの教育改革のキーワードになると思いますが、研修受けることもまだ少ないと思います。
あと、生徒指導提要はちゃんとは読んでないだろうけど、そこに書いてあるようなことは、すでに実践している。という人も多くいると思います。(もちろんそうでない人がいるのも事実でしょうが。)
ちなみに私のお世話になっているNPO法人School Voice Projectは生徒指導提要のポイントについてまとめてくれているので、そこ読むだけでも全然良いと思います。私もネット記事から見始めました。
生徒指導提要は私は見た方が良い立場だったし、必要だったので、読みました。ただ、別の分野とかになると、それができていないことも普通にあります。
「知っておいた方が良いもの」は世の中には腐るほどあります。でも求められ過ぎている感じもします。そういった部分も改善の余地があるのではないかと思いました。
記事自体は素晴らしいのですが、ちょっと別の角度から書かせてもらいました。様々な改善があると、もっと生徒指導提要の大事な部分も現場に浸透していくのではないかと思います。
※参考
NPO法人School Voice Project 学校を良くするメディア「メガホン」
【解説記事】校則見直しや子どもの権利も明記! 12年ぶりの「生徒指導提要」改訂のポイントとは?
■3:探究・キャリア教育ニュース
12/15 長崎新聞
学力検査で「探究的な学び」導入へ 長崎県の公立高校入試改革 2025年の受験生から
ーーーーー
長崎県で「探究的な学び」が高校入試に出てくるようです。ここでは探究ではなく、「探究的な学び」となっているので、読解力重視の傾向になるのだと思います。
「探究」と「探究的な学び」は、同じようでだいぶ異なると私は思っています。とてもとても雑に分類すると、探究はテーマ自由型が多く、深め方もある程度自由。探究的な学びは、既存教科内などで行われるテーマに制限が多いものと思っています。(←めっちゃ雑です)
記事から、引用です。
例えば国語は、地元産品を使った商品開発について意見を交わす場面を取り上げ、受験生は、生産者の希望も踏まえて意見をまとめ、合意を得られる提案を回答する。ほかの教科も、日常生活や身近な場面から出題したり、提示された資料を根拠に考えを求めたりする。
これを機に、中学校でも探究が本格的に進むであろうと思います。どこかに問題があるようなので、探してみたのですが、見つかりませんでした。入試が終わったら過去問でチェックせねば。
探究が本格化するきっかけになりそうなので、良い傾向だなと思います。長崎県としても、一連の入試改革の中でチャレンジしたことはとても素晴らしいです。
ただ、反面心配もあります。探究は、かなり評価するのが難しいからです。基準がどの提示されているのか、気になるところです。(作問者・採点者ともに大変だろうなと思います。)
特に探究は、その人に内在する見方考え方に左右されます。問いも表出の仕方はそれぞれです。もちろんロジカルに考えたり、日常に結びつけることは大事ではあります。
ただ、探究は日常に結びつけなくても良いと私は思います。(日常に結びつけることが基本ではありますが、もっと探究の守備範囲は広いと思います。)受験で扱われるようになることで、正解主義のようなものに探究がなってしまわないと良いなと感じます。(やらされ探究・正解を教えられる探究になると、ちょっと探究の良さが消えてしまう心配があります。探究はとても面白い評価なので。)
ここでは、探究的な学びの方ですし、上記の例では合意形成というゴールが明確なテーマなので、試験用にうまく作問されているのでしょう。問題を見ていないので、中学校でこれを教えたりするのは大変だな〜と思います。
今年度からということで、今後に注目したいなと思います。
※参考
12/12 教育新聞
探究方法の指導に課題感 福島県内の高校教員の半数超
福島県でも調査や対策などが行われているようです。
■4:働き方改革関連ニュース
12/13 教育新聞
「次期指導要領は現場負担に配慮を」 中教審部会で意見相次ぐ
ーーーーー
PISAの結果を踏まえ、中教審でも議論が進んでいます。ここでは様々な意見が出ているのでさすがだなと思います。負担の軽減を求める意見が出ていることも現場としてはありがたいです。
とにかく、タイトルの通り、負担が増えないことを祈るばかりです、学習指導要領は辞典のように分厚くなり、特に小学校では悲鳴が上がっています。
探究の導入など、とても意義深いものもありますがが、減らしていくことを考えないとまずいです。
教育以外もそうですが、人口減少により日本は曲がり角に差し掛かっています。とにかく10年後には次の学習指導要領が分厚くならないことを祈るばかりです。
また同時に現場でできることを模索したいなと思います。いくら上層部が議論をしようとも、現場を変えるのは私たちの小さな実践だと思います。その精神を忘れずに日々を過ごしたいと思います。
第2弾:インタビュー・イベント紹介はこちらです!
以上です!お読み頂き、ありがとうございましたー!!
またお時間があればご覧ください〜!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
